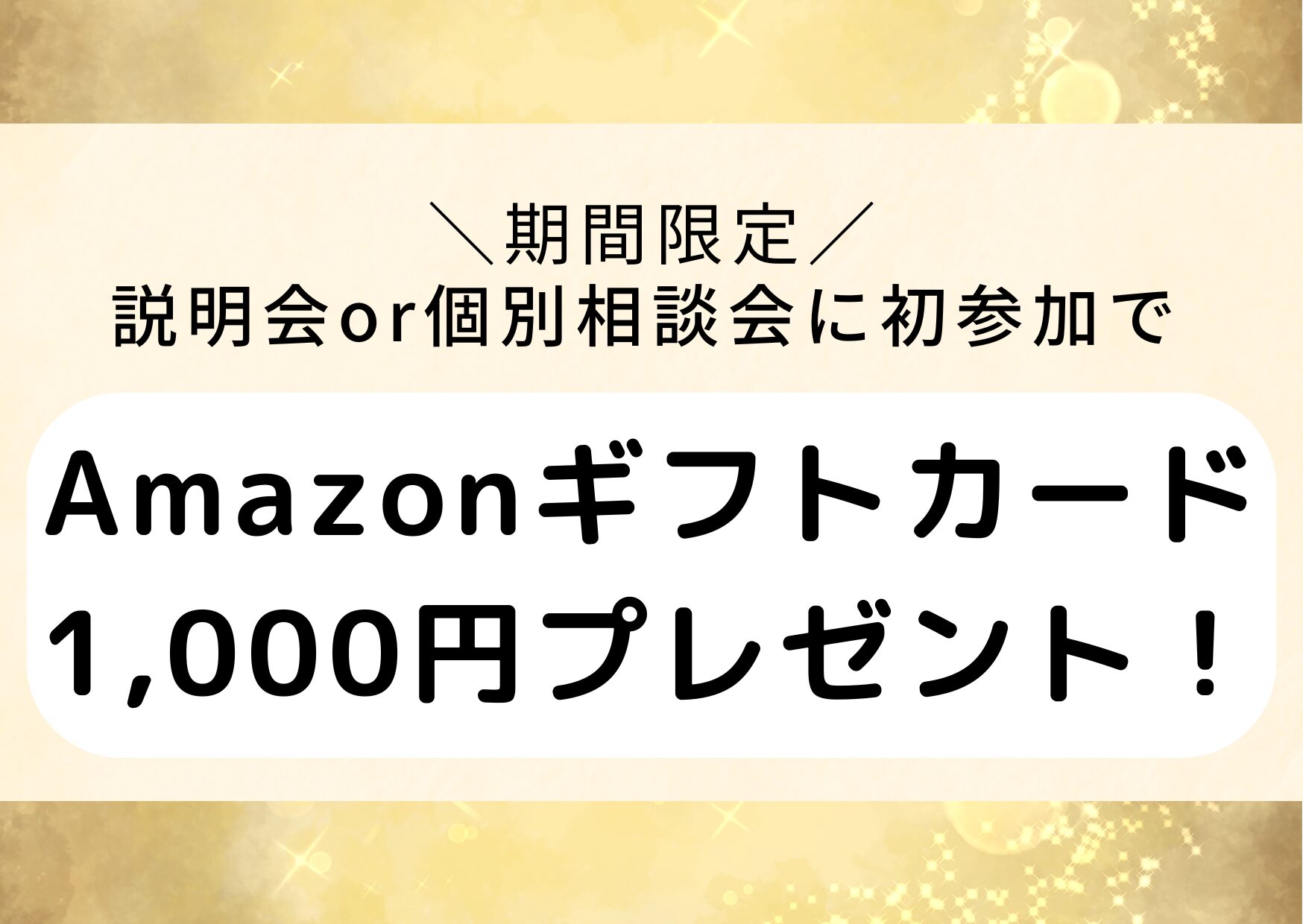不登校で挫折してからの逆転劇。通信制高校で人生を変えた27歳女性の物語:教育者からエンジニアへ
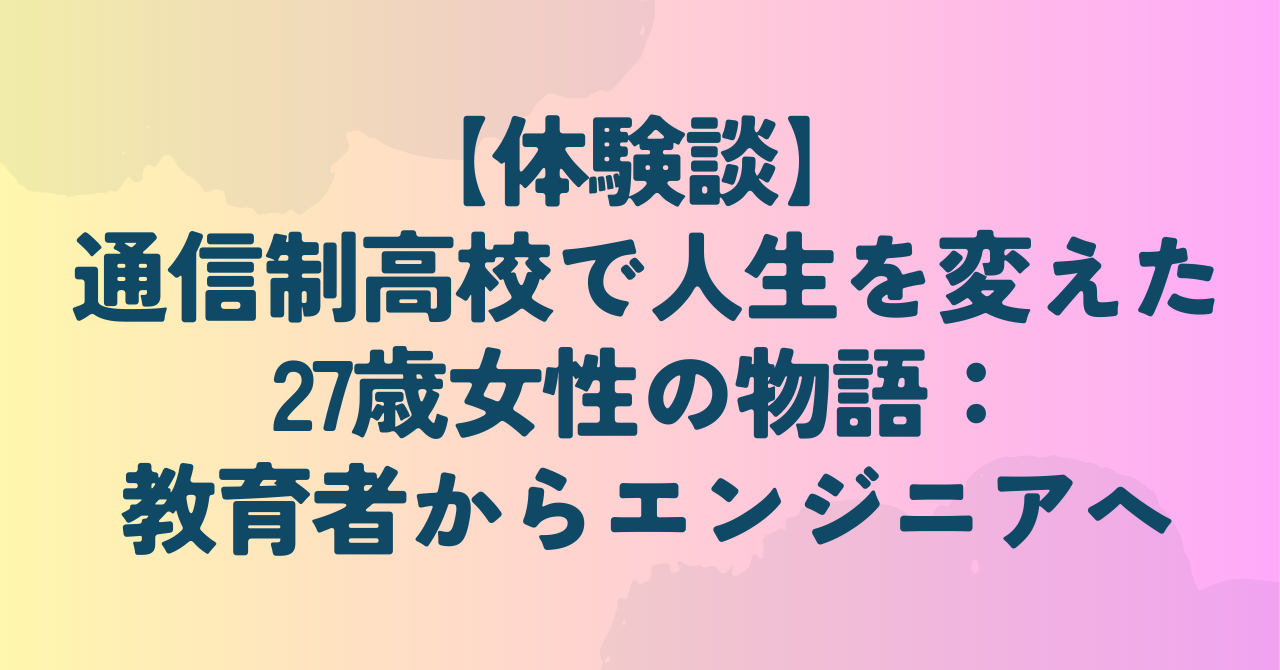
はじめに:自分の居場所を見つける旅
教育の現場において、不登校は依然として大きな社会問題となっています。文部科学省の調査によると、2023年度の小中学校における不登校児童生徒数は過去最多を更新し、30万人を超えました。その背景には様々な要因があり、一人ひとりの事情は千差万別です。
本記事では、小学生の頃からいじめに遭い、家庭環境の複雑さも相まって不登校を経験し、境界性パーソナリティ障害と診断されながらも、自分自身の道を切り拓き、通信制高校の教諭として多くの生徒の支えとなってきた27歳女性の実体験をお届けします。現在はエンジニアへの転職を目指す彼女の物語から、不登校の子どもたちや保護者の方々、そして教育関係者にとって、新しい視点や希望を見出していただければ幸いです。
幼少期から続いた「居場所のなさ」:国立小中学校時代の苦悩
国立の小中学校に受験して通っていた彼女の学校生活は、決して平坦なものではありませんでした。小学1年生という幼い時期から、同級生の女子2人からのいじめを受け続けていたのです。出席番号が隣だったことから、常に近くにいる機会が多く、毎日のように悪口や陰口を言われたり、トイレに閉じ込められたりする日々を送っていました。
「なぜいじめられているのか、なぜ仲間外れにされるのか、当時は全く理解できませんでした。先生に相談しても『いじめられる側にも問題がある』と言われたことが今でも鮮明に記憶に残っています」
小学校3年生の頃には、家庭環境も大きく変化します。父親が職場での人間関係から躁鬱病を発症し、3年間の休職を余儀なくされました。その間に母親も鬱病を発症し、家庭内は両親の喧嘩が絶えない状況となりました。3人姉弟の長女であった彼女は、幼い心に大きな責任を感じていました。
「下の2人の面倒を見なければならないという責任感を強く持っていました。私がしっかりしなければこの家は壊れてしまう、という思いが常にありました。自分の意見を押し殺し、相手に合わせることが習慣となり、自分に自信が持てなくなったのはこの時期からだと思います。ニコニコしておけばいい、という処世術をこの頃に学びました」
この困難な家庭環境と学校でのいじめが重なり、わずか9歳にしてリストカットや希死念慮を経験するようになりました。最初のリストカットは学校でハサミを使用していた際、手の甲に傷をつけたことがきっかけでした。
「いくつも傷をつけた後、友達が保健室に連れて行ってくれました。周囲が心配してくれたことが、リストカットを続けるきっかけになったと思います。しかし、最初のリストカットが母親に発覚した時、『ハサミで切るだけで心配されるなんて。私もやりたいわ』と言われたことは今でも忘れられません」
中学時代:いじめられる側からいじめる側へ
中学生になると、彼女の行動パターンに変化が現れます。「いじめられる側は嫌だ」という強い思いから、今度は自らがいじめる側に回るようになりました。注目されることや虚勢を張ることで、自分の存在価値を示そうとしていたのです。
「この時期は、後に境界性パーソナリティ障害と診断される症状が強く出ていました。先輩に突然告白したり、同級生とキスをしたりと、12〜13歳としては非常に衝動的な行動を取っていました」
家庭でも学校でも居場所を見出せない彼女は、次第に問題行動が増加していきました。今振り返ると、それらの行動は周囲からの関心や愛情を求めるものだったと語ります。
「誰でもいいから愛して欲しかったし、自分を受け入れて欲しかった。ただ話を聞いて欲しかったんです。それが親からも先生からも得られなかったため、出会い系サイトで知り合った男性や塾の先生と交際し、愛情を求めて身体を捧げて必要とされようとしていました」
高校進学と不登校:自分探しの始まり
公立高校に進学した彼女を待っていたのは、厳しいスケジュールと新たな環境での居場所のなさでした。朝6時に起床して学校へ行き、予備校で22時まで予習をするという生活が続きました。
「元々小学生の頃から塾には通っており、勉強自体は嫌いではなかったのですが、『明日までにここまで終わらせて、確認テストを受ける』という毎日に追われることが辛かったです。自分のペースで勉強できず、強制的に詰め込まれる日々に嫌気が差していました」
さらに、学校の国公立大学合格至上主義とも言える方針に疑問を感じるようになりました。「国公立大学に進学することだけがゴールではないのでは?」という思いが日に日に強くなっていったのです。
高校1年生のゴールデンウィーク明けから、彼女は学校に行けなくなりました。きっかけは些細なことでした。
「体操服を忘れました。取りに帰ったら電車に遅れる。誰かに貸してもらおうか?でもなんでこんなに頑張らないといけないんだろう、何を目指しているんだろう。体操服を忘れたくらいで、なぜこんなに必死に言い訳を探さないといけないんだろう…と考えているうちに、電車に乗れなくなりました。そのまま家に帰り、不登校が始まったのです」
不登校を選択した後の周囲の反応は様々でした。母親は受け入れることができず寝込んでしまいました。お金をかけてここまで育ててきたのに、という思いからでしょう。一方、父親は比較的冷静に受け止め、通信制高校の見学に同行してくれるなど、サポートを示してくれました。友人たちもノートを届けてくれるなど、彼女の復学を支援しようとしてくれました。
通信制高校との出会い:人生の転機
不登校となった後、彼女は進路について考えるようになります。地元には公立の定時制高校もありましたが、卒業までに4年かかることや卒業率の低さを知り、私立の通信制高校を検索して見学に行きました。中学校時代の友人も通信制高校に転校していたこともあり、選択肢として頭にあったそうです。
通信制高校への転校を決めた際には、今までの勉強の積み重ねが無駄になるのではないかという不安がありました。しかし同時に、校則がなくなりアルバイトも自由にできること、登校日数も自分で選べるという点に大きな魅力を感じていました。
「通信制高校での学びは、自分が好きなことを自分のペースで学べる点が全日制と比べて格段に合っていました。授業がない日にアルバイトをしていたのですが、そこで外国人のお客さんと知り合い、英語に興味を持つようになりました。それがきっかけで海外に一人で旅行に行ったり、大学では外国語を専攻したりと、自分の興味に従って学ぶ機会を得られました。これは型にはまった公教育では絶対にできなかったことだと思います」
通信制高校との出会いは、彼女にとって人生の大きな転機となりました。
「自分の人生を終わらせたいと思っていた時に出会った通信制高校。そこでたくさんの仲間と信頼できる先生たちに会い、自信を取り戻すことができました。自分の力を引き出してくれる場所でした。通信制高校での思い出は、人生の中でも忘れることのない大切なものです」
教育者としての道へ:同じ経験を持つ者だからこそできること
大学卒業後の進路選択においても、彼女のストーリーは偶然と必然が交差します。大学4年生の就職活動では、志望企業1社のみを受けて落選。他の企業のことは考えておらず、このままフリーターになろうかと悩んでいた時、通信制高校時代の恩師に相談の電話をしたところ、「ここで働かない?」と誘われ、母校での教員としての道が開かれました。
「通信制高校の教諭として、自分の経験を生かして生徒と向き合うことができました。生徒の辛い気持ち、保護者の方の苦しみは、他の職員よりも理解できると自負しています。自分が実際に経験したからこそ、一人ひとりに寄り添うことができたと思います」
彼女の教育方針で特徴的だったのは、生徒を「子ども」ではなく「一人の人間」として接することでした。その姿勢が生徒との信頼関係を築き、多くの生徒と深い関わりを持つことができたのです。
新たな挑戦:エンジニアへの転身
5年間の教員生活を経て、彼女は新たな挑戦を決意します。30歳を前に未経験の職場への転職を考えるようになったのです。
「少人数の職場だったので、大人数と一緒に働いてみたいという思いや、次は子どもではなく大人と一緒に働きたいという気持ちが、学校を離れようと思ったきっかけです。エンジニアという職種を選んだのは、場所に縛られない働き方や、自分の頑張り次第で年収を上げていける点に魅力を感じたからです。将来的には経営者やフリーランスを目指しています」
人生を振り返って:障害を抱えながらも見出した希望
境界性パーソナリティ障害の診断を受けたのは大学4年生の時でした。それまでは思春期ということもあり、明確な診断名はつけられていませんでした。高校生で不登校になった時から精神科には通院していましたが、大学4年生の時に再度希死念慮とリストカットがひどくなり、別の病院を受診した際に診断されたのです。
「治療としては安定剤の投薬が主でした。周囲のサポートはほとんどなく、親しい友人1人を除いて誰にも伝えていませんでした」
自身の人生を振り返り、彼女は三つの大きな転機があったと語ります。
「生きることを諦めなかったこと、通信制高校に転校したこと、そして仕事に一生懸命打ち込んだ5年間です。生きることを諦めず、自分で学校を辞める決断をし、責任と役割を持って仕事に打ち込んだ日々は、パーソナリティ障害の症状を緩和させてくれました。誰かに必要とされることが、私の心を安定させてくれたのです」
同じ境遇にある若者たちへのメッセージ
自らの経験から、同じような状況にある若者たちに向けて、彼女はこう語ります。
「通信制高校へ通うことについて、まだまだ偏見や差別があるかもしれません。でも自分で選んだその選択は素晴らしいものです。人と違う選択肢を選んでよかったと思える日が必ず来ます。色々な学校を見学して、自分に最も合った場所を選んでみてください」
困難な状況にある子どもたちを支える大人たちへ
最後に、困難な状況にある子どもたちを支える大人(親・教師・支援者など)に向けたメッセージを彼女は熱く語ります。
「困難な状況にある時に最も辛いのは子ども自身です。学校に通えなくなった子どもは、自分のことを一番責めて苦しんでいます。私も不登校の半年間は、毎日朝が来るのが怖かったです。みんなができることがなぜ自分にはできないのか、自分はいなくなった方がいいのではないか、と毎日考えていました」
「『学校に行きなさい、なんで行かないの?』と言うのは簡単です。でも、それが子どもをもっと苦しめることだということを知ってほしいのです。行きたいのに行けないんです。それを上手く言葉で表せないから、不登校という行動で表しているのです。しかし、本人もどうしていいのか分からないのです」
彼女は支援する大人の役割として、次の一歩を提案することの重要性を強調します。
「サポートしてくれる大人は、次にどうしたらいいかを提案することが大切です。転校するために学校見学に行ったり、少し勉強を促してみたり、病院を受診してみるなど。困難な状況では子どもたちは自分で先のことを考えるエネルギーもありません。少し先の未来を提案してあげてほしいのです。誰からも何も言われなかったら、不登校や引きこもりの状態が長引いてしまいます。適切な声掛けや、発達障害、精神疾患の基礎的な知識も必要です」
まとめ:不登校を経験したからこそ見えた景色
彼女の物語は、不登校や精神疾患という困難を経験しながらも、それを乗り越え、むしろその経験を糧にして教育者として多くの子どもたちの支えとなり、さらに新たな挑戦に踏み出す姿を描いています。
不登校は決して人生の終わりではなく、むしろ新たな始まりとなり得ること。型にはまった教育だけが全てではなく、一人ひとりに合った学びの形があること。そして何より、どんな状況にあっても、自分の力で道を切り拓いていくことができるという希望を、彼女の生き方は教えてくれています。
通信制高校から大学へ、そして教育者となり、今またエンジニアという新たな分野へ挑戦する彼女の姿は、不登校や精神的な困難を抱える若者たちにとって、大きな励みとなるでしょう。同時に、そうした子どもたちに関わる大人たちに対しても、支援のあり方について深い洞察を与えてくれています。
人生は決して一直線ではなく、様々な曲がり角や困難に直面します。しかし、それらを乗り越えながら、自分だけの道を見つけていくことこそが、真の意味での「自分らしく生きる」ということなのかもしれません。彼女の物語が、多くの人の心に希望の灯をともす一助となることを願ってやみません。