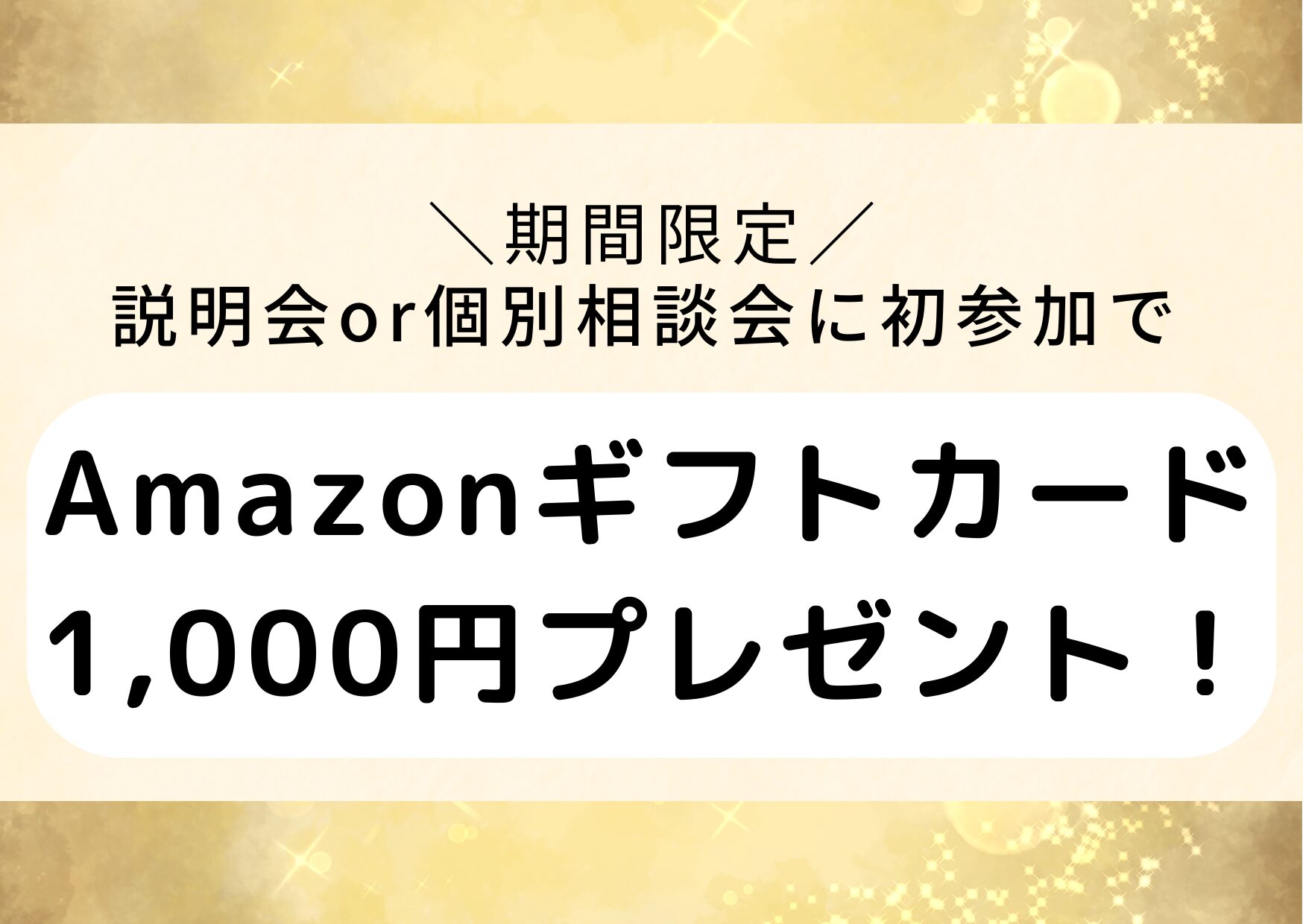【実体験】不登校、通信制高校から興味関心のあるプログミングなどを学び社会人へ:私の道のり
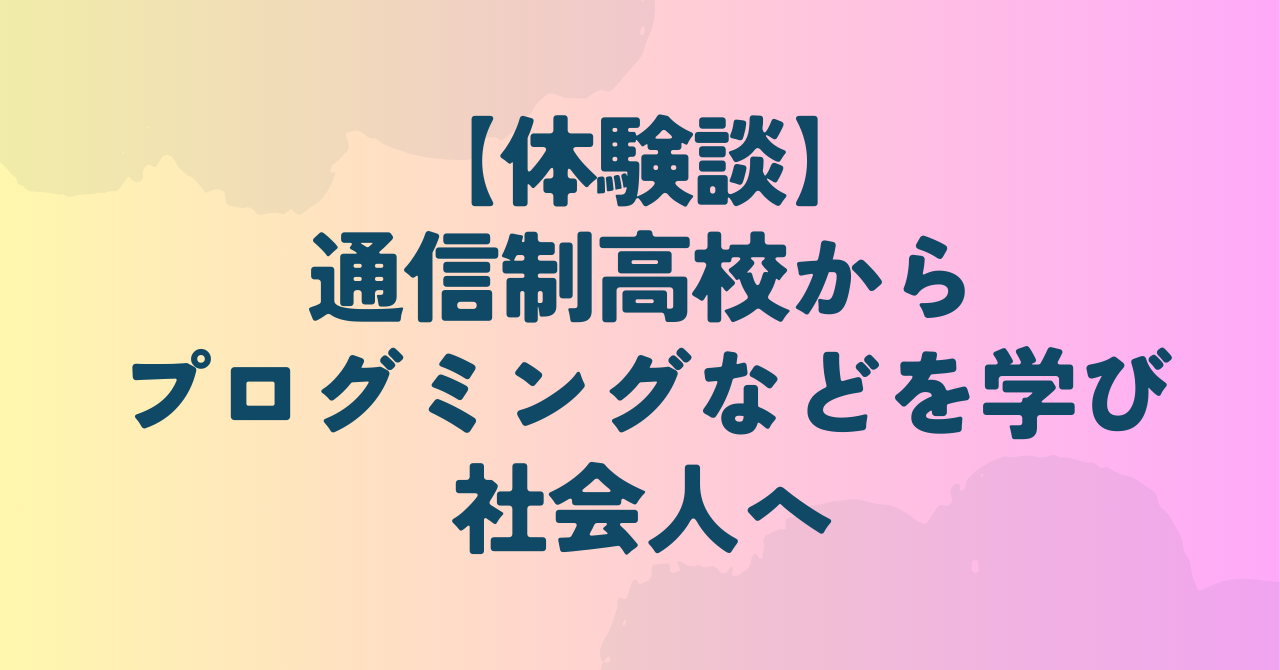
「空気が読めない子」というレッテルと中学時代の苦悩
明確な一つの出来事というより、日々の小さなズレの積み重ねが私を「空気が読めない子」というレッテルへと導きました。グループワークで皆が盛り上がっている話題に素直な疑問を投げかけてしまったり、休み時間に一人で本を読んでいることが多かったり。周りからは「協調性がない」「何を考えているかわからない」と思われていたようです。悪意はなかったのですが、クラスの「普通」とされる振る舞いから浮いてしまい、次第に「空気が読めない」というレッテルが定着していきました。そのレッテルが、ますます私を孤立させていったように感じます。
学校に行けなくなった決定的な瞬間
中学2年の秋、体育祭の練習が続く時期に転機が訪れました。ある朝、制服に着替えようとしたのですが、体が鉛のように重く、どうしても動かせませんでした。玄関に向かおうとしても、足がすくんで前に進めなかったのです。学校での疎外感や、集団行動への強いプレッシャーが限界に達していたのでしょう。涙が止まらず、親に「行けない」と告げるのが精一杯でした。感じていたのは、恐怖と、どうしようもない無力感、そして「自分はダメなんだ」という深い絶望感でした。
保健室登校の試みとその限界
親や先生の勧めもあり、一時的に保健室登校を試みました。保健室では、ベッドで横になったり、持参した本を読んだりして過ごしました。養護の先生は優しく話を聞いてくれましたが、教室への復帰を前提とした関わりに感じられ、根本的な解決にはならないと感じていました。他の生徒が授業を受けている音を聞くと、自分が取り残されているような焦りや罪悪感も募りました。結局、保健室も「学校」という枠組みの中であり、私にとっては心安らぐ場所にはなりえず、数週間で足が向かなくなりました。
自責の念からの解放と学びの喜びの発見
最初の頃は「学校に行けない自分は怠け者だ」「親に迷惑をかけている」と、ひたすら自分を責めていました。転機になったのは、親が「焦らなくていい」と私の状況を受け入れてくれたこと、そして自宅で好きなことに没頭する時間が増えたことです。特にパソコンやインターネットに触れ、自分の興味関心に従って情報を集めたり、簡単なプログラミングを試したりする中で、「学校の勉強だけが学びではない」と気づきました。強制されるのではなく、自ら知りたいことを探求する喜びを知り、少しずつ「これでいいんだ」と自分を肯定できるようになりました。
インターネットとの出会いが開いた新たな世界
当時の私にとって、インターネットはまさに世界への「窓」でした。学校という狭いコミュニティしか知らなかった私にとって、オンライン上には無限の情報と、多様な価値観を持つ人々が存在していました。趣味のフォーラムで同じ興味を持つ人と匿名で交流したり、海外の情報をリアルタイムで知ったりする中で、自分の悩みがちっぽけに感じられる瞬間もありました。顔や名前を知らない相手となら、気負わずに本音で話せることもありました。物理的に家にいても、精神的には世界と繋がっている感覚が、孤独感を和らげ、視野を広げてくれました。
親の理解と支えがもたらした変化
両親は最初こそ戸惑い、心配していましたが、私が学校のことを話すだけで体調が悪くなる様子を見て、無理強いするのは良くないと判断してくれました。不登校に関する本を読んだり、専門機関に相談したりする中で、少しずつ理解を深めてくれたのです。「学校に行かなくてもいい。あなたのペースで考えよう」と言ってくれた時の安堵感は忘れられません。親の理解と受容が、私が自分を取り戻すための大きな支えとなりました。
母との学びの時間
母は、私が興味を示した分野の本を一緒に読んでくれたり、教科書の内容で分からない部分を隣で一緒に考えたりしてくれました。特に歴史や文学が好きだったので、関連する本を図書館で借りてきて、感想を話し合ったりもしました。単に勉強を教えるというより、対等な立場で一緒に学ぶ、という姿勢が嬉しかったです。その時間は、学力維持だけでなく、母とのコミュニケーションを深め、私が社会から孤立していないと感じさせてくれる貴重な機会でした。母の存在が、学びへの意欲を繋ぎとめてくれた側面も大きいと思います。
親のサポートで心に残ったこと
一番心に残っているのは、「あなたの人生なのだから、最終的にどうするかは自分で決めていい。私たちはそれを応援する」と言ってくれたことです。この言葉は、私に責任感と同時に大きな安心感を与えてくれました。また、無理に外出を促すのではなく、私が「図書館に行きたい」と言った時に黙って付き添ってくれたり、興味を持ったパソコン関連の書籍を買ってきてくれたりしたことも、私の世界を広げる手助けになりました。結果を急がず、子どもの興味や小さな変化に寄り添い、信じて見守る姿勢が、何よりの支えになるのだと思います。
学校外での居場所と支え
親以外では、やはりインターネットの世界が大きな支えでした。オンラインゲームで協力プレイをしたり、趣味のコミュニティで情報交換をしたりする中で、学校とは違う人間関係を築くことができました。顔が見えないからこその気楽さもありました。また、近所の図書館も大切な居場所でした。静かな空間で好きなだけ本を読める時間は、私にとって何よりの癒しであり、知的好奇心を満たす場でもありました。特定の誰かというよりは、自分の興味関心を通じて繋がれる世界や、一人で落ち着ける場所が心の支えになっていたと思います。
高校進学と通信制高校での学び
中学校には、最終的にほとんど復帰しませんでした。籍は置いたままでしたが、自宅学習が中心でした。義務教育の修了は、出席日数などの要件を満たしていたため、形式的には卒業という形になりました。高校進学にあたっては、全日制の高校に通う自信がなかったため、自分のペースで学べる通信制高校を選びました。レポート提出とスクーリングが中心の学習スタイルは、私に合っていたと思います。中学時代の経験から、画一的な環境ではなく、多様な学び方が認められる場所を求めていました。
大学進学の決断と選択基準
大学進学を決めたのは、不登校期間中に興味を持った情報科学や社会学について、もっと深く専門的に学びたいという気持ちが強くなったからです。また、同世代との交流や社会との接点を持つことへの意欲もありました。大学選びでは、学びたい分野の専門性に加え、自由な校風や学生の多様性を重視しました。不登校の経験から、偏差値や知名度よりも、自分がのびのびと学べる環境かどうか、多様な価値観が尊重される場所かどうかを大切に考えました。集団に馴染めなかった経験が、逆に自分に合った環境を見極める目を養ったのかもしれません。
大学生活での新たな発見
大学生活で印象に残っているのは、やはりその自由度の高さです。授業選択から時間の使い方まで、自分で主体的に決められる環境は新鮮でした。様々なバックグラウンドを持つ友人との出会いも刺激的で、中学時代には考えられなかったような多様な価値観に触れることができました。不登校の経験があったからこそ、当たり前のように大学に通えること、学びたいことを学べること、友人と語り合えることのありがたみを強く感じました。ゼミでの専門分野への没頭や、サークル活動での交流は、自己肯定感を高める貴重な経験となりました。
社会人としての最初の挑戦
社会人になって最初に感じたのは、やはり組織への適応と人間関係構築への不安でした。不登校経験から、集団の中でうまくやっていけるか、期待に応えられるかというプレッシャーは大きかったです。就職活動でも、不登校の過去をどう伝えるべきか悩みました。乗り越えられたのは、まずは目の前の仕事に集中し、スキルを磨くことで自信をつけようと努めたからです。また、幸運にも理解ある上司や同僚に恵まれ、少しずつ職場に慣れていくことができました。小さな成功体験を積み重ねることで、「自分にもできる」という感覚が育っていったように思います。
転職と新しい環境への挑戦
不登校の経験を通じて、「道は一つではない」「環境を変えることで状況は好転しうる」ということを身をもって学んだのが大きいと思います。一度社会のレールから外れた経験があるからこそ、既存の枠組みにとらわれず、自分の興味関心や成長の機会を求めて新しい環境に飛び込むことへの抵抗が少ないのかもしれません。変化は不安も伴いますが、それ以上に新しい知識やスキル、出会いを得られる成長の機会だと捉えています。キャリアは積み上げるだけでなく、時に横に広げたり、方向転換したりすることも大切だと考えています。
不登校経験が育んだ社会人としての強み
強みになっていると感じる部分はいくつかあります。まず、人の痛みに寄り添える共感力です。自分が苦しんだ経験があるからこそ、相手の立場や感情を想像しやすくなりました。これは顧客対応やチーム内でのコミュニケーションに役立っています。また、画一的な考え方にとらわれず、多角的な視点から物事を捉えられる点も強みです。困難な状況に直面した際の粘り強さや、自分で考えて道を切り拓く力も、不登校の経験で培われた部分かもしれません。独自の視点を活かした企画提案や、問題解決へのアプローチに繋がっていると感じます。
生成AI分野への関心
不登校時代にパソコンやインターネットに救われた経験から、テクノロジーが持つ可能性には元々強い関心がありました。プログラミングも独学でかじっていた時期があり、その延長線上でAI技術の進化に注目するようになりました。特に生成AIが、文章や画像、音楽などを創造できることを知り、そのクリエイティブな側面に強く惹かれました。かつて自分がインターネットの世界に新しい可能性を見出したように、生成AIもまた、人間の能力を拡張し、新しい価値を生み出す「窓」になるのではないかと感じ、深く探求したいと思うようになりました。
フリーランスとしての決断
これまで複数の事業運営や業務委託を経験する中で、組織に属する働き方と、より裁量権を持って自分のペースで働くスタイル、双方のメリット・デメリットを実感してきました。生成AIという新しい分野で挑戦するにあたり、特定の企業に縛られず、多様なプロジェクトに柔軟に関わりたいという思いが強くなり、フリーランスの道を選びました。もちろん、収入の不安定さなどへの不安はありました。しかし、これまでの事業経験で培った自己管理能力や営業力、そして何よりAI分野への強い興味と探求心が、不安を乗り越える原動力となりました。
現在のAI関連の仕事
現在は、クライアント様の様々なニーズに応じて、生成AIを活用したサービスを提供しています。例えば、企業のブログ記事やSNS投稿用の文章を、ターゲット層に合わせて複数パターン生成したり、Webサイトや広告に使用する画像を、コンセプトに合わせてオリジナリティ高く作成したりしています。また、大量のテキストデータから要点を抽出・要約するリサーチ業務の効率化や、企業のブランドイメージに合ったロゴデザインの提案なども行っています。クライアント様の課題を丁寧にヒアリングし、AIの特性を活かして、時間短縮、コスト削減、あるいは新しいアイデア創出といった価値を提供できるよう努めています。
不登校を経験している子どもたちへのメッセージ
今、学校に行けなくて苦しんでいる君へ。まず伝えたいのは、「あなたは何も悪くない」ということです。学校が合わないこと、周りに合わせられないことは、決して君のせいではありません。今は辛くて、将来が不安で、真っ暗闇の中にいるように感じるかもしれません。でも、どうか自分を責めないでください。休むことは、逃げることではなく、自分を守るための大切な時間です。焦らなくて大丈夫。自分のペースで、好きなことや興味のあることを見つけてみてください。道は一つではありません。必ず、君が輝ける場所や道が見つかるはずです。
不登校のお子さんを持つ親御さんへ
お子さんが学校に行けなくなり、親御さんご自身も大変お辛く、不安な日々をお過ごしのこととお察しいたします。私の経験からお伝えしたいのは、どうか焦らず、お子さんの気持ちに寄り添っていただきたいということです。「学校に行くのが当たり前」という考えを一旦横に置いて、お子さんが今何を感じ、何を求めているのか、じっくり耳を傾けてあげてください。そして、「あなたの味方だよ」というメッセージを伝え続けてほしいのです。親御さんの理解と安心感が、お子さんにとっては何よりの支えになります。また、親御さん自身も抱え込まず、相談機関などを頼り、ご自身の心と体を大切にしてください。