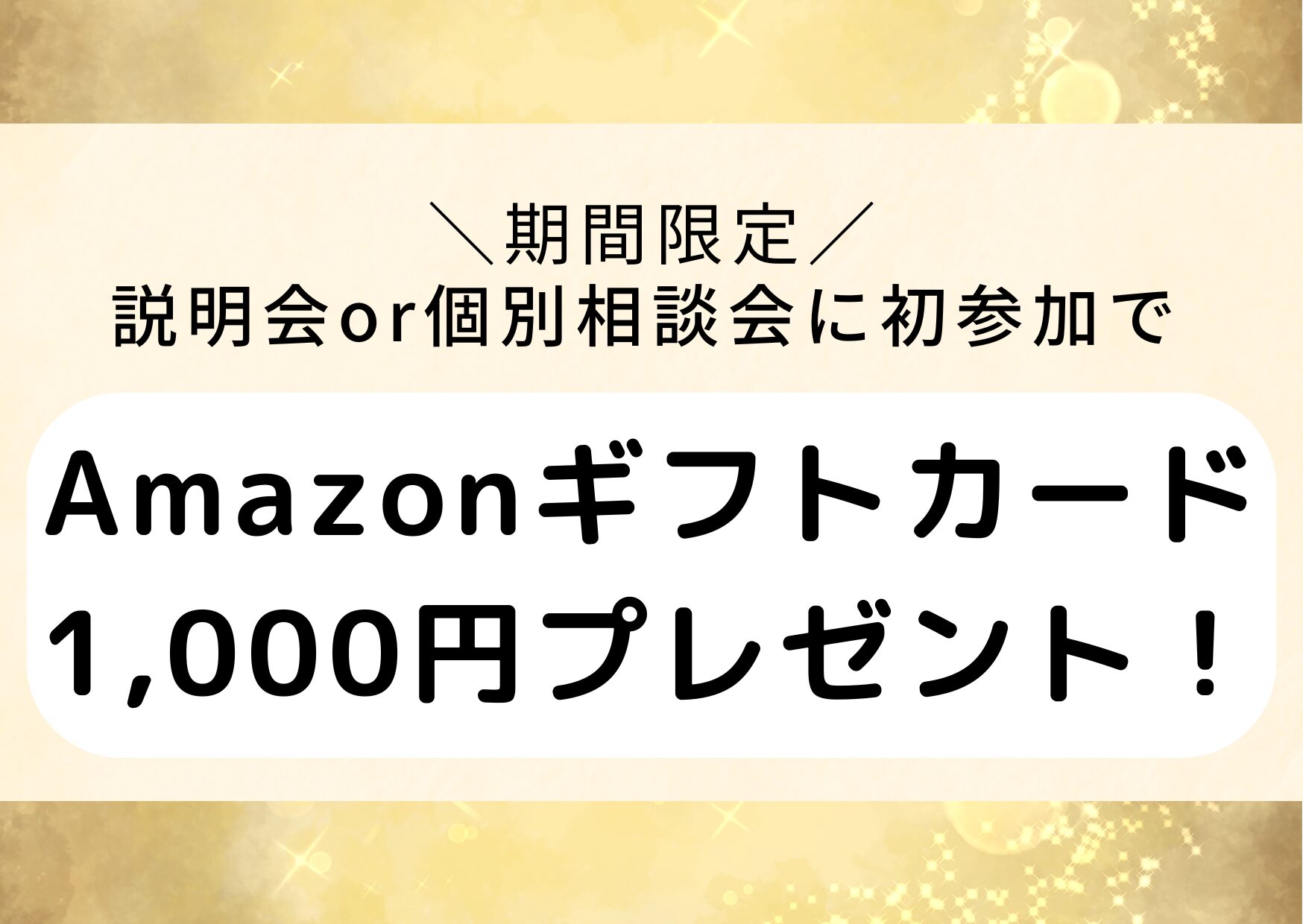不登校体験から学ぶ:通信制高校卒業後のキャリア形成と私のその後
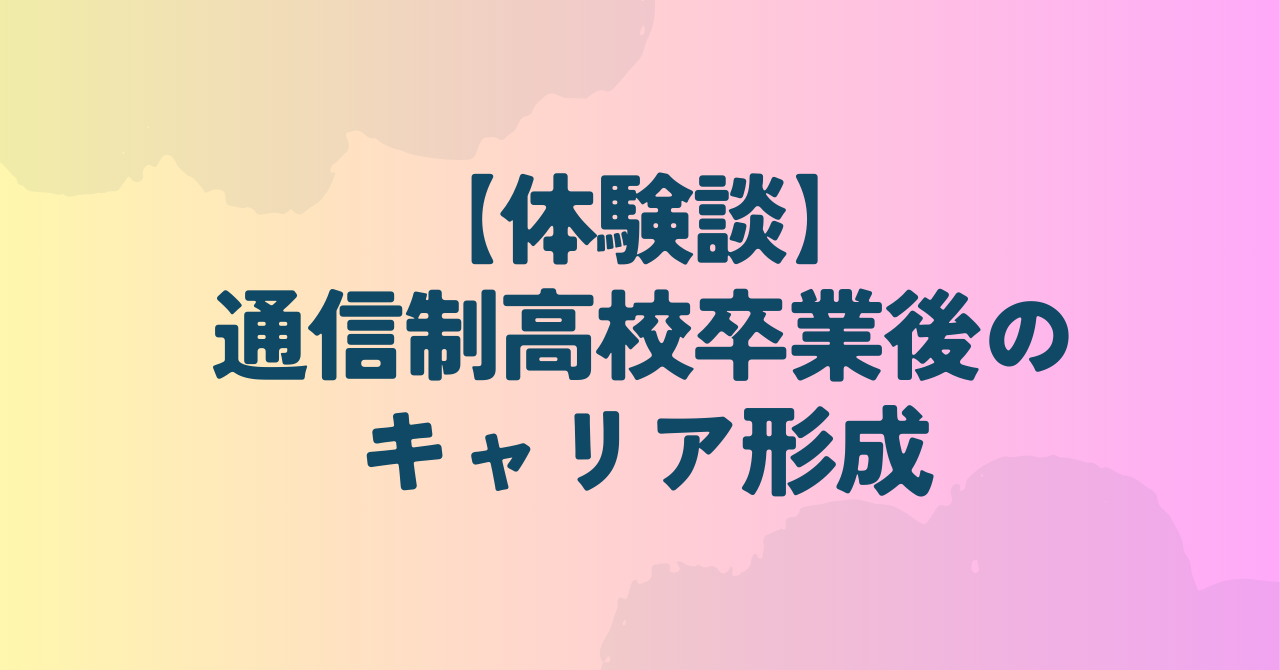
はじめに:優等生から不登校への道のり
私は東京都の公立小学校時代、誰もが認める「優等生」でした。運動会ではリレーの選手に選ばれるほど足が速く、勉強面でもクラスでトップの成績を維持していました。特に算数と国語が得意で、テストで100点を取ると先生が黒板に私の回答用紙を貼り出すこともあり、周囲からの評価も高いポジションにいました。
しかし、小学校6年生の時に両親の判断で私立中学への進学が決まり、環境が一変することになりました。私立中学に入学してから、これまでとは比較にならないほどの学習量と競争の激しさに直面し、今までのように簡単にトップになることは難しくなりました。周囲の生徒たちは小学校時代から塾に通っていた子が多く、私は徐々に授業についていけなくなり始めたのです。

不登校のきっかけ:学業不振と精神的プレッシャー
不登校になったのは中学2年生の1学期末試験後でした。それまで何とか中の上程度の成績を維持していたものの、このテストで特に数学と英語の成績が急落してしまいました。教室では成績順に席が決められることもあり、私は後方の席に移動することになりました。
さらに追い打ちをかけるように、数学の教師から「公立から来た生徒は遅れを取りやすい」と全体に向けて言われ、自分が指されているような気がして強い恥辱感を覚えました。期末テスト後の夏休みは、次の学期への不安で押しつぶされそうな日々でした。2学期の始業式の朝、制服を着ようとしたところで突然吐き気と動悸に襲われ、その日は保健室で過ごしました。翌日からも同じ症状が続き、学校に行けなくなったのです。
学校環境との不適合:「学ぶ喜び」の喪失体験
私立中学に入ってから常に感じていたのは、「自分はここに場違いなのではないか」という違和感でした。小学校では自信を持って発言できていたのに、中学では間違いを恐れるあまり授業中の挙手も減っていきました。
特に苦痛だったのは、学校全体に漂う「学歴エリート」としてのプライドと競争原理です。先生方も「この学校から有名大学に何人合格した」という話をよくし、勉強ができることが人間的価値の基準であるかのような空気がありました。小学校時代に感じていた「学ぶ楽しさ」よりも、「結果を出すこと」への圧力が強く、勉強が単なる手段と化していくことに深い違和感を感じていました。
不登校初期の心理状態:自己否定と罪悪感の日々
学校に行けなくなった当初は、強い自己嫌悪と焦りに襲われました。「なぜ自分だけが行けないのか」「このままでは将来が台無しになる」といった考えが頭から離れませんでした。朝になると体が震え、頭痛や吐き気が襲ってきて、物理的に動けなくなる状態でした。
同時に、不思議な解放感も感じていました。毎日感じていた緊張やプレッシャーから一時的に逃れられたという安堵感です。しかし、その安堵感自体にも罪悪感が伴い、「自分は逃げているだけだ」という自己否定的な思いと常に闘っていました。
周囲の理解不足:「怠け」と誤解される苦しみ
学校からの反応は冷たいものでした。クラス担任からは「精神的に弱い」「もっと頑張れば克服できる」と電話で言われたこともあります。クラスメイトからは当初は「どうしたの?」と連絡がありましたが、時間が経つにつれて連絡は途絶えていきました。
一部の教師は家庭訪問をしてくれましたが、その際も「早く学校に戻らないと遅れをとる」という言葉が多く、私の状態を理解しようとする姿勢よりも、学校のシステムに早く戻すことを優先しているように感じました。
家族の対応:理解と葛藤のはざまで
両親、特に父は「良い大学に入れば良い人生が待っている」という考えが強く、教育熱心でした。私の成績が良かったことから私立中学を勧めたのも父でした。不登校になった当初、父は「根性が足りない」「気合いで乗り越えるべきだ」という考えを持っており、学校に行くよう厳しく言うこともありました。
母は比較的柔軟で、私の状態を心配してくれましたが、それでも「学校に行かないと将来困る」という不安から、頻繁に学校に行くよう促していました。両親ともに不登校についての知識や理解が乏しく、私の状態を「怠け」や「わがまま」と捉える発言もありました。
助けになったのは、母が徐々に私の状態を理解しようと努力してくれたことです。教育相談センターに自分から足を運んで情報を集め、不登校に関する本も読んでくれました。そして、ある時「無理に学校に行かなくてもいい。あなたのペースでいいんだよ」と言ってくれたことが大きな救いとなりました。
一方で改善してほしかったのは、父の理解不足でした。不登校から半年経っても「根性の問題」と考え続け、時に厳しい言葉で私を責めることがありました。また、両親が親戚や知人に対して私の状況を隠そうとする様子を見て「自分は恥ずかしい存在なのだ」と感じることが多々ありました。両親自身が不登校に対する社会的偏見から自由になり、私の味方になってほしかったです。
不登校期間中の日常生活:孤独との向き合い方
不登校になった最初の1〜2ヶ月は完全に引きこもり状態でした。夜更かしをして昼過ぎまで寝ていることが多く、起きても自室から出ることはほとんどありませんでした。テレビを見たり、小学校時代から集めていた本を読んだりして過ごしていました。
3ヶ月目ぐらいから、母の勧めで教育相談センターのカウンセリングに週1回通い始めました。カウンセラーのアドバイスもあり、少しずつ生活リズムを整え始め、朝起きる時間と寝る時間を決め、日中は簡単な家事を手伝ったり、興味のある分野の本を読んだりする習慣がつきました。
学習への取り組み:自分のペースでの勉強再開
最初の2〜3ヶ月は勉強する気力がまったくなく、学校から送られてくるプリントも手をつけられない状態でした。しかし、カウンセラーから「今は勉強以前に心を休ませることが大切」と言われ、無理に勉強しなければという思いから少し解放されました。
半年ほど経った頃から、小学校時代から得意だった国語と社会を中心に、自分のペースで学習を再開しました。特に歴史や文学に興味があったので、教科書よりも関連書籍を読むことが多かったです。数学と英語は依然として手をつけられない状態が続き、その部分での遅れへの不安は常にありました。
社会的つながりの再構築:適応指導教室での出会い
不登校になって最も変化したのが友人関係です。中学校の友人とはほとんど連絡が途絶え、社会的な孤立感を強く感じるようになりました。唯一の救いは小学校時代からの友人が数人いて、たまに連絡をくれたことでした。
社会とのつながりとしては、教育相談センターでのカウンセリングと、半年ほど経った頃から週に一度通い始めた適応指導教室(不登校の子どものための教室)が大きな支えになりました。適応指導教室では同じような境遇の子どもたちと出会い、「自分だけではない」という安心感を得ることができました。
最も辛かった時期:文化祭と修学旅行の季節を乗り越えて
最も辛かったのは不登校になって4ヶ月目ぐらいの時期でした。学校の文化祭や修学旅行の時期と重なり、参加できないことで強い疎外感を感じました。また、この頃には学習の遅れが相当なものになっていることを実感し、「このままでは取り返しがつかない」という不安が最高潮に達しました。
この時期を乗り越えられたのは、適応指導教室での出会いが大きかったです。そこでは「学校に行くことだけが正解ではない」「自分に合った学び方を見つけることが大切」という新しい価値観に触れることができました。また、カウンセラーから「不登校は心身からのSOSのサイン」という言葉をもらい、自分を責める気持ちが少し和らぎました。
転機となった出会い:通信制高校という新たな選択肢
大きな転機となったのは適応指導教室での出会いでした。特に印象的だったのは、そこで知り合った年上の生徒が通信制高校に進学し、自分のペースながらも充実した高校生活を送っているという話を聞いたことです。「学校に行けないこと=人生の終わり」ではないと知り、大きな希望を感じました。
また、教育相談センターのカウンセラーが紹介してくれた元不登校経験者の大学生とのメンター制度も大きな助けになりました。その大学生は中学時代に私と同じような経験をしながらも、現在は教育学を学んでいました。「あなたの感じ方は間違っていない」「辛い時期も自分を形作る大切な経験になる」という言葉をかけてもらい、自己肯定感が少しずつ回復していきました。
不登校からの回復:自己理解と多様な価値観の獲得
不登校を乗り越えられた最大の理由は、「学校以外の選択肢があること」を知り、「自分に合った形で学ぶことができる」という希望を持てたことだと思います。それまでは学校に行けないことを完全な失敗と捉えていましたが、通信制高校や定時制高校など、様々な学びの形があることを知って視野が広がりました。
また、カウンセリングを通じて自分自身を深く見つめることができたことも大きいです。なぜ私立中学の環境に馴染めなかったのか、どのような学び方が自分に合っているのかを理解できるようになりました。「みんなと同じでなくてもいい」という考え方を受け入れられるようになったことが、次のステップへの大きな力となりました。
通信制高校での学び:自分のペースで成長できる環境
中学3年生の後半からは、適応指導教室に加えて、週に1回ほど学校の保健室登校を始めました。完全に教室に戻ることはできませんでしたが、進路についての情報を得る必要があったからです。担任の先生や進路指導の先生との面談を経て、通信制高校への進学を決めました。
通信制高校を選んだ理由は、自分のペースで学べることと、人間関係のプレッシャーが比較的少ないことでした。通信制高校では週に2〜3日のスクーリング(登校)があり、残りは自宅学習という形態が私に合っていました。また、多様なバックグラウンドを持つ生徒が集まっており、「正解は一つではない」という価値観を実感できる環境でした。
通信制高校での人間関係:多様性を受け入れる環境
通信制高校では、普通高校とは異なる人間関係の形がありました。年齢も背景も様々な生徒が集まっており、不登校経験者だけでなく、プロのスポーツや芸能活動をしている人、社会人経験のある人なども多くいました。
この多様性が、私にとって大きな安心感をもたらしました。「みんな同じ」を求められる環境ではなく、一人ひとりが自分の事情や目標を持ち、それを互いに尊重し合う雰囲気があったのです。また、教師も生徒の多様性を理解しており、個々の状況に合わせた接し方をしてくれました。
通信制高校の学習システム:自立心を育む教育
通信制高校のカリキュラムは、主にレポート学習とスクーリング(面接指導)、テストで構成されていました。レポートは各教科ごとに提出期限が設けられていましたが、その期限内であれば自分のペースで取り組むことができました。
この学習スタイルは、自分で計画を立て実行する自己管理能力を鍛えるのに非常に役立ちました。最初は締め切り直前に慌ててレポートをまとめることもありましたが、徐々に計画的に取り組めるようになりました。また、わからないところは教師に質問しやすい環境も整っており、必要な時に必要なサポートを受けられる体制が整っていました。
不登校経験から得た強み:多様性への理解と希望の持ち方
不登校経験から得た最大の強みは「多様な価値観を認められるようになった」ことです。一般的な「成功」の定義や「正しい」生き方にとらわれず、それぞれの個性や状況に合った選択があることを理解できるようになりました。
また、苦しい時期を乗り越えた経験から、困難に直面しても「この先にも道はある」という希望を持ち続ける力が身につきました。今では何か壁にぶつかっても、「今はつらくても必ず解決策はある」と信じられるようになりました。そして、同じような悩みを持つ人に対する理解と共感の深さも、この経験から得られた大切な財産だと感じています。
専門学校進学とIT分野への興味:新たな可能性の発見
通信制高校卒業後は、専門学校に進学しました。IT関連の分野を選んだのは、不登校時代に一人で過ごす時間が多い中でパソコンに親しみ、プログラミングや情報整理に興味を持ったことがきっかけでした。
不登校経験は進路選択に大きく影響しました。以前は「一流大学に行くこと」が唯一の選択肢だと思っていましたが、自分に合った形での進学や就職を考えるようになりました。また、自分の興味や適性を大切にするという姿勢が、IT分野という選択につながりました。
DX推進の仕事へのキャリアパス:不登校経験が導いた職業選択
専門学校卒業後、小さなIT企業でのサポート業務からキャリアをスタートしました。クライアント企業の業務効率化の手伝いをする中で、「無駄な作業や非効率なプロセスを改善することで、人の負担を減らせる」ということにやりがいを感じるようになりました。
不登校時代に感じていた「既存のシステムに合わない人もいる」という思いが、「より多くの人が働きやすい環境を作りたい」という思いにつながり、業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の仕事に携わるようになりました。現在は中小企業のDX推進をサポートする仕事に就いています。
現在の仕事と不登校経験の関連性:多様性を尊重する視点
現在は、企業が抱える非効率な業務プロセスを分析し、デジタル化による改善提案や導入支援を行っています。特に、アナログな作業が多い中小企業に対して、現場の声を丁寧に聞きながら負担を減らせるシステム導入を支援することにやりがいを感じています。
不登校経験は「多様な価値観や働き方を認める」という姿勢として仕事に活かされています。一人ひとりの事情や考え方を尊重しながら、それぞれに合った改善提案ができることが強みになっていると感じます。また、自分自身が辛かった経験から、「無理をさせない」「心理的安全性を確保する」ことを常に意識しています。
業務効率化専門家としての視点:一人ひとりに合った解決策
業務効率化やDX推進の仕事をする上で特に大切にしているのは、「テクノロジーは手段であって目的ではない」という視点です。単に最新技術を導入することが目的ではなく、それぞれの企業や個人が抱える課題に対して、最適な解決策を提案することが重要だと考えています。
この考え方は、不登校時代に「一つの正解」や「みんなと同じであること」に疑問を持ち、「自分に合った方法」を模索した経験から生まれたものです。システム導入においても、企業それぞれの文化や従業員の特性に合わせたカスタマイズを大切にしています。「正解は一つではない」という不登校時代に得た気づきが、今の仕事の根幹になっています。
デジタルと人間のバランス:テクノロジーの本質的役割
DX推進の現場では、しばしば「デジタル化によって仕事が奪われる」という不安の声を耳にします。しかし私は、テクノロジーは人間の創造性や感性を発揮するための時間を作り出すものであり、人間の価値を高めるものだと考えています。
この考え方も、不登校時代の経験に根ざしています。当時、「学校に行くこと」という形式だけが重視され、一人ひとりの学び方や成長のプロセスが軽視されていることに違和感を覚えました。現在のDX推進においても、「デジタル化すること」自体が目的化するのではなく、それによって人間がより創造的で有意義な時間を持てるようになることを目指しています。
不登校の子どもたちへのメッセージ:自分のペースを大切に
現在不登校で悩んでいる子どもたちには、「学校に行けないことは失敗ではない」ということを伝えたいです。一時的に学校から離れることで、自分を見つめ直し、本当に大切なことや自分らしい生き方を考える貴重な時間になる可能性もあります。焦らず、自分のペースを大切にしてください。
また、「今の辛さは永遠には続かない」ということも心に留めておいてほしいと思います。私も当時は「このままずっと苦しい」と感じていましたが、時間の経過とともに状況は変わり、新たな可能性が開けてきました。今は見えなくても、必ず光は差し込んでくるものです。
親御さんへのアドバイス:無条件の愛情と多様な選択肢
親御さんには、お子さんの状態を「問題」として捉えるのではなく、「心身からのサイン」として受け止めていただきたいと思います。学校に行くことだけが成功ではなく、お子さんが自分らしく生きていける道を一緒に探していただければと思います。そして何より、「あなたがいてくれるだけで十分」という無条件の愛情を伝え続けることが、お子さんの自己肯定感を育み、次のステップへの原動力になると信じています。
また、学校以外の選択肢についても積極的に情報収集してください。通信制高校、定時制高校、フリースクール、ホームエデュケーションなど、多様な学びの形があります。「普通の学校に行くこと」だけが正解ではなく、お子さんに合った学び方を見つけることが重要です。
まとめ:不登校体験が導いた私のキャリアとその後の人生
不登校の経験は確かに辛いものでしたが、その経験を通して得た気づきや強みが、現在の私のキャリアや人生観を形作っています。「みんなと同じでなくてもいい」「自分に合った方法で進んでいい」という気づきは、業務効率化という仕事にも直結しています。
苦しい時期を乗り越えてきたからこそ、今の仕事でも「人それぞれに合った方法」を提案できる視点を持てています。不登校という経験が、思いもよらない形で私の強みになり、今のキャリアにつながっているのです。
通信制高校での学びが私に与えたのは、単なる知識ではなく、自分自身への信頼と多様な選択肢を認める柔軟な思考でした。これらは社会人になってからも大きな財産となっています。
不登校の経験は決して無駄ではなく、むしろかけがえのない財産になりうるものです。今悩んでいる方々にも、今は見えなくても、自分らしい道が必ず開けることを伝えたいと思います。通信制高校はその選択肢の一つであり、私にとっては新たな一歩を踏み出す大切な場所となりました。