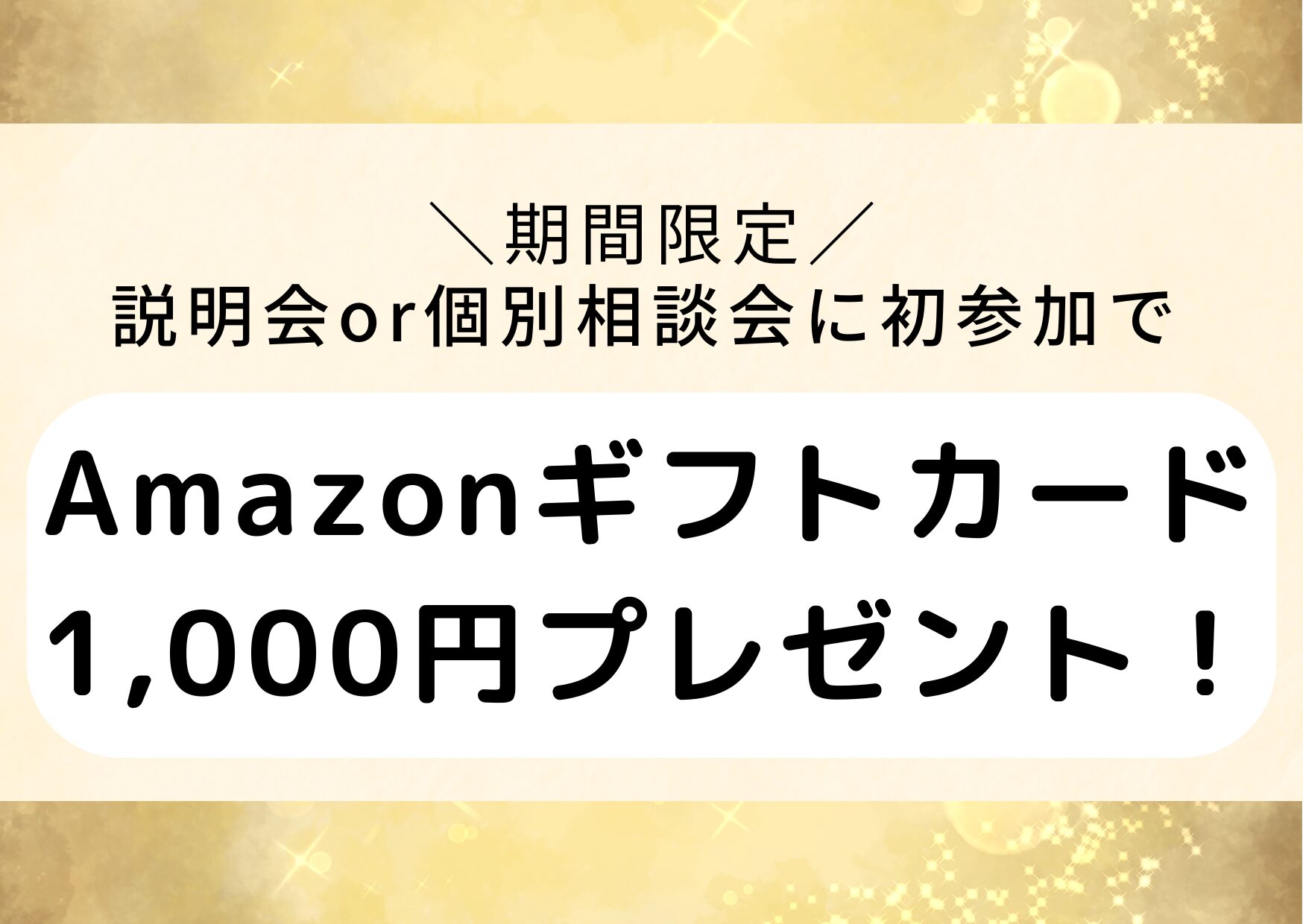人間不信から自分らしさの発見へ 〜不登校経験から学んだ大切なこと〜
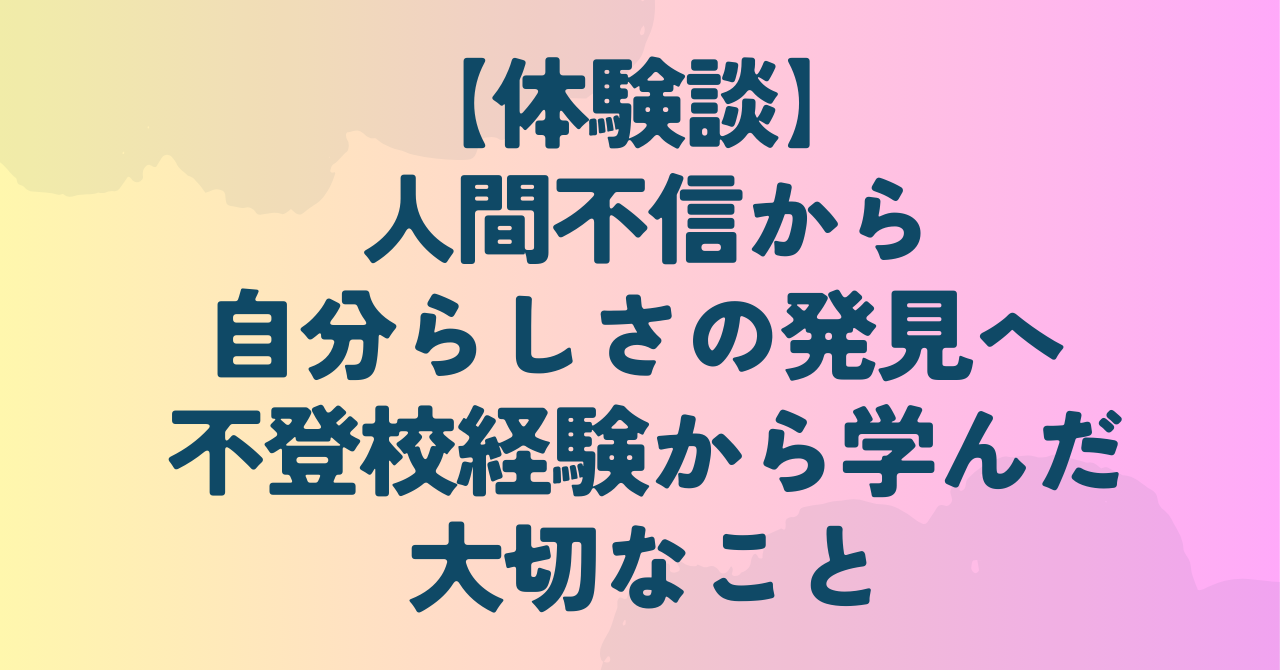
自己紹介と現在の学校生活
Yと申します。現在はデザイン系の高校に通っており、気の合うクラスメイトと共に都内でデザインに関する授業を受けています。不登校を経験した過去がありますが、今は自分の好きなことを学べる環境で充実した日々を過ごしています。
コロナ禍での孤立と心の葛藤
中学生になるタイミングでコロナ禍に入り、私の学校生活は想像していたものとは大きく異なるものになりました。「中学デビュー」して友達をたくさん作りたいという願いとは裏腹に、人間関係がうまく築けず、次第に孤立していきました。
正直とても悔しかったです。中学生になると共にデビューして友達を沢山作れたらいいなと思っていましたが、全然上手くいかず一人だけになってしまい自分のことをネガティブに考え始めてしまって、自分は本当に生きてていいのかなと人生について色々考えてしまいました。
自分の存在価値を見失うほどの孤独感は、思春期特有の繊細さと相まって、私の心を深く傷つけていきました。
人との関わりの中で感じた辛さ
中学校での人間関係の難しさを最も痛感したのは、グループワークの場面でした。
個人的にグループワークの時が一番辛かったです。グループワークはもう既に仲良くなって固まっているチーム内で会話したりしてしまっていたり、自分の案は聞かれなかったり遠ざけられたりしてしまったりしていたので、先生と話す時もあったのですが、先生と話すとなっても先生からも遠ざけられてたりしてしまっていて、その瞬間が一番人との距離の差や孤独感を感じで辛かったです。
所属する場所がないという感覚は、学校という閉ざされた環境の中で一層強まりました。クラスメイトだけでなく、教師からも理解を得られなかったことが、さらなる孤立感を生み出していったのです。
深まる人間不信と世界の見方の変化
次第に、周囲の人々への不信感が強まっていきました。
全員自分のことが嫌いなんだなと思っていました。小学校の時の関係も嘘だったのかなとか思ったりしてしまって、仲良かった人達とも話せなくなったり初対面の人は目も合わせることも出来なくなって、一時的にパニックになって周りが見えなくなってしまうことがありました。あの時は全てが怖くて恐ろしいと思っていました。
かつての良好な人間関係さえも疑わしく感じ、世界全体が敵意に満ちた場所のように思えてしまいました。この時期の私の世界観は暗く、信頼できるものは何もないように感じていました。
不登校を選択するまでの葛藤
限界を感じながらも、すぐには休む決断ができませんでした。
クラスメイトから「逃げた」と言われるのが怖くて、最初は登校しないことに強い罪悪感がありました。でも、体も心も限界だったので、少しずつ「休む勇気」も必要だと自分に言い聞かせていきました。
「学校に行くのが当たり前」という社会的プレッシャーの中で、休む選択をすることは想像以上に勇気が必要でした。自分を責め続けながらも、心身の健康を守るための決断だったと今は理解しています。
両親のサポートと心に残った言葉
不登校になった当初、両親の対応はさまざまな変化がありました。
不登校になったばかりの頃は、学校へ行きなさい!と強制的に学校に行かせる形でした。しかし、休む頻度が増えると段々自分の心の状態を第一に考えてくれるようになって、自分の好きなことを家でやる形を取らせてくれるようになりました。勉強、人間関係など色々と他の子達と追いついていない自分に、「焦らないでいいよ」と言ってくれた母の一言にはとても救われていました。
時間の経過とともに両親の理解が深まり、特に母からの「焦らないでいいよ」という言葉は、常に追いつかなければならないというプレッシャーから解放してくれる大切な支えになりました。
周囲の大人たちの対応で傷ついたこと
一方で、表面的な励ましの言葉には傷つくこともありました。
表面的な励ましや、「そんなの気にするな」などの言葉です。気持ちが追いついていないときにそれを言われると、理解されていないと感じてしまって悲しかったです。
本人の気持ちに寄り添わない言葉かけは、時に傷を深めることがあります。心の準備ができていない段階での「気にするな」という言葉は、悩みを軽視されたように感じてしまうのです。
不登校期間中の学びと成長
学校に行かない時間を、自分の好きなことに集中する時間に変えていきました。
不登校の間は自由に自分の好きなことをとことんやっていました。自分は絵を描くのが好きなので、デジタルイラストを描いたり水彩画をやったりと、その日その日の気分で精神的な負担が減るように絵を描いていました。オンラインはないですが、中学校で習うものは家で色々な動画を見て解き方とか考え方を学ぶようにしていました。
絵を描くという自己表現を通して心の安定を図りながら、学習面では自分のペースで動画などを活用して勉強を続けていました。この時期に身につけた自己管理能力は、後の学校生活でも大きな力となりました。
前向きになれた転機と出会い
高校に入学してから、人間関係への不信感が徐々に癒されていきました。
高校に入学したての頃、初めて自分に話しかけてくれた人がいました。その人は今ではもうクラスのムードメーカーみたいな子ですが、入学当初にクラスメイト全員に対等に話しかけていた印象があります。その人がクラスを和ませてくれたことで、日を経つにつれて一人一人の個性を尊重してくれるクラスメイトが増えていきました。クラスメイトの皆が、一人一人の個性を活かして学校で仕事や役割を与えてくれたり、話しかけてくれるので段々話すことが楽しく思えました。
一人のクラスメイトの存在が変化のきっかけとなり、「個性を尊重する」という新しい価値観に触れることで、少しずつ人との関わりに前向きになれました。各自の強みを認め合う環境は、私の心の安全地帯となっていきました。
高校選びの経緯と考慮したポイント
進学にあたっては、様々な選択肢を比較検討しました。
全日制や定時制、通信制など様々な学校を見ましたが、やはり学校を実際に見学して判断しました。見学前・後には既に全日制か定時制に行きたいと思っていて、入学して雰囲気が無理だったら通信制にしようと決めていました。久々に登校するので、それぞれ自分の体調や起床時間にあっているかあっていないか、毎日行くことは出来るか吟味して全日制を選びました。4年間も定時で学んだりするのは大変だと思ったので、3年間で沢山学ぼうと思って全日制を選びました。
実際に見学をして雰囲気を体感し、自分の体調や生活リズムと照らし合わせて全日制を選択しました。バックアッププランも考えながら、段階的に復学のステップを踏んでいった慎重さが功を奏したといえます。
人間関係の克服を決意したきっかけ
人間不信を乗り越えようと決意したのは、家族の支えがあったからこそでした。
自分の家の環境は、正直金銭面的にお金が足りず厳しいのが現実です。それでもデザインを学ぶのが好きで将来美術系の大学に通いたいと駄々を捏ねた結果、両親が必死に働いて学費を貯めてくれてたのがきっかけでした。両親は現実を見て、私のために全力で働いて将来頑張って欲しいと思ってくれていたことが嬉しかったです。それに、両親が頑張っているのに、自分が頑張っていない状態がとても嫌で憎く感じたので人間不信を克服しようと決心しました。
経済的に厳しい状況の中で、私の夢を応援してくれる両親の姿に心を動かされ、自分も頑張らなければという思いが生まれました。誰かのために変わろうとする力は、時に自分のためだけでは生まれない強さを引き出してくれます。
デザイン系の高校を選んだ理由
高校選びで最も重視したのは「将来やりたいこと」と「学校の雰囲気」でした。
高校は「自分が将来やりたいこと」を優先的に見ていましたが、それと同時に重視したのは「学校内の雰囲気」です。自分がしたいことが見つかっても、また同じように人間関係で失敗して閉ざされてしまうのではないかと感じてしまっていたので、自分らしくいられそうな場所かどうかを判断していました。
専門的な学びと心理的安全性を両立できる環境を求めた結果、デザイン系の高校を選択しました。自分の興味を追求できる場所であることと、個性を尊重する文化があることが決め手となりました。
中学時代の自分に伝えたいこと
今の視点から当時の自分にアドバイスするなら、焦らずに人間関係を築くことの大切さを伝えたいと思います。
無理に頑張って関わりを増やそうと必死になりすぎるのは良くないと言いたいです。 無理に関わろうとして、逆に嫌がられてしまうということを学びました。きっかけをつくらずに焦って友人を増やそうとするのは良くないと思いました。あの時に戻るなら、焦らず落ち着いて、相手について少しずつ理解してから勇気を出して話しかけたいです。
人間関係は数ではなく質が大切だという気づきは、苦い経験から得た貴重な教訓でした。焦りから生まれる行動は時に逆効果になることを、身をもって学びました。
人間関係の再構築で学んだこと
人間関係を再構築する過程で、重要な気づきがありました。
「相手を変えようとするより、自分の受け止め方を整えること」です。無理に関わろうとしない、でも閉ざしすぎない。そのバランスを見つけることが大事だと感じました。
相手や状況を変えようとするのではなく、自分の心の持ち方を変えることの大切さに気づきました。適度な距離感を保ちながら関係を育むことの重要性は、今でも私の人間関係の指針となっています。
価値観の変化と自分らしさの発見
この経験を通して、私の価値観は大きく変化しました。
「普通であること」への執着がなくなりました。自分らしさを引き出すことを第一としている学校に行ったことで、クラスメイト一人一人に対する価値観を互いに大切にする雰囲気があったため、むしろ「自分のままでいる強さ」が本当の意味で大切だと思えるようになりました。
「普通」や「みんなと同じ」という価値観から解放され、むしろ自分らしくあることの大切さに気づきました。多様性を尊重する環境に身を置くことで、自分自身を肯定できるようになったのです。
心を守りながら前進するための習慣
精神的な健康を保ちながら成長するために、いくつかの習慣を身につけました。
小さな目標を立てること、完璧を求めすぎないこと、そして自分を否定しないこと。 時間はかかりますが、実際に自分も高校で自分を理解してくれる人と出会えました。 自分自身を表現することは忘れないで欲しいです。そして、辛い時は自分の好きなことをとことんやる、この習慣で心がだいぶ安定しました。
小さな成功体験を積み重ねること、自己否定を避けること、そして自己表現を大切にすることが、私の心の支えとなりました。特に「辛い時は自分の好きなことをとことんやる」という習慣は、精神的な安定をもたらす重要な要素でした。
不登校や人間関係に悩む方へのメッセージ
同じような悩みを抱える人たちに、自分のタイミングを大切にしてほしいと思います。
人生において自分のタイミングや精神面で、ここから変えよう!と思う瞬間がいつか来ると思います。その時は学校や将来行きたい場所についてじっくり調べてみてください。学校だって、私も受験生になりたての頃、全日制だけだと思っていましたが、定時制などもあって驚いていました。全日制か定時制、はたまた別のところか、どちらに入ったとしても遠回りに見えても、それが自分に合っているなら、それが正解です。
自分に合った選択をすることの大切さと、遠回りに見える道も実は自分にとっての最適な道かもしれないという視点は、不登校経験から得た貴重な知恵です。
周囲の大人に望むサポート
親や教師など周囲の大人に望むサポートについて、こう伝えたいと思います。
まずは「評価」より「自分の周りの状況に対する理解」をしてほしいです。親は学校で普段自分がどんな生活をしているかをずっと見ている訳ではありません。ずっと見ていないからこそ、普段の学校の様子はどうか、定期的に気にかけたりして欲しいと思いました。
子どもの学校生活の実態を理解することが、適切なサポートの第一歩です。表面的な評価ではなく、日常の様子に関心を持ち、定期的に対話する姿勢が子どもの心の支えになると感じています。
経験から生まれた意外な強み
辛い経験から思いがけない強みも生まれました。
自分が相手の相談事を聞いたりしたりカウンセラー代わりになれるようになったと思います。定期的に色々なクラスメイトの悩みを聞いたり、一緒に行動したりと誰かの心に支えになれて嬉しく思います。
自分が悩んだ経験があるからこそ、人の心の痛みがわかるようになりました。その共感力と傾聴力は、今では友人たちの相談相手として活かされています。苦しい経験がむしろ人を思いやる力になったことは、予期せぬ贈り物でした。
将来の夢と理想の学び方
最後に、これからの夢と理想について紹介します。
「誰かの心に寄り添えるような表現」を届ける仕事がしたいです。自分では伝えられないことや苦しいことを表現して多くの人に伝わらなかったとしても、誰か一人の脳に印象に残る作品をつくりたいです。私の作品がある一人の人生に影響を与え、何かやりたいことを見つけるキッカケになれたらいいなと思います。学校の形にとらわれず、学びたいことを自由に深められる環境を作るのが理想です。
誰かの心に寄り添う表現者になりたいという夢は、自分自身の苦しみと向き合ってきた経験から生まれたものです。一人でも良いから、誰かの人生に良い影響を与えられる作品を作りたいという思いは、かつての孤独な自分を救いたいという願いでもあるのかもしれません。
また、学校という枠組みにとらわれない、自由な学びの環境を理想としているのは、様々な学び方があることを身をもって経験したからこそでしょう。
まとめ:苦しみから生まれた希望の物語
不登校と人間不信という深い闇を経験しながらも、そこから自分らしさを発見し、新たな道を切り拓いてきたYさんの物語は、同じように悩む多くの人たちに希望を与えてくれます。
「普通であること」への執着から解放され、「自分のままでいる強さ」を見出すまでの道のりは決して平坦ではありませんでしたが、その過程で得た気づきや成長は、かけがえのない財産となっています。
苦しい時期があったからこそ芽生えた「誰かの心に寄り添える表現者になりたい」という夢は、自身の経験を社会に還元する形で花開こうとしています。
誰にでも自分のタイミングがあり、一見遠回りに見える道も、実は自分にとっての最適な道かもしれない——そんなメッセージが、この体験談には込められています。