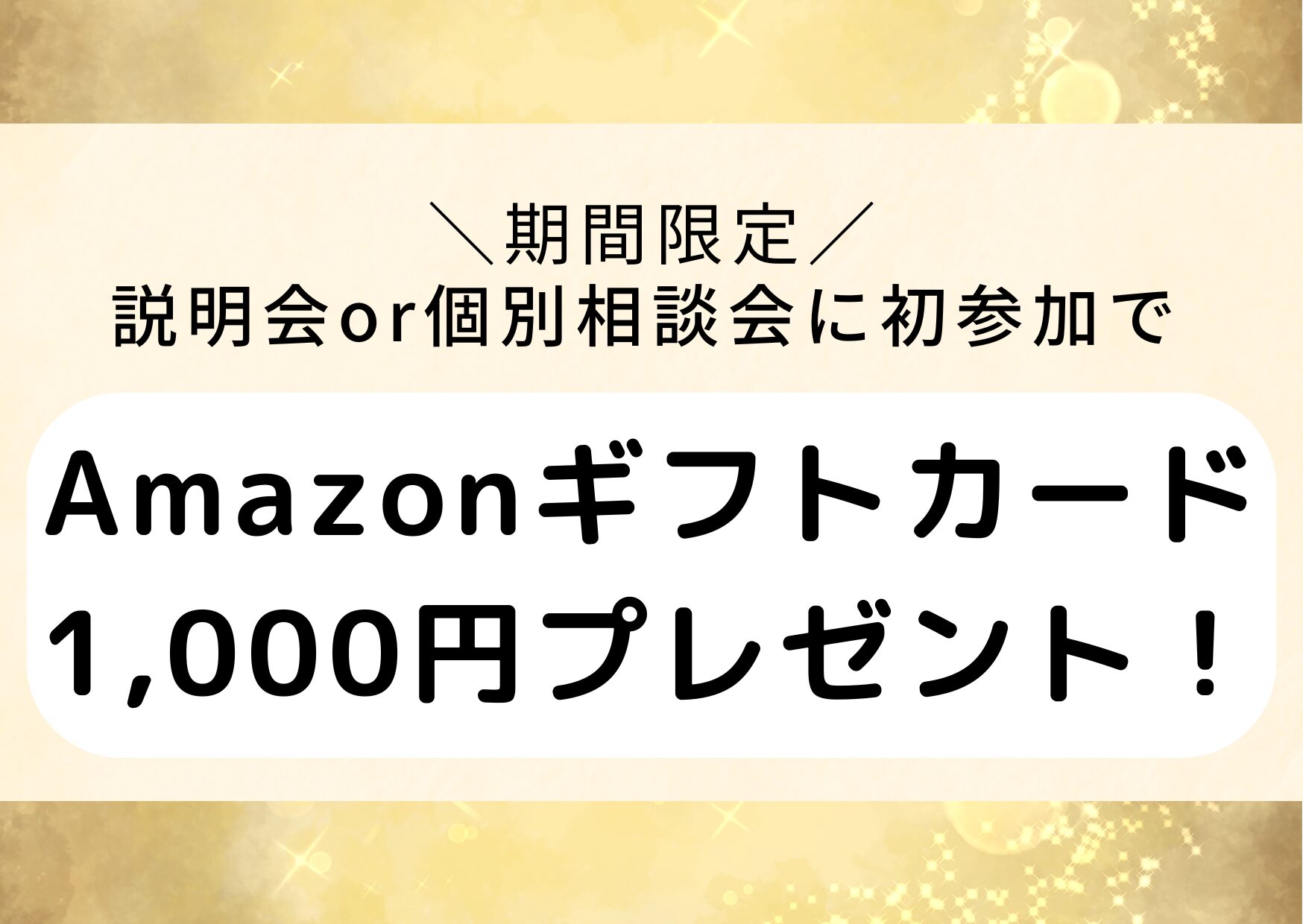不登校経験者インタビュー 〜通信制高校で見つけた新たな道〜
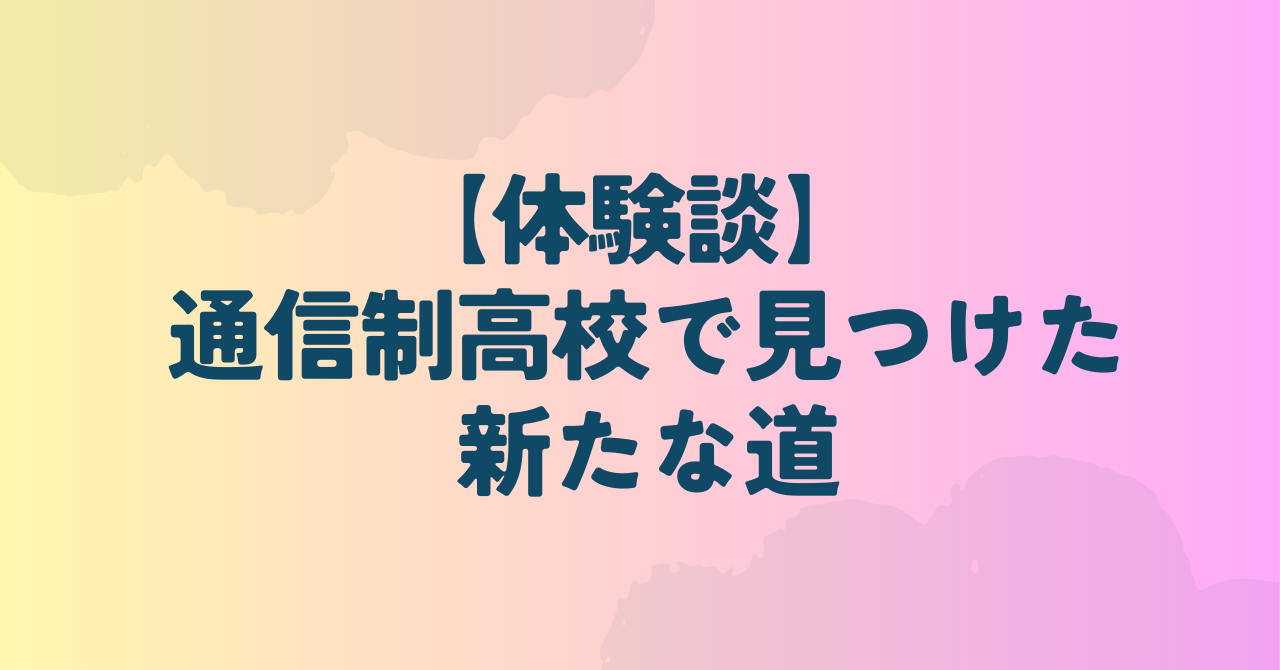
不登校になるまでの学校生活
小学校時代は、転校経験はあったものの、どちらの学校でも楽しく通っていました。特に2校目ではクラスの中心的存在として、休み時間には友達と遊び、充実した人間関係を築いていました。
勉強面では、自ら親に頼んで学習塾に通うほど勉強好きな子どもでした。全教科得意で、授業が簡単に感じられるほどだったため、授業中に友達と話してしまい、先生に怒られることもよくありました。
不登校のきっかけと当時の心身の状態
最初は「単に体がだるくて1日学校を休んだ」と記憶しています。しかし、翌日になっても「学校に行くのが怖い」という気持ちが強くなり、そのまま登校できなくなりました。
当時はコロナ禍で中学入学後の学校生活が変則的だったこと、クラスの半数は別の小学校から来た生徒だったことなど、環境の変化が大きなストレスになりました。また、自宅が学区の端にあり、急な坂道を20分ほど歩かなければならない通学路も負担になっていました。
心理的なストレスが先にあり、それが身体症状として現れたのではないかと振り返っています。
家族の理解と対応
母親は「学校に行きなさい」と言うことは一度もなく、体調を心配してくれました。毎日「今日もしんどい、今日も学校に行けない」と伝える日々が続き、やがて「学校に行ける日に担任に連絡する」というルールに落ち着きました。
姉と兄は特に干渉せず無関心でしたが、当時の私にとっては「何もかもが嫌だった」ため、それがかえって心地よかったです。
学校や先生からの対応
1年生の時の担任は若く意欲的な先生で、月に1度は家庭訪問をしてくれました。「その時はそれさえも苦痛」と感じていましたが、先生の熱意は伝わっていました。
2年生、3年生の担任は少し距離を置いて関わってくれました。時折電話をかけてきたり、学校に行った時には優しく話しかけてくれたりしました。特に、卒業式にも参加できなかった私に、わざわざ家まで卒業証書を届けてくれた際の言葉は、今でも前向きな気持ちにさせてくれる大切な言葉になっています。
起立性調節障害の診断
不登校になって3ヶ月ほど経った頃、元々通院していた小児科医に症状を相談したところ、起立性調節障害と診断されました。自分の状態に「名前がついた」ことで、「免罪符を得たようなほっとした気持ち」になりました。
この診断をきっかけに、月に1回、1時間ほどのカウンセリングを受けるようになりました。母親は積極的にカウンセラーに質問や相談をしていましたが、私はなかなか心を開くことができませんでした。それでも、最後のカウンセリング後に一人で泣いた経験から、この時間が自分の世界で重要な役割を果たしていたと気づきました。
母親からのサポート
母子家庭で育った私にとって、母親の存在は大きな支えでした。通信制高校のパンフレットを取り寄せてくれたり、常に体調を気にかけてくれたりと、母親は子ども以上に真剣に子どものことを考え、寄り添ってくれました。
振り返ると、「母がどれだけ私のことを思っているか気づくのに時間がかかった」と思います。今では母親にしてもらったことに感謝の気持ちを伝えるよう心がけています。「今の私が元気に高校に通えているのは母のサポートのおかげ」だと思います。
兄姉との関係
私は末っ子で、姉とは11歳、兄とは9歳の年齢差があります。二人との関係は良好で、不登校のことにはあまり触れず、一緒にゲームをして過ごすことが多かったです。甘やかされていたと感じる一方で、自分の悩みや辛さは打ち明けられず、泣いている姿も見せませんでした。
今振り返ると「もう少し周りの人を信じて相談に乗ってもらった方が良かった」と感じています。
家族対応の良かった点と改善点
良かった点は「今まで通りの接し方」をしてくれたことです。家族も戸惑いながらも、元気だった頃と同じように接してくれたため、家に自分の居場所を感じることができました。
一方で、当時は母親と姉の仲が悪く、二人の喧嘩を見聞きすることが苦痛でした。私が愚痴を聞かされる役になることも多く、直接関係のない立場でありながら心を傷つけられることがありました。
外出できるようになるまでの過程
完全に引きこもっていたわけではなく、元々ぜん息治療で月に1回は小児科に通院していました。この通院だけは不登校になっても続けており、「ここに行くのをやめたら人じゃなくなる」という気持ちから、社会とのつながりを保つ「最後の砦」と考えていました。
この小児科の先生からカウンセリングを紹介され、それが世界を広げるきっかけになりました。「何か1つでも他者とのかかわりを持つことの大切さ」を実感しました。
外出への恐怖を和らげる方法
毎晩「明日は学校に行こう」と思いながらも、朝になると玄関から出られなかったといいます。現在でも高校に行く際に気分が悪くなることがあり、「制服を着る」「リュックに教科書を入れる」といった学校に関連する行動がプレッシャーになっています。
そのため、現在の高校には私服で通い、時にはトートバッグにペンケースだけを入れて登校することもあるそうです。外出の恐怖を克服する上で最も大切なのは「外に出られなくても自分を責めないこと」だと強調します。中学生の頃は一日休むたびに自己嫌悪に陥り、それが引きこもりを加速させていたと振り返ります。
登山や一人旅ができるようになった要因
外出に対する抵抗が減り、積極的な活動ができるようになった要因として「外に出られなくても自分を責めないようにしたこと」を挙げています。心に余裕ができたことで、徐々に自分から外出できるようになったそうです。
「私は自分から外に出られるようになるまで3年かかった」と述べ、焦らずゆっくり休むことを勧めています。
通信制高校を選んだ理由
通信制高校を選んだ主な理由は以下の点です:
- 体調面での不安から週5日の登校に自信がなかった
- 不登校後、教室の雰囲気が苦手になっていた
- 制服が必須ではない(教室と制服という「縛り」から解放されたかった)
- 登校回数を自由に決められる点が魅力的だった
- 進路指導が充実していた
高校卒業後の進路を学校と一緒に考えられる「進路指導の充実度」も重視したポイントだったそうです。
通信制高校への通学と工夫
週2回、1時間かけて電車通学することは最初は苦痛だったといいます。しかし、始業時間が10時と遅いこと、好きな時間に登下校できるという柔軟なルールのおかげで、徐々に通学へのプレッシャーが軽減していきました。
また、当初は定期券を購入する予定でしたが、「学校に行かなければならない」という義務感につながることを恐れ、ICカードで乗車する方法を選んだそうです。この選択も登校へのハードルを下げる効果があったと振り返っています。
通信制高校の学習スタイルの利点
通信制高校の学習スタイルで特に合っていると感じる点は:
- 登校回数を自由に決められる
- 登下校の時間が自由
- 主要教科の授業も受講は任意
- 自分のペースで紙の課題を進められる
「モチベーションが高い時期に一気に課題を進め、やる気が出ない時は好きなことをする」という選択ができる点が、本人に合っていたようです。
通信制高校での学びと人間関係
通っている高校には、中学校で馴染めなかったり、体調を崩して登校が難しかったりと、何らかの事情を抱えている生徒が多いそうです。お互いの境遇を理解するのに時間がかからず、多くの友人ができました。
学校が定期的に生徒同士の交流イベントを開催してくれるため、性別や学年を超えた友情を育むことができたといいます。多様な人との関わりを通じて「人の生き方は様々」ということに気づくことができたと語っています。
体調管理の工夫
高校生になってから「よく食べてよく歩く」習慣が身につき、体調が劇的に改善したそうです。特にポケモンGOに夢中になったことが、外出の原動力になりました。
体調が悪い時でも完全に運動をやめてしまうと症状が悪化することを経験したため、家の中でも足踏みをするなど、無理のない範囲で運動を続けることを心がけているといいます。「運動は習慣にした方がいい」と強調しています。
通信制大学への進学希望
まだ体調面での不安が残るため、自由にカリキュラムを組めて自宅で学習できる通信制大学への進学を考えているそうです。通信制大学で幅広い分野を学び、特に興味を持った分野が見つかり、体調も改善すれば4年制大学への編入も視野に入れているとのこと。
中学生の頃は将来が全く見えず漠然とした不安を抱えていましたが、現在はある程度進路が定まり、不安も大きく軽減されたと語っています。
不登校経験から得た成長
2年半の不登校期間を経て「見えている世界が広がった」と感じています。自分と他人の違いを理解して自分を受け入れられるようになり、他者も受け入れられるようになったといいます。
不登校という「心を休める期間」があったからこそ精神的に成長でき、無理に登校していれば逆に追い詰められていたと考えています。家に籠っていた2年半は「決して無駄ではなく、人生において必要な期間だった」と前向きに捉えています。
不登校で悩む人たちへのメッセージ
現在不登校で悩んでいる子どもたちへ:
学校に行けない期間が続くと自分を責めてしまいがちだと思いますが、どうか自分を責めずにゆっくり休んでほしいです。心と体の調子が良くなるのを待ってから学校に行ってもいいですし、学校以外の居場所を見つけるのもいいと思います。今、自分がいる世界でできることを見つけて頑張ってほしいです。
保護者の方へ:
進路のことや学校以外の居場所づくりなど、多くのアンテナを張って得た情報をお子さんに伝えるといった方法でお子さんをサポートするのがいいと思います。心が弱っていると今の自分以外のことを考える余裕がないと思うので、そういったサポートはお子さんの心に寄り添うのと同じくらい大切です。