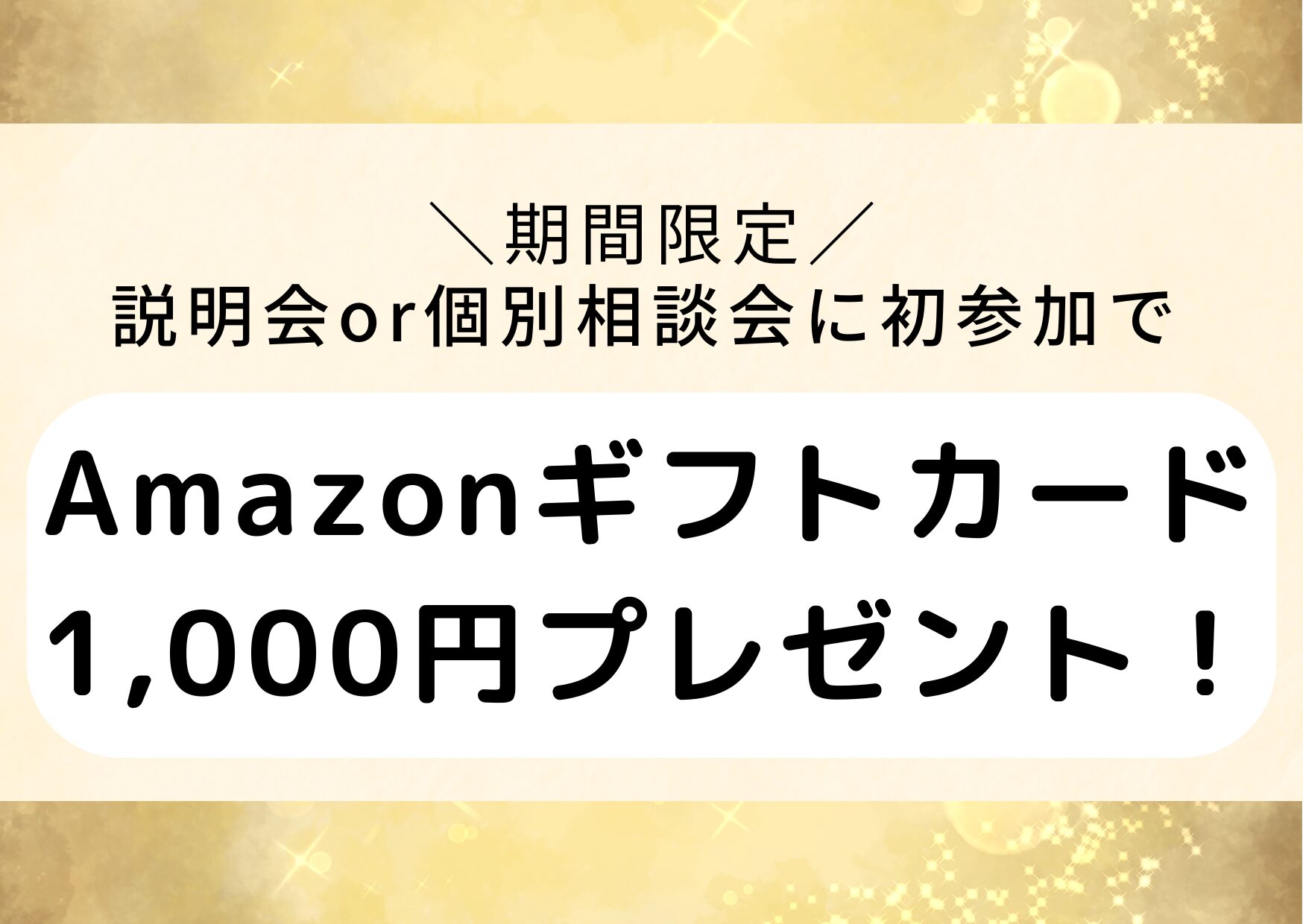【後悔しない】不登校期間中にやるべき勉強法と通信制高校での学び直し
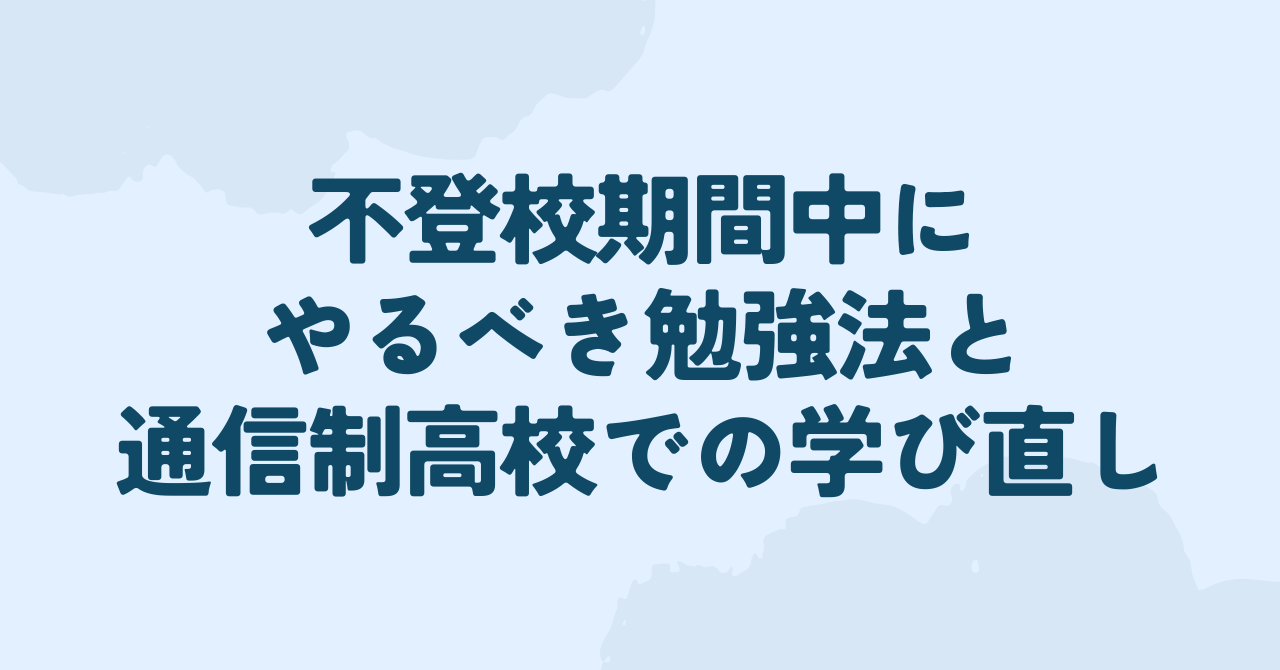
「不登校になってから勉強をしておけばよかった」「学校に戻ったとき、授業についていけなくて苦労した」
不登校を経験した多くの生徒が、このような後悔の声を口にします。学校に通えない期間があっても、勉強を続けることは将来の可能性を広げるために非常に重要です。この記事では、実際に不登校を経験し、その後通信制高校で学び直したCさんの体験談をもとに、不登校期間中の効果的な勉強法と通信制高校での新たな学びの形をご紹介します。

目次
- 不登校経験者が語る「勉強しておけばよかった」後悔
- 不登校期間中にやるべき具体的な勉強法
- 勉強のモチベーションを保つコツ
- 通信制高校での学び直しの実際
- 通信制高校と普通高校の勉強の違い
- 埼玉県越谷市の通信制サポート校での学習サポート
- 不登校経験者からのアドバイス
- まとめ:不登校期間を将来につなげる学びの時間に
不登校経験者が語る「勉強しておけばよかった」後悔
不登校を経験したCさんは、不登校期間中の過ごし方についてこう振り返ります。
「不登校の期間にしてなくて後悔したこと、1つ目は勉強です。復帰してからついていけなくなって本当に大変です。勉強だけはしておけばよかったと後悔しました。また、やりたいことに挑戦しておけばよかったと思っています。時間はあったはずなのでその時間を『いつまでも悩んでいる時間』ではなく『未来の自分のために使う時間』にした方が良かったと思っています。」
Cさんは家での過ごし方についても言及しています。
「家で考えていたら違っていたと思うこと、それは趣味等の好きなことや勉強の事です。趣味はあまり思いつめないようにするために大切だと思います。また、不登校中にほとんど勉強しなかった私は本当に苦労しているので、学校に行かなくても勉強できる方法を考えておきましょう。」
文部科学省の調査によれば、不登校から学校復帰した生徒の約70%が「学習の遅れ」を最も不安に感じる要素として挙げています。また、不登校期間中に何らかの学習を継続していた生徒は、そうでない生徒と比較して復帰後の学校適応度が高いことも明らかになっています。
これらの事実からも、不登校期間中の学習継続は、将来の選択肢を広げるためだけでなく、精神的な安定にも寄与する重要な要素だと言えるでしょう。
不登校期間中にやるべき具体的な勉強法
では、不登校期間中にどのような方法で勉強を続ければよいのでしょうか。Cさんの経験や教育専門家の知見を基に、具体的な勉強法をご紹介します。
1. 自分のペースで学べる学習方法
不登校の状態にある生徒にとって、自分のペースで取り組める学習方法は大きな助けとなります。
「学校は行かなくてもいいと思いますが勉強はした方が良いです。不登校になると基本的に家での生活になるため『勉強もしなくていいか』となりがちですがあとあと大変になります。」
Cさんが語るように、不登校中も勉強を続けることが重要です。以下のような方法が効果的です:
- オンライン学習サービスの活用:自分のペースで進められるオンライン教材
- 学習アプリの利用:ゲーム感覚で学べるアプリは継続しやすい
- 通信教育の教材:定期的に送られてくる教材で学習習慣を維持
- 図書館の活用:自分の興味に合わせた本を読むことも立派な学習
国立教育政策研究所の研究によれば、不登校生徒にとって「強制されない」「自分のペースで進められる」学習環境が最も効果的であることが示されています。これらの学習方法は、まさにその条件に合致しています。
2. 外部サポートを利用した学習
一人での学習に限界を感じる場合は、外部のサポートを利用することも有効です。
「独学では分からないという人は塾に行ったり家庭教師をお願いするのが良いかもしれません。」
Cさんのアドバイスにあるように、以下のような選択肢を検討してみましょう:
- フリースクールの活用:不登校生徒向けの学習支援を行う場所
- 家庭教師の依頼:マンツーマンで自分のペースに合わせた指導を受けられる
- オンライン個別指導:自宅にいながら専門家の指導を受けられる
- 教育支援センター(適応指導教室)の利用:公的な支援機関での学習
日本財団の調査によれば、何らかの外部サポートを利用して学習を継続した不登校生徒は、高校卒業率が約25%高いという結果が出ています。自分一人で抱え込まず、適切なサポートを受けることも重要な選択肢です。
3. ICTを活用した学習環境の構築
近年のテクノロジーの発展により、不登校生徒の学習環境は大きく改善されています。
- オンデマンド授業の視聴:学校の授業を録画したものを自宅で視聴
- 学習管理アプリの活用:進捗管理や苦手分野の把握に役立つ
- デジタル教科書の利用:紙の教科書よりも検索や学習記録が容易
- オンライン質問サービス:分からない問題をその場で質問できる
文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」の一環として、多くの学校ではICTを活用した不登校生徒への学習支援が進んでいます。担任の先生や学校のICT担当者に相談してみると、意外な支援が受けられるかもしれません。
勉強のモチベーションを保つコツ
不登校期間中に最も難しいのは、勉強のモチベーションを保ち続けることかもしれません。Cさんの経験から、効果的なモチベーション維持の方法を考えてみましょう。
1. 小さな目標設定と成功体験の積み重ね
「過去に戻れるとしたらもっと有意義に生活したいです。当時の自分はだらだらしながら『どうしたら学校にいけるか』考えていたり、『学校に行きたくない』という感情と戦っているだけでした。そのおかげで今は学校に行けているといえばそうなのかもしれませんが、もっと有意義な時間の使い方ができたのではないかと思っています。例えば、勉強したりいろいろなことに挑戦したりして不登校なら不登校なりに新たなことに挑戦するのもありだったと今では思います。」
教育心理学の研究によれば、大きな目標よりも小さな目標を設定し、達成感を積み重ねていくことがモチベーション維持に効果的だとされています。例えば:
- 一日30分の学習時間を確保する
- 教科書1ページを読み終える
- 問題集5問を解く
このような小さな目標を達成することで、自己効力感(自分にはできるという感覚)が高まり、学習意欲の維持につながります。
2. 自分の興味関心に結びつけた学習
不登校期間中は、学校のカリキュラムに縛られない自由な学びが可能です。自分の興味関心と学習を結びつけることで、モチベーションを高めることができます。
- 好きな小説を読んで国語の力をつける
- 興味のあるテーマについて調べ学習を行う
- 将来の夢や目標に関連する科目から始める
認知科学の研究によれば、内発的動機(自分の興味や好奇心に基づく動機)は、外発的動機(報酬や罰に基づく動機)よりも持続しやすく、学習効果も高いことが示されています。
3. 自分の学習スタイルの理解と活用
一人ひとり得意な学習スタイルは異なります。自分に合った学習方法を見つけることも、モチベーション維持の鍵です。
- 視覚型学習者:図や表、映像を使った学習
- 聴覚型学習者:音声教材や読み上げ、議論を通じた学習
- 運動感覚型学習者:実際に書いたり動いたりしながらの学習
学習心理学では、自分の認知スタイルに合った学習方法を採用することで、学習効率が20〜30%向上するという研究結果も出ています。自分がどのタイプなのか意識しながら学習方法を選ぶと良いでしょう。
通信制高校での学び直しの実際
不登校を経験した後、多くの生徒が選択するのが通信制高校です。Cさんも通信制高校の特徴について言及しています。
「人間関係があまりないので苦労しない(精神的に疲れない)ところや家から出なくてもいいので周りの目を気にしなくて良いというところです。」
通信制高校での学びには、以下のような特徴があります:
1. 自分のペースで学べるカリキュラム
通信制高校の最大の特徴は、自分のペースで学習を進められることです。レポート提出やスクーリング(面接指導)の日程も、ある程度自分で選択できる場合が多いです。
- 体調の良い時に集中して学習できる
- 苦手科目にじっくり時間をかけられる
- 得意科目を先に進めることも可能
文部科学省の調査によれば、通信制高校を選んだ不登校経験者の約65%が「自分のペースで学べること」を最大のメリットとして挙げています。
2. 多様な学習方法
通信制高校では、従来の教科書やレポートだけでなく、多様な学習方法が提供されています。
- オンライン授業:自宅からリアルタイムで参加できる授業
- VOD(ビデオ・オン・デマンド)授業:録画された授業をいつでも視聴可能
- チャット質問:オンラインでリアルタイムに質問できるシステム
- プロジェクト学習:自分の興味あるテーマについて探究的に学ぶ
ICT教育研究団体の調査によれば、多様な学習方法を提供している通信制高校ほど、生徒の学習満足度と卒業率が高い傾向にあるとされています。
3. 個別サポート体制
通信制高校では、一人ひとりの状況に応じた個別サポートが充実しています。
- 担任教員によるサポート:定期的な面談や学習指導
- 学習アドバイザー:学習計画の立案や進捗管理をサポート
- スクールカウンセラー:心理的な悩みの相談
- キャリアカウンセラー:進路選択のアドバイス
全国高等学校通信制教育研究会の報告によれば、個別サポートが充実している通信制高校ほど、中途退学率が低く、大学進学率や就職率が高い傾向にあることが示されています。
通信制高校と普通高校の勉強の違い
通信制高校と普通高校では、学習の進め方に大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った学習スタイルを選ぶことが重要です。
1. 学習の進め方の違い
普通高校では、クラス全体が同じペースで授業を進めていきますが、通信制高校では基本的に自分のペースで学習を進めます。
- 普通高校:教師主導の一斉授業、決められた時間割
- 通信制高校:自己主導の学習、自分で決める学習計画
教育社会学の研究によれば、自己調整学習の能力(自分で計画を立て、実行し、評価する能力)は、通信制高校での学習を通じて向上することが示されています。この能力は、大学進学後や社会人になってからも役立つ重要なスキルです。
2. 学習評価の違い
学習の評価方法も、通信制高校と普通高校では異なります。
- 普通高校:定期試験、小テスト、授業態度など総合的に評価
- 通信制高校:レポート評価、スクーリング評価、単位認定試験
高等教育研究機関の調査によれば、通信制高校の評価方法は「何を知っているか」だけでなく「何ができるようになったか」を測る傾向が強く、実社会で求められる能力の育成につながりやすいとされています。
3. 学習リソースの活用
学習リソースの活用方法も大きく異なります。
- 普通高校:教科書、授業ノート中心の学習
- 通信制高校:多様な学習リソース(オンライン教材、動画教材、参考書など)の活用
デジタル教育研究会の調査によれば、通信制高校の生徒は多様な情報源から必要な情報を選択し、活用する「情報リテラシー」が高まる傾向にあることが分かっています。これも将来役立つ重要なスキルの一つです。
埼玉県越谷市の通信制サポート校での学習サポート
埼玉県越谷市には、通信制高校と連携し、より手厚いサポートを提供する「通信制サポート校」新開高等学院があります。サポート校では、不登校を経験した生徒が安心して学べる環境が整っています。
1. 越谷市の通信制サポート校の特徴
埼玉県越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)には、以下のような特徴があります:
- 少人数制のクラス:一人ひとりに目が行き届く少人数制
- 個別カリキュラム:生徒の状況や目標に合わせたオーダーメイドの学習計画
- 柔軟な登校日程:週1〜5日など、自分の状況に合わせて選べる登校日数
- 多様な学習スタイル:対面授業、オンライン授業、自宅学習の組み合わせ
- 総合的なサポート:学習面だけでなく、メンタル面や進路面も含めた総合サポート
全国サポート校協会の調査によれば、通信制サポート校を利用した生徒の約85%が「学習意欲が向上した」と回答しており、高い満足度が示されています。
2. 学習面でのサポート
越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)では、以下のような学習サポートが提供されています:
- 個別指導:一人ひとりの理解度や学習スタイルに合わせた指導
- 教科別サポート:苦手科目の克服に特化したサポート
- レポート作成サポート:通信制高校のレポート作成をサポート
- 試験対策:単位認定試験や大学入試に向けた対策
- 学習計画の作成:効率的に単位を取得するための学習計画立案
教育評価研究会の報告によれば、こうした個別最適化された学習サポートは、特に不登校経験者の学習意欲と学力向上に効果的であることが示されています。
3. 生活面・メンタル面でのサポート
学習面だけでなく、生活面やメンタル面でのサポートも充実しています:
- カウンセリング:定期的な個別カウンセリング
- ソーシャルスキルトレーニング:対人関係の構築や維持のスキルを学ぶ
- 生活リズムの構築支援:規則正しい生活習慣の確立をサポート
- 居場所づくり:安心して過ごせる環境の提供
- 興味関心に基づく活動:部活動や特別活動の提供
臨床心理学の研究によれば、こうした総合的なサポートが、不登校経験者の自己肯定感の向上と社会的適応に大きく寄与することが明らかになっています。
不登校経験者からのアドバイス
最後に、実際に不登校を経験し、その後通信制高校で学んだCさんからのアドバイスをご紹介します。
「時間はあったはずなのでその時間を『いつまでも悩んでいる時間』ではなく『未来の自分のために使う時間』にした方が良かったと思っています。」
Cさんの言葉からも分かるように、不登校期間を単なる「空白期間」ではなく、自分の将来のための準備期間として捉えることが大切です。以下に、Cさんの体験から導き出されるアドバイスをまとめてみました:
1. 勉強は続けること
「勉強だけはしておけばよかったと後悔しました。」
Cさんが最も強調しているのは、勉強を続けることの重要性です。たとえ学校に行けなくても、自分のペースで少しずつでも学習を続けることが、将来の選択肢を広げることにつながります。
2. 興味あることに挑戦する
「やりたいことに挑戦しておけばよかったと思っています。」
不登校期間中は、学校のカリキュラムに縛られない自由な時間があります。この時間を活用して、自分の興味あることに挑戦してみることも大切です。それが将来の進路選択につながることもあります。
3. 自分のペースを大切にする
「不登校から復活する人もいれば復活できない人もいます。また、復活までにかかる時間も人それぞれだと思います。しかし、焦らずに自分のペースで慣れていけばいいと思います。それが長続きするコツなのかもしれません。」
無理に学校復帰を目指すのではなく、自分のペースを大切にすることがCさんのアドバイスです。通信制高校やサポート校など、自分に合った学びの場を見つけることも一つの選択肢です。
4. サポートを求めることも大切
「独学では分からないという人は塾に行ったり家庭教師をお願いするのが良いかもしれません。」
一人で抱え込まず、必要に応じて外部のサポートを求めることも重要です。通信制サポート校や家庭教師、オンライン学習サービスなど、様々な選択肢があります。
まとめ:不登校期間を将来につなげる学びの時間に
不登校の期間があっても、学びを続けることで将来の可能性は広がります。Cさんが語るように「勉強だけはしておけばよかった」という後悔をしないためにも、自分のペースで学習を続けることが大切です。
通信制高校やサポート校は、不登校を経験した生徒にとって新たな学びの場となります。特に埼玉県越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)では、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートが受けられます。
「時間を『未来の自分のために使う』」というCさんの言葉は、不登校を経験している全ての生徒に向けた力強いメッセージです。今は学校に行けなくても、自分なりの方法で学びを続け、将来につなげていきましょう。不登校の経験は決して無駄ではなく、自分自身を見つめ直し、新たな学び方を発見する貴重な機会になるかもしれません。