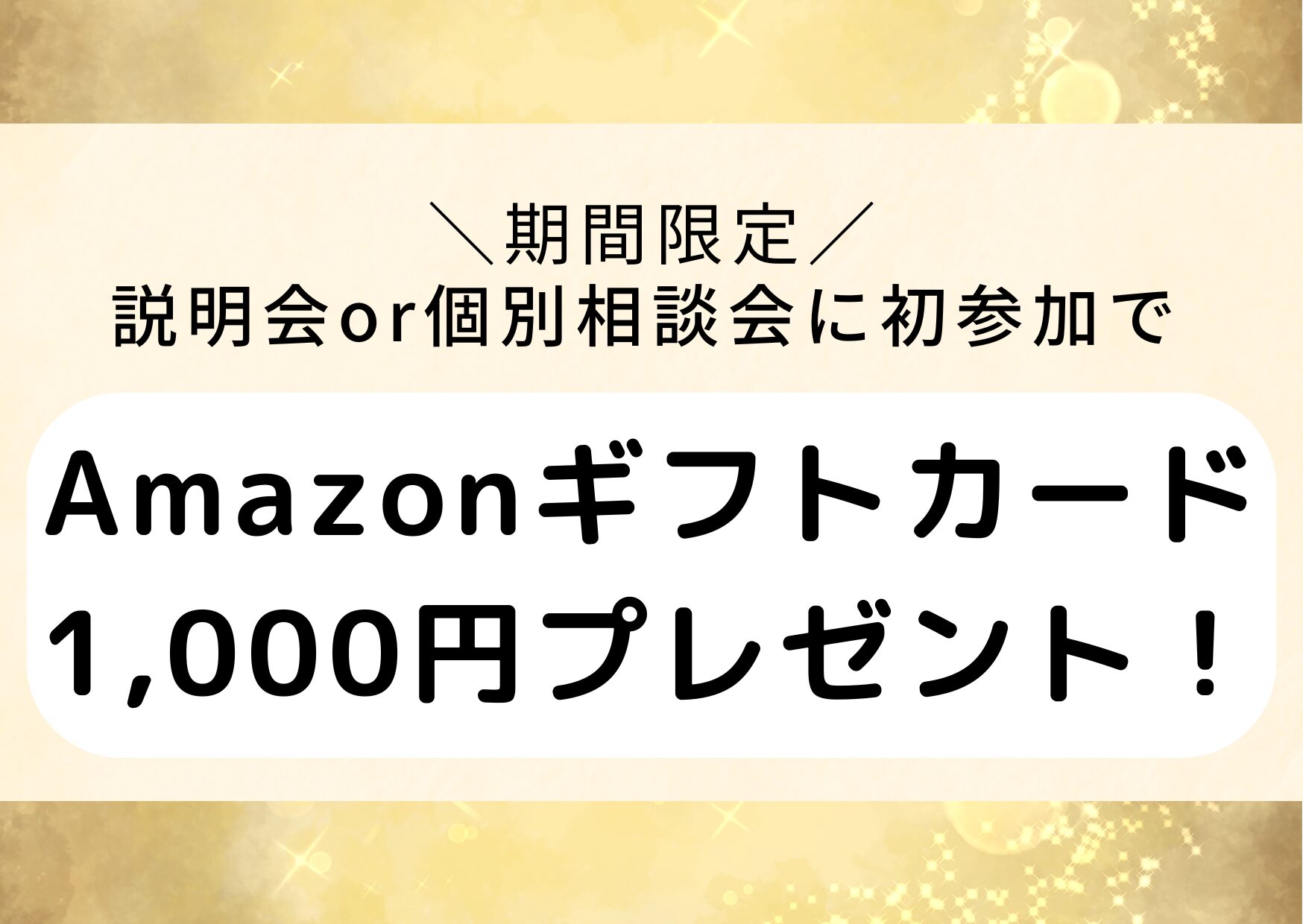【実体験】起立性調節障害が原因の不登校を乗り越えた方法とは
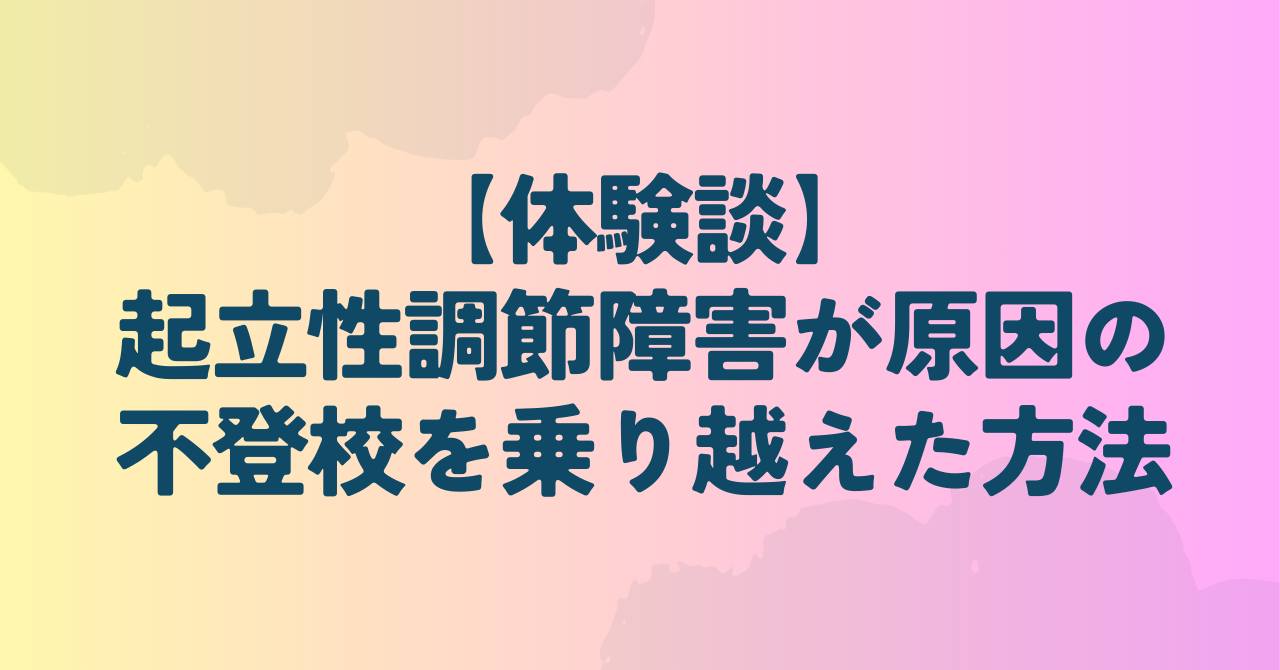
「何度アラームをセットしても朝起きられない」「学校に行きたいのに体が動かない」「『サボっている』と誤解されて辛い」
こんな症状に悩んでいませんか?実は、これらは「起立性調節障害」という思春期に多く見られる自律神経の疾患かもしれません。この記事では、実際に起立性調節障害から不登校になった経験を持つCさんの体験談をもとに、症状の特徴や学校生活への影響、そして乗り越えるための具体的な方法をご紹介します。

目次
- 起立性調節障害とは何か – 基本的な症状と特徴
- 「朝起きられない」が不登校につながるメカニズム
- 体験者が語る起立性調節障害の辛さ
- 周囲の無理解が生む二次的な精神的負担
- 体験者が実践した症状改善のための具体的な工夫
- 学校・家庭に求められる適切なサポートとは
- 起立性調節障害と上手に付き合う通信制高校という選択肢
- 埼玉県越谷市の通信制サポート校での柔軟な学習環境
- まとめ:起立性調節障害を理解し、適切なサポートで乗り越える
起立性調節障害とは何か – 基本的な症状と特徴
起立性調節障害とは、主に思春期の子どもに多く見られる自律神経の疾患です。立ち上がった時に血圧が下がりすぎてめまいや立ちくらみを起こしたり、朝に起きられなくなったりする症状が特徴的です。
Cさんは起立性調節障害について、次のように説明しています。
「起立性調節障害とは思春期くらいの子供(中高生)に多く見られる病気です。朝になかなか起きられない、食欲不振、めまいや立ちくらみが増えるなどの症状があります。特に朝起きれないという症状は学生の皆さんを苦しめていると思います。」
この疾患は、成長期の体の変化に自律神経の調整が追いつかないことで生じると言われています。日本小児心身医学会の調査によると、中高生の約10%が何らかの起立性調節障害の症状を持っているとされています。症状の程度は個人差がありますが、重症の場合は日常生活に大きな支障をきたし、不登校の原因になることもあるのです。
「朝起きられない」が不登校につながるメカニズム
起立性調節障害の最も代表的な症状である「朝起きられない」は、学校生活に大きな影響を与えます。朝の時間に始まる学校の仕組みの中で、どうしても遅刻が増えたり、1時間目の授業に出席できなくなったりすることが多くなります。
Cさんはこの状況について次のように語っています。
「朝起きれないと遅刻が多くなり、体が動かないからどうしようもないのに周りから責められて学校が嫌になってしまいます。その結果不登校の原因となる場合も少なくありません。私もそうでした。ただでも起立性調節障害の影響で思うように体が動かなくてつらい中、周りから責められたことなどの精神的ストレス等もあり不登校になりました。」
さらに具体的な学校での経験についても、次のように述べています。
「起立性調節障害みたいな症状(朝に起きれないなど)があったことからどうしても朝は遅刻して行ったりしていました。そのような生活を送っていると当たり前ですが1時間目など最初の方の授業が足りなくなってきます。先生に『このままだと留年です』とまで言われてしまいました。」
このように、体の問題から始まった症状が、学校生活の困難さを生み、さらには周囲からの無理解や叱責によって精神的な負担が加わることで、不登校へと発展していくケースが少なくないのです。
体験者が語る起立性調節障害の辛さ
起立性調節障害の症状が学校生活をどのように妨げるのか、Cさんに詳しく聞いてみました。
「一番つらかったのは学校に行きはじめたときです。高校で不登校になったので授業の出席が足りず、どうしても行かなければなりませんでした。しかし、それまではあまり学校に行っていなかったため体力的にもきつかったです。また、周りの目が気になったり自分のことを悪く言われているのではないかと思ってしまいました。そうすると学校に行きたくないという感情(不安や心配、恐怖等)になってしまい行くまでに時間がかかるようになっていました。」
特に辛かったのは、努力しても改善しない症状を周囲に理解してもらえないことだったようです。
「朝早く起きようと思って早く寝ても早く起きられないからです。早く起きる努力をしているのに家族から『夜遅くまで起きているからだ』などと言われてしまってとてもつらかったです。それでも体が思うようになりませんでした。この時が一番つらかったです。自分の存在ごと消したくなりました」
起立性調節障害の大きな困難の一つは、外見からはわかりにくい病気であるため、「怠けている」「努力が足りない」と誤解されやすいことです。本人は必死に努力していても、思うように体が動かない辛さがあります。
周囲の無理解が生む二次的な精神的負担
起立性調節障害の症状そのものに加えて、周囲の無理解からくる精神的な負担も大きいものです。Cさんは周囲からの言葉について次のように語っています。
「例えばただ単に『学校に行け』『朝早く起きれるように工夫しろ』といった感じのことを言われたときはできない自分への怒りとそれを理解せずに言ってくる相手に対する怒りがありました。しかし、同じ内容でも具体的な策(カフェインをとる、朝の血圧を上げるなど)を言われたときはありがたかったです。」
このように、単に「頑張れ」「努力しろ」といった抽象的な励ましではなく、具体的な対策を示すことが効果的です。専門家によると、起立性調節障害は本人の努力不足ではなく、自律神経の機能不全による医学的な問題であることを周囲が理解することが、子どもの精神的な負担を軽減する上で非常に重要だと言われています。
Cさんは起立性調節障害への理解について、次のように訴えています。
「起立性調節障害の人はは朝に起きられない等の理由から遅れて学校に行く場合が多いです。そのため周りの人からすればよくサボっていると思われがちな病気です。ただ、一番つらい思いをしているのは本人なので受け入れてあげることが大切です。しかし、現在の日本では起立性調節障害の人に対する理解がありません。実際にそう感じました。なので、もっと周りの人が理解して『しょうがないものだからその人にあった方法を考えよう』などと思うようにするだけで本人たちはだいぶ違うと思います。」
体験者が実践した症状改善のための具体的な工夫
起立性調節障害の症状を完全に治すことは難しいかもしれませんが、症状を軽減するための工夫はあります。Cさんが実際に試して効果があった方法について聞いてみました。
「食事面では朝ごはんにみそ汁を食べる、濃いめのお茶を飲むなど血圧を上げたり眠気を覚ませるように心がけました。あとは、気持ちを切り替えるようにしました。『学校に行かなければならない』という考え方を改めました。そこからも体力の関係等で完全に復帰するまでは時間がかかりましたが最終的には完全に復帰しました。時間が解決してくれました。」
また、別の場面でも具体的な対策について言及しています。
「一番は病院に受診して薬をもらうことだと思います。ただ、病院に受診することに抵抗がある方もいるでしょう。そういう方は朝にみそ汁など血圧が上がるものを食べる、カフェインを含んでいる飲み物を飲む(コーヒーや濃いめのお茶など)などすると良いです。(朝起きられないのは低血圧が原因の場合が多いため)ただ、これらの方法は薬と違って根本的に直すものではありません。なので、1年ほど経過しても治らない場合は受診した方がいいと思います。」
医学的には、起立性調節障害の主な治療法としては以下のようなものがあります:
- 生活習慣の改善(規則正しい睡眠、適度な運動)
- 食事の工夫(塩分の適度な摂取、水分補給)
- 薬物療法(症状が重い場合)
Cさんが実践した「みそ汁を食べる」「濃いめのお茶を飲む」といった方法は、医学的にも効果が認められている対策です。また、専門医への相談も重要な選択肢であることがわかります。
学校・家庭に求められる適切なサポートとは
起立性調節障害を抱える子どもを支えるために、学校や家庭ではどのようなサポートが求められるのでしょうか。Cさんの体験をもとに考えてみましょう。
「まず、『朝起きれないのはしょうがないことなんだ』と思うことです。『起きれない自分が悪い』ではなく『病気だからしょうがない』や『自分ではどうしようもない』と思うことで少し心が楽になります。私の場合は時がたつにつれて症状が軽くなりました。(だんだん起きれるようになりました)また、病院に受診して診断書をもらうのも一つの手です。学校によると思いますが、『起立性調節障害はしょうがないことだ』という考えを持っている学校であれば何かしらの対応をしてもらえるかもしれません。」
このように、まず大切なのは本人と周囲が「これは病気であり、努力不足ではない」という認識を持つことです。その上で、以下のようなサポートが効果的です:
- 学校での配慮: 遅刻や欠席に対する柔軟な対応、別室登校の許可など
- 家庭での理解: 無理に起こそうとするのではなく、症状の重さを理解した上での対応
- 医療機関との連携: 専門医の診断を受け、必要に応じて治療を行う
- 段階的な登校: いきなり毎日フルタイムの登校ではなく、体調に合わせた段階的な登校計画を立てる
特に学校では、起立性調節障害についての理解を深め、「サボっている」という誤解を避けることが重要です。診断書を提出することで、出席や成績評価において配慮を受けられる可能性もあります。
起立性調節障害と上手に付き合う通信制高校という選択肢
起立性調節障害の症状と学校の時間的制約が合わない場合、通信制高校は有効な選択肢となります。通信制高校では自分のペースで学習を進められるため、朝の体調が悪い時でも学習に取り組むことができます。
Cさんが考える通信制高校のメリットは次のとおりです。
「人間関係があまりないので苦労しない(精神的に疲れない)ところや家から出なくてもいいので周りの目を気にしなくて良いというところです。」
通信制高校では、登校日数が少なく、自宅での学習が中心となります。そのため、朝起きられないという起立性調節障害の主症状があっても、自分の体調の良い時間帯に学習することが可能です。また、「周りの目を気にしなくて良い」という点も、心理的なストレスを軽減する大きなメリットです。
さらに、通信制高校では一人ひとりの状況に応じた学習計画を立てることができます。体調の波に合わせて柔軟に学習スケジュールを調整できるため、無理なく高校卒業資格を取得することが可能なのです。
埼玉県越谷市の通信制サポート校での柔軟な学習環境
埼玉県越谷市には、起立性調節障害などの体調不良を抱える生徒でも安心して学べる通信制サポート校(新開高等学院)があります。サポート校では、通信制高校の学習をバックアップするさまざまなサポートが提供されています。
越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)の特徴として、以下のようなものが挙げられます:
- 柔軟な登校時間: 朝起きられない生徒のために、午後からの登校も可能
- 個別学習プラン: 一人ひとりの体調や学習進度に合わせたカリキュラム
- 医療的ケアとの連携: 必要に応じて医療機関と連携したサポート体制
- メンタルケア: 不登校経験や体調不良から生じる心理的負担へのケア
- オンライン学習環境: 体調の悪い日は自宅からオンラインで参加できる仕組み
特に起立性調節障害を抱える生徒にとって、時間的制約が少なく、自分のペースで学べる環境は大きな助けとなります。越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)では、「病気だからしょうがない」という理解の上で、本人の状態に合わせた学習環境が整えられています。
また、同じような症状を抱える生徒同士で交流できる機会もあり、孤独感を軽減することができます。「一人ではない」という安心感は、精神的な支えとなるでしょう。
まとめ:起立性調節障害を理解し、適切なサポートで乗り越える
起立性調節障害は決して怠けや努力不足ではなく、思春期に生じやすい自律神経の疾患です。朝起きられない、立ちくらみがする、疲れやすいなどの症状は本人の意思ではコントロールできないことが多く、周囲の理解と適切なサポートが重要です。
Cさんの体験からわかるように、「朝にみそ汁を食べる」「濃いめのお茶を飲む」といった具体的な工夫や、医療機関への相談が症状改善に役立ちます。また、周囲の人は「しょうがないことだから、その人に合った方法を考えよう」という姿勢で接することが、本人の大きな支えになります。
もし起立性調節障害の症状で学校生活に困難を感じているなら、通信制高校や埼玉県越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)という選択肢もあります。自分のペースで学べる環境で、無理なく学習を続けることが可能です。
Cさんのメッセージにあるように、「時がたつにつれて症状が軽くなる」こともあります。焦らず、自分の体と向き合いながら、適切なサポートを受けて一歩ずつ前に進んでいきましょう。越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)は、そんなあなたの新たな一歩を応援しています。