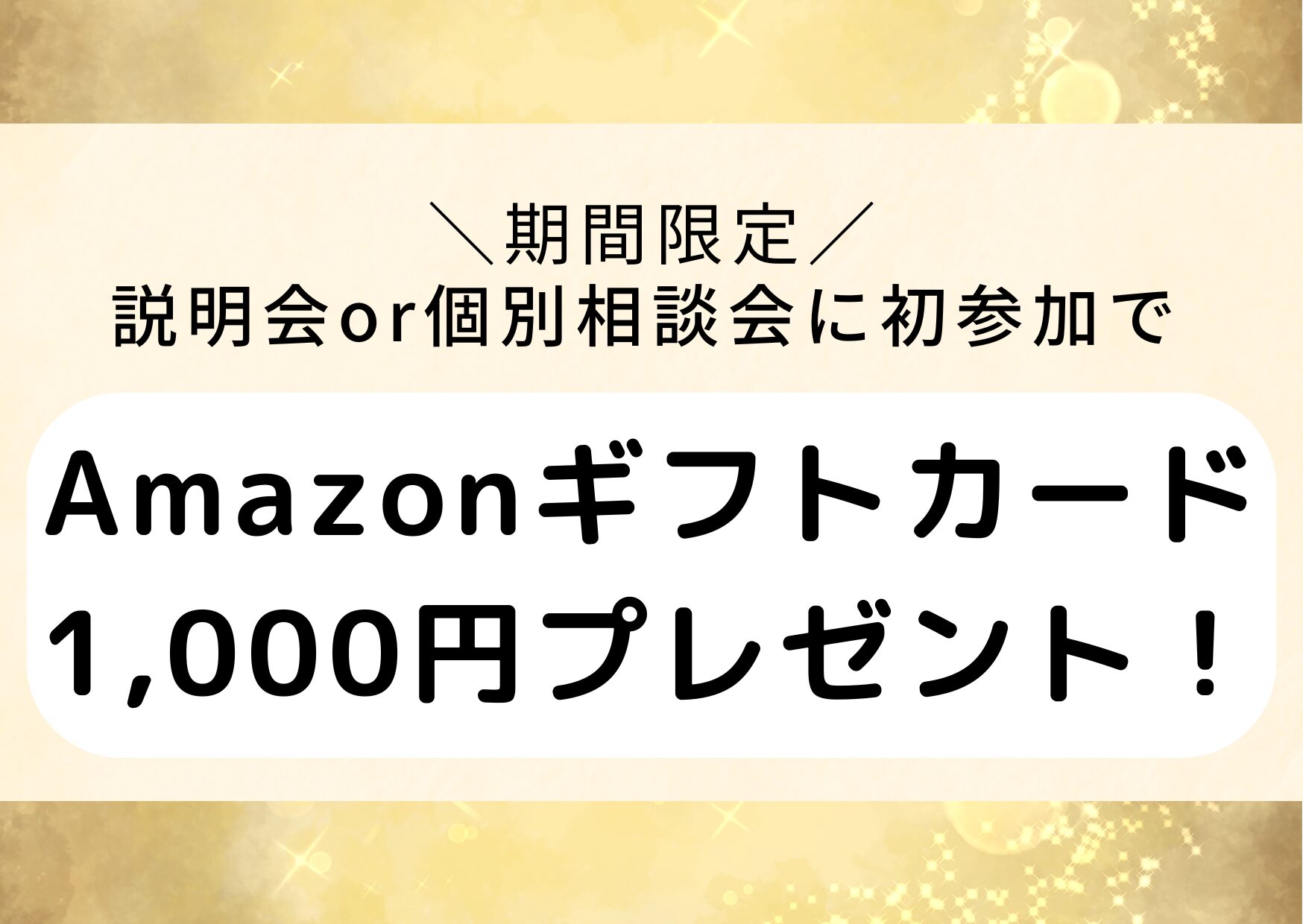【実体験】不登校とSNSの関係 – 経験者が語る適切な距離感

SNSが日常生活に浸透する中、若者の心理や学校生活にも大きな影響を与えています。不登校の原因や悪化要因としてSNSが関連するケースも増えています。この記事では、実際にSNSが関係して不登校を経験したCさんの体験談をもとに、適切な距離感の作り方や対処法についてご紹介します。

SNSと不登校の関係性 – 体験者の声
SNSは人間関係を広げる素晴らしいツールである一方、精神的な負担やストレスの原因になることもあります。特に思春期の中高生にとって、SNS上の評価や交流は現実以上に重要な意味を持つことがあります。
不登校経験者のCさんは、SNSと不登校の関係について次のように語っています。
「SNSとの距離感は近かったと思います。YouTubeを少しやっているというのもあってSNSの事はいつも考えていました。また、不登校になって正直暇だったというのもあって割とずっとSNSを見ていました。」
内閣府の調査によれば、現代の中高生の約9割がSNSを利用しており、1日の利用時間は平均2〜3時間と言われています。また、文部科学省の調査では、不登校の生徒の中にはSNSでのトラブルや過度な利用が背景にあるケースが増加していることが報告されています。
SNSの利用は決して悪いことではありませんが、その影響力を正しく理解し、適切に付き合うことが重要です。特に心理的に不安定になりやすい思春期においては、SNSでの出来事が実生活に大きな影響を与えることがあるのです。
SNSが不登校のきっかけとなった実体験
Cさんに「SNSでのどのような出来事が精神的なダメージになり、不登校のきっかけとなりましたか?」と質問したところ、次のような体験を語ってくれました。
「私の場合は高校に入学して新しい人間関係が作れるか不安でドキドキしている時にSNSでたくさんのアンチコメントがきてしまいました。そうすると学校の事でただでも精神が弱っているのに生活習慣やSNSでの誹謗中傷等が加わって完全に精神が崩壊しました。そこから不登校になってしまいました。」
このように、現実世界での不安やストレスがある状態で、SNS上での否定的な体験が重なることで、精神的な負担が限界を超えてしまうケースがあります。特にCさんの場合は、学校生活への不安が高まっている時期に、SNS上での誹謗中傷が追い打ちをかける形となりました。
日本小児精神医学会の研究によれば、SNSでの誹謗中傷体験は、実際の対面でのいじめに劣らぬ精神的ダメージを与えることが報告されています。特に、以下のような特徴があることが指摘されています:
- 24時間続く可能性: 学校だけでなく家庭でも続く心理的圧迫
- 拡散の速さと広がり: 短時間で多くの人に見られる可能性がある
- 匿名性: 発信者の匿名性により、より過激な内容になりやすい
- 記録の残存: 一度投稿されたものが長期間残り続ける
これらの特徴により、SNS上でのトラブルは現実以上に深刻な影響を与えることがあります。Cさんのように、実際の学校生活の不安とSNSでの問題が重なると、不登校への引き金となりうるのです。
不登校期間中のSNS利用とその影響
不登校になった後のSNS利用についても、その影響は複雑です。Cさんは不登校期間中のSNS利用について次のように語っています。
「不登校になって正直暇だったというのもあって割とずっとSNSを見ていました。ゲームに関しては元からあまりやっていなかったのでほとんどしていませんでした。(YouTubeの撮影でプレイする程度)」
不登校の期間中、家で過ごす時間が増えることでSNSの利用時間が増加しがちです。これには、以下のようなプラス面とマイナス面があります。
プラス面
- 同じような悩みを持つ仲間との出会い
- 情報収集や学習のリソース
- 孤独感の軽減と交流の機会
マイナス面
- 依存症のリスク
- 社会的比較による自己肯定感の低下
- 実際の対人関係構築機会の減少
- 睡眠リズムの乱れ
国立成育医療研究センターの調査によれば、不登校の子どもたちのSNS利用時間は平均の1.5〜2倍になる傾向があるとされています。これは、現実社会からの逃避や孤独感の埋め合わせとしての側面もあると考えられています。
適度なSNS利用は情報収集や気分転換として有効である一方、過度の依存は新たな問題を生み出す可能性があります。不登校期間中のSNS利用についても、適切なバランスが重要なのです。
SNSとの適切な距離感を作る具体的な方法
SNSとどのように付き合えばよいのか、Cさんは自身の経験から次のようにアドバイスしています。
「SNSとの距離感が近すぎると精神的にダメージを受けたり発達によくないので適度な距離感が大切だと思います。実際に『SNSとの距離感を考えていたら不登校にならなかったのかな』などと考えたこともあります。こういった経験をしてSNSが普及している世の中だからこそ、あまりのめり込みすぎず適度な距離感を保って使用することが大切だと思いました。」
では、具体的にどのようにSNSとの適切な距離感を作れば良いのでしょうか。以下に、心理学的研究や専門家の見解に基づいた方法をご紹介します。
1. 利用時間の管理
- 決まった時間だけ利用する(例:1日1時間まで)
- スマートフォンのタイマー機能や使用時間制限機能を活用する
- 就寝前の1時間はSNSを見ない習慣をつける
2. 精神衛生のための工夫
- フォローする人・アカウントを定期的に見直す
- 自分を不快にするコンテンツはミュートやブロックを活用する
- SNSで見た情報を鵜呑みにしない批判的思考を養う
3. リアルな体験とのバランス
- オフラインでの活動や趣味を意識的に増やす
- 家族や友人との直接的なコミュニケーションを大切にする
- 自然の中で過ごす時間を持つ
4. 心理的な距離の取り方
- SNS上の評価と自己価値を切り離して考える習慣をつける
- 「いいね」の数や返信の有無に一喜一憂しない心の持ち方を意識する
- SNSに投稿する前に「本当に必要か」を考える習慣をつける
日本小児科学会のガイドラインでは、中高生のスマートフォン利用時間は1日2時間以内が望ましいとされています。また、就寝の1時間前からはブルーライトを発する画面の視聴を避けることが、良質な睡眠のために推奨されています。
SNSとの健全な関係を築くためには、意識的な利用習慣の形成が重要です。Cさんが言うように、「あまりのめり込みすぎず適度な距離感を保つ」ことが、メンタルヘルスを守るための鍵となるでしょう。
保護者や教員ができるサポート
SNSと不登校の問題に対して、保護者や教員はどのようなサポートができるのでしょうか。Cさんの体験やさまざまな研究から、効果的なサポート方法を考えてみましょう。
保護者ができるサポート
コミュニケーションの強化
- SNSでの体験について、オープンに話し合える関係性を築く
- 批判や否定ではなく、理解と共感の姿勢を示す
- 子どもの話をじっくり聞く時間を定期的に持つ
適切なルール設定
- 家族全体でのデジタルデバイス利用ルールを話し合いで決める
- 就寝時間前のスマートフォン使用制限
- 家族の共有時間(食事など)でのデバイス使用制限
メディアリテラシーの教育
- SNS情報の信頼性を評価する方法を教える
- プライバシー設定の重要性を伝える
- ネット上の言動が他者や自分に与える影響について話し合う
代替活動の提供
- 家族での外出や活動の機会を増やす
- 子どもの興味関心に基づいた趣味や活動を支援する
- リアルな社会体験の機会を意識的に作る
教員ができるサポート
予防的教育
- 学校でのSNS・情報モラル教育の充実
- SNSでのトラブル事例とその対処法についての学習
- クラス内でのSNS利用についてのルール作り
早期発見と介入
- SNSでのトラブルサインに敏感になる
- 生徒の変化(欠席の増加、成績低下など)に注意を払う
- スクールカウンセラーとの連携
フォローアップ体制
- SNSトラブルを経験した生徒への継続的サポート
- 必要に応じた保護者との連携
- 専門機関(医療・相談機関)との協力体制
文部科学省の調査によれば、SNSリテラシー教育を積極的に行っている学校では、SNS関連のトラブルが30%以上減少したという報告もあります。予防的な教育と、問題発生時の適切なサポート体制の両方が重要です。
保護者と教員が協力し、子どもたちのSNS利用を単に制限するのではなく、適切な利用方法を身につけられるよう支援することが大切です。
通信制高校でのSNSとの付き合い方
不登校を経験し、通信制高校に通うことになった場合、SNSとの付き合い方はどのように変わるでしょうか。通信制高校ならではの特徴と関連付けて考えてみましょう。
通信制高校とSNSの関係性
学習ツールとしての活用
- 学習管理アプリやオンラインプラットフォームの利用
- 同じ通信制高校の生徒との情報共有
- 教材や参考資料のオンライン検索
コミュニケーションツールとしての意義
- 通学日数が少ない中での生徒同士のつながり維持
- 教員とのコミュニケーションチャンネル
- 学校イベントやスクーリング情報の共有
自己管理能力の育成
- 通信制高校では自己管理能力が求められる
- SNS利用も自己管理の一環として捉える
- 学習時間とSNS利用時間のバランス調整
通信制高校では、対面でのコミュニケーション機会が限られるため、SNSは人間関係構築の重要なツールとなる一方、学習に集中すべき時間を奪う可能性もあります。自分自身で学習計画を立て、それを実行する自己管理能力の一部として、SNS利用も適切にコントロールすることが重要です。
日本学術会議の報告によれば、通信制高校生のSNS利用は、適切に活用されれば学習成果や学校適応感の向上に寄与する可能性があることが示されています。ただし、その前提として、メディアリテラシーと自己管理能力の育成が不可欠です。
埼玉県越谷市の通信制サポート校 新開高等学院でのメディアリテラシー教育
埼玉県越谷市の通信制サポート校新開高等学院では、不登校経験者やSNSとの関係に悩む生徒のために、さまざまなメディアリテラシー教育プログラムが提供されています。
越谷市の通信制サポート校新開高等学院の特徴
専門的なメディアリテラシー教育
- SNSの適切な利用方法に関する授業
- インターネット上のリスク管理についての学習
- デジタルデバイスの健全な使用習慣の形成
個別カウンセリング
- SNS依存傾向のある生徒への個別相談
- 過去のSNSトラウマからの回復支援
- 自己肯定感を高めるためのカウンセリング
グループワーク
- 同じような経験を持つ生徒同士での体験共有
- ロールプレイを通じたSNSコミュニケーションの練習
- チームでのメディア制作活動
保護者向け支援
- 家庭でのデジタルデバイス利用ルールづくりのサポート
- 子どものSNS利用に関する相談対応
- 親子のコミュニケーション改善サポート
これらのプログラムを通じて、生徒たちはSNSを単なる娯楽や社交の場としてではなく、学習や自己成長のためのツールとして活用する方法を学ぶことができます。また、過去のSNSでの傷つき体験を乗り越え、健全な関係を再構築するための支援も行われています。
越谷市の通信制サポート校新開高等学院では、生徒が社会に出た後も役立つデジタルスキルとメディアリテラシーの習得を支援しています。SNSとの適切な距離感を保ちながら、その可能性を最大限に活かせる力を育てることを目指しているのです。
専門家からみたSNSと不登校の関係
最後に、SNSと不登校の関係について、専門家の見解や最新の研究知見をご紹介します。
心理学的視点から
心理学者は、SNSが青少年に与える影響について、「両刃の剣」であると指摘しています。ソーシャルサポートの獲得や自己表現の場としてのポジティブな側面がある一方、社会的比較による自己肯定感の低下や依存症のリスクといったネガティブな側面も存在します。
特に注目すべきは「ソーシャルコンパリソン(社会的比較)」の問題です。SNS上では他者の生活の「ハイライト」が目立つため、自分の日常と比較して劣等感を抱きやすくなります。こうした心理的プロセスが、学校への行き渋りや不登校の一因になることがあります。
教育学的視点から
教育学者は、SNSリテラシー教育の重要性を強調しています。単にSNSの使用を制限するのではなく、適切な利用方法を教えることが重要だという見解です。これには、情報の真偽を見極める力、人間関係構築のためのコミュニケーションスキル、自己開示の適切な範囲などが含まれます。
また、学校と家庭が連携したSNS教育が効果的であることも指摘されています。学校での体系的な教育と、家庭での実践的なサポートが組み合わさることで、子どもたちのメディアリテラシーが効果的に育まれるのです。
医学的視点から
小児・思春期医学の専門家は、SNSの過剰利用が睡眠障害や注意力低下、抑うつ症状などと関連する可能性を指摘しています。特に、夜間のSNS利用が睡眠の質を低下させ、それが日中の集中力低下や疲労感につながり、登校意欲の減退に影響することがあります。
一方で、適切な利用は精神的健康にポジティブな影響を与える可能性もあるとされています。例えば、同じような悩みを持つ仲間との出会いや、興味関心に基づくコミュニティへの参加は、自己肯定感や帰属意識の向上に貢献することがあります。
統合的アプローチの重要性
これらの専門的知見を総合すると、SNSと不登校の問題に対しては、以下のような統合的アプローチが効果的だと考えられます:
- 予防的教育: メディアリテラシー教育の充実
- 適切な利用環境: 家庭や学校でのルール設定
- 心理的サポート: SNS利用に関連する不安や悩みへの相談体制
- 代替活動の充実: リアルな体験や対面活動の機会提供
- 専門機関との連携: 必要に応じた医療・相談機関との協力
Cさんの体験が示すように、SNSは現代の若者にとって切り離せない存在です。そのネガティブな影響を最小限に抑えながら、ポジティブな可能性を引き出すための環境づくりと教育が求められているのです。
まとめ:SNSとの健全な関係づくりが不登校予防と回復の鍵
SNSは現代社会において若者の生活に深く浸透しています。不登校とSNSの関係は単純ではなく、きっかけとなることもあれば、孤独感を和らげる助けになることもあります。大切なのは、その両面を理解し、適切な距離感を保つことです。
Cさんの体験談にあるように、「SNSとの距離感が近すぎると精神的にダメージを受けたり発達によくない」一方で、適切に活用すれば有益なコミュニケーションツールになります。埼玉県越谷市の通信制サポート校(新開高等学院)では、このようなSNSの両面性を理解し、健全な関係づくりを支援するプログラムが提供されています。
不登校からの回復プロセスにおいても、SNSとの適切な付き合い方を学ぶことは重要です。「あまりのめり込みすぎず適度な距離感を保って使用する」というCさんの言葉は、すべての若者にとって貴重なアドバイスと言えるでしょう。
SNSは使い方次第で、自己成長や学びの機会になることもあれば、精神的な負担の原因になることもあります。それぞれの特性を理解し、バランスの取れた利用を心がけることが、不登校の予防と回復の両方において重要なのです。
通信制高校やサポート校という選択肢は、不登校を経験した生徒が自分のペースで学びを継続しながら、SNSとの健全な関係を再構築する機会を提供してくれます。越谷市の通信制サポート校新開高等学院では、一人ひとりの状況に合わせたサポートが受けられますので、不登校やSNSの問題でお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
新開高等学院(南越谷)について
通信制高校にはさまざまな課題が存在しますが、新開高等学院では独自の教育アプローチと充実したサポート体制によって、これらの課題を効果的に解決しています。埼玉県越谷市にある新開高等学院は、「卒業できるだろうか」「進学は本当に可能なのか」「心理的な問題で通えなくなったらどうしよう」といった不安を抱える生徒や保護者に、確かな解決策を提供しています。

新開高等学院が解決する通信制高校の3つの課題

1. 卒業率の低さ
多くの通信制高校では卒業率が低い傾向にありますが、新開高等学院では個別指導を重視し、一人ひとりの状況に合わせた学習サポートを行うことで卒業資格取得率97%という高い実績を誇ります。確実な進級・卒業に向けて、担当教員が継続的にサポートし、挫折せずに学び続けられる環境を提供しています。
2. 進学サポートの不足
「通信制高校からは大学に進学できない」という誤解がありますが、新開高等学院では大学受験に強いサポート体制を構築。AO入試対策を強化し、自己PRや面接対策の個別指導に力を入れています。進学希望校の合格に向けた対策を徹底的に行い、総合型選抜入試に強いことが特徴です。
3. 心理的な壁で通えない不安
心理的な理由で通学が難しくなる心配を抱える生徒や保護者は多いですが、新開高等学院では「心理的安全性の確保」を最優先。専門のカウンセラーへの相談体制を整え、さらに気持ちを表に出しにくい生徒のために悩み相談アプリを開発。いじめを絶対に許さない姿勢で学びの場を守り、心の土台を整える授業を通して生徒の精神的成長をサポートしています。
新開高等学院の3つの強み
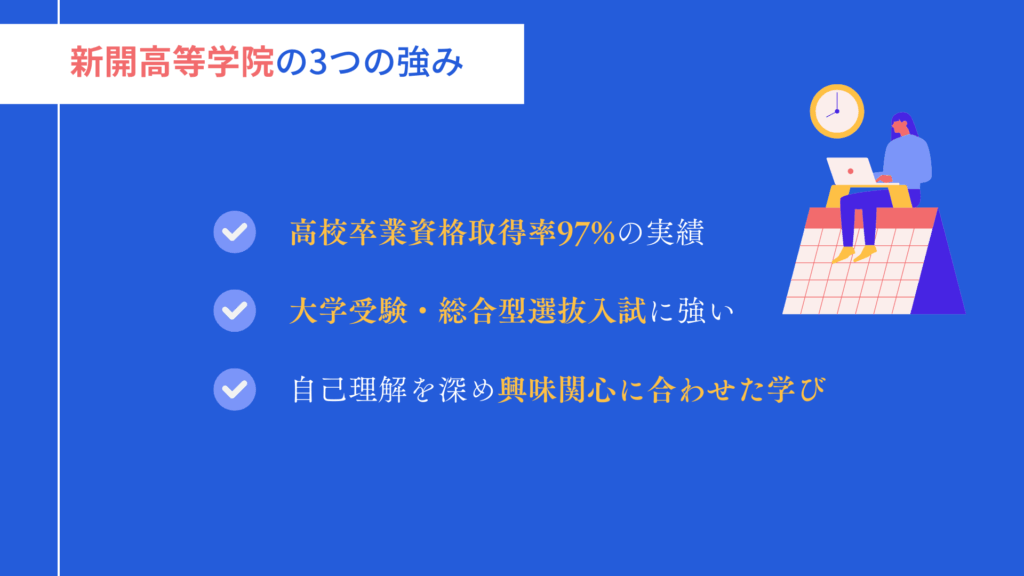
1. 高校卒業資格取得率97%の実績
新開高等学院では、個別指導を通じて生徒一人ひとりの高校卒業資格の取得をサポート。その結果、97%という高い資格取得率を達成しています。確実な通信制度を行い、卒業に向けて着実に歩める環境を提供しています。
2. 大学受験・総合型選抜入試に強い
AOや総合型選抜入試に特化した対策を実施。自己PRや面接対策を個別指導し、進学希望校への合格をサポートします。英語教育にも力を入れており、留学支援も行っているため、大学進学においても有利に進められる環境が整っています。
3. 自己理解を深め興味関心に合わせた学び
新開高等学院では9つの質問を通して自分の内面と向き合い、「自分らしさ」を発見する自己理解プログラムを提供。28の価値観キーワードで自分の方向性を明確化し、「探究」「挑戦」「創造」「貢献」などの価値観を言語化します。その上で多様な体験を通して自分の好きなことや得意なことを見つけ、その興味を深め、将来につなげていくための3ステップの学びを提供しています。
新開高等学院の心理的安全性を最優先する学習環境
新開高等学院の最大の特徴は「心理的安全性の確保」です。安定的に学生生活を過ごし、学びを進めるためには心理的な安全性が不可欠であると考えています。
悩みを防ぐアプリの開発
気持ちを表現するのが得意でない生徒でも安心して学べるよう、気持ちや悩みを気軽に共有できるアプリを独自開発。表面では分からない気持ちや悩みにも寄り添います。
いじめを絶対に許さない姿勢
新開高等学院ではいじめは絶対に許さないという姿勢を持って指導。生徒たちの創造性や個性を尊重しつつも、人を傷つける行為に対しては厳正に対処しています。
心の土台を整える授業
「失敗への向き合い方」や「プラス思考になるためのコツ」など、心の土台を整えるための授業を実施。学びを進めていく上で必要な精神的成長をサポートしています。
新開高等学院の生徒の可能性を広げる学習アプローチ
「見つける・探す・繋げる」3ステップの学び
新開高等学院では生徒の興味関心を「見つけ、深め、未来に繋げる」学びを提供しています。プログラミング、ゲーム作り、YouTubeチャンネル運営、イラスト・マンガ制作、ダンス、音楽制作など、多彩な体験を通して自分の「好き」を探し、それを将来の進路につなげていきます。
英語教育の充実
新開高等学院では希望する生徒に対して、1年生から無償で英語力を入れて学べる環境を提供。英語が苦手でも「ゼロから始める」気持ちをしっかりサポートし、留学や就職、大学受験において有利になるよう指導しています。
柔軟な学習スタイル
オンラインでも対面でも学べる柔軟な学習スタイルを提供。週に1回を目安に行動計画を一緒に立てる通学スタイルを推奨していますが、生徒の状況に応じて週2日、週3日など、通学頻度を自分で決めることができます。
他校との比較で見る新開高等学院の特徴
新開高等学院は他の通信制高校と比較ると、以下のような特徴があります。
自由とサポートのバランス
新開高等学院の最大の強みは、生徒の自由を尊重しながらも適切なサポートを提供するバランスの取れた教育アプローチです。週1回を目安に教員と一緒に行動計画を立てることで、自己管理能力を育みながらも孤立せずに学習を進めることができます。
また、オンライン学習も可能ですが、定期的な対面指導を通じて学習の進捗確認やモチベーション維持のサポートを行っています。
少人数制による充実した指導
少人数制のクラス編成により、教員が生徒一人ひとりの学習状況や課題を把握し、きめ細かな指導を行うことが可能です。これにより、学習面での不安や疑問点をリアルタイムで解決し、学習の遅れを防止します。
学内で完結する学習環境
新開高等学院では、外部の学習塾に通う必要がなく、学内の授業や指導だけで高校卒業に必要な学力を身につけることができます。大学受験対策なども校内で提供されており、追加費用をかけずに進学準備が可能です。
興味関心に応じた学びのサポート
生徒それぞれの「やりたいこと」や「興味のあること」に対して、単に応援するだけでなく、具体的な方向性を示したり、必要なスキルの習得をサポートしたりする手厚い支援を行っています。これにより、将来の進路や夢に向けた実践的な学びが可能になります。
経済的な負担への配慮
年間学費は46万円と、広域通信制高校と比較して実質的な負担が少なく設定されています。さらに、外部の学習塾や予備校に通う必要がないため、追加の教育費用も抑えることができます。
新開高等学院の支援内容一覧
生活面のサポート
- 心理的な安全性が保たれるような場づくり
- いじめが起こらないよう人間関係に配慮
- ボランティア、アルバイト、インターンに対する支援
- 就職についての支援
学習面のサポート
- 高校卒業資格取得の支援
- 通信制高校のレポートやテストの支援
- 一般入試や総合型選抜入試、推薦入試への対応
- 興味関心のある学習内容に関して詳細な指導
その他の支援
- オンライン語学学習(英語・韓国語)の提供
- 海外留学のサポート
- 国内留学の案内
- オンラインカウンセリングの提供
まとめ:通信制高校の課題を解決する新開高等学院
通信制高校で多く見られる「卒業できるか不安」「進学は難しいのでは」「心理的な問題で通えなくなるかも」といった悩みを解決するのが新開高等学院です。97%の高い卒業率、総合型選抜入試に強い進学サポート、そして何より心理的安全性を最優先にした学習環境が、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出します。
少人数制で一人ひとりに寄り添い、個別指導を重視する新開高等学院は、通信制高校で学ぶすべての生徒とその保護者の不安を解消し、確かな未来への道筋を示してくれる教育機関です。心理的サポートと学習サポートの両面から生徒をバックアップする新開高等学院で、安心して高校生活を送りませんか?
【新開高等学院の基本情報】
- 住所:〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目27-7
- 学習スタイル:オフライン(オンラインも可)
- 通学頻度:週1回を目安に行動計画を一緒に立てる(週2日、週3日など自由に選択可)
- 卒業資格取得率:97%
- 問い合わせ:公式サイトより

この記事の監修者
乗松 拓弥
新開高等学院 代表者プロフィール
氏名:乗松拓弥
株式会社テトリオ 代表取締役社長
新開高等学院 学院長
【教育業界での豊富な実績】
◆ 大手学習塾での指導経験
- 学習塾において4年間、高校受験・大学受験指導に従事
- 年間100名以上の生徒指導実績
◆ 教育現場での実務経験
- 私立学校教員として学校の立ち上げ、担任としての職務に従事
- 公立校の教員として担任の職務に従事
- 不登校生徒の復学支援プログラム開発に参画
【専門分野と実績】
✓ 多様な進路選択のサポート
- 大学AO入試・総合型選抜指導:合格率90%
- 大学受験専門塾での指導
- 起業、マーケティング、広告運用など幅広い実務経験
【保有資格・認定】
- 教諭免許状
【メディア出演・講演実績】
◆ メディア掲載
- abemaTV「新しい学校づくりについて」(2020年)
- ラジオ出演(2020年)
- 教育科学研究会の冊子に掲載
- 書籍「学校ってなんだろう」一部執筆