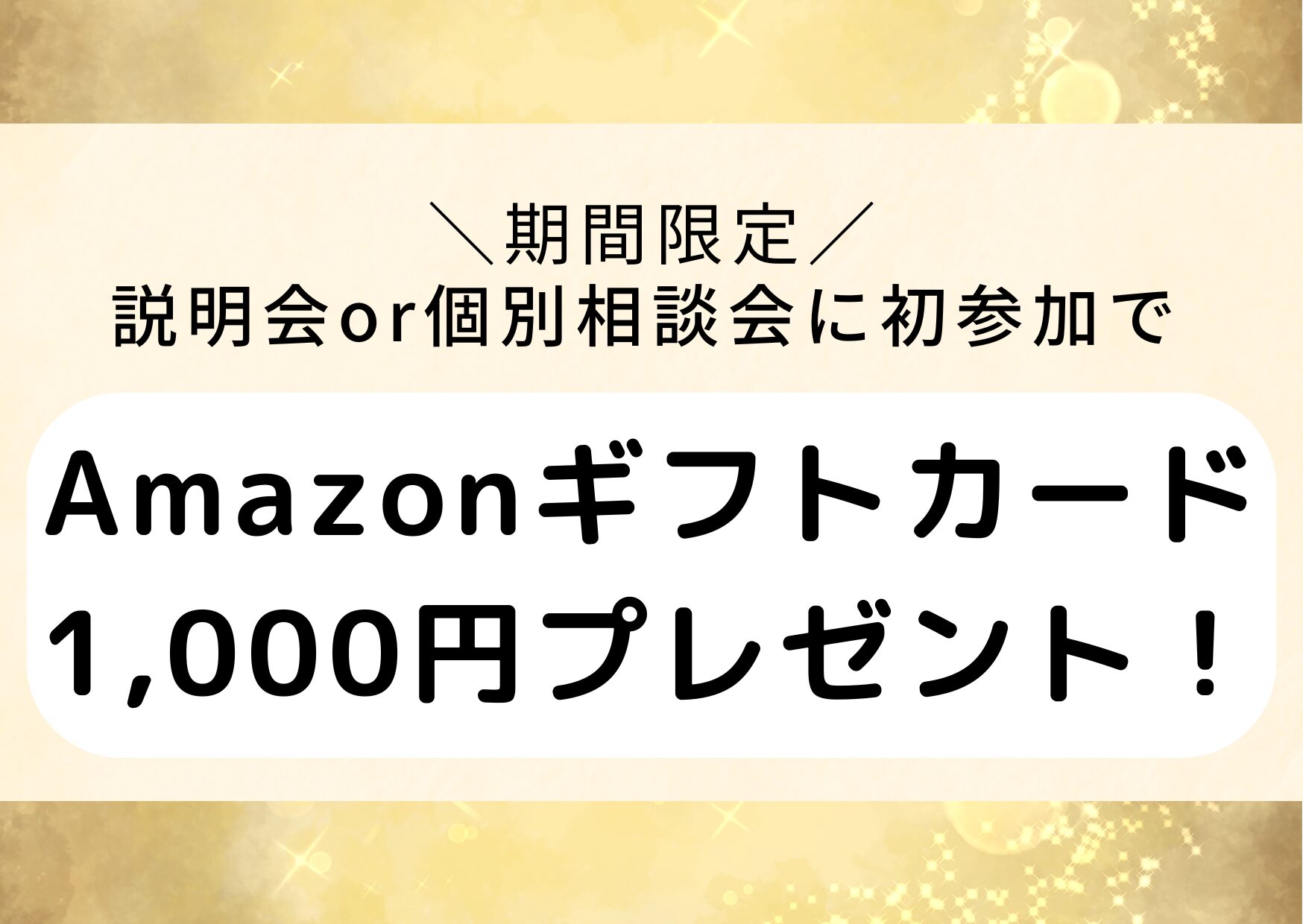【実体験】ダウン症の子どもと進路選択 – 通信制高校が広げる可能性と未来
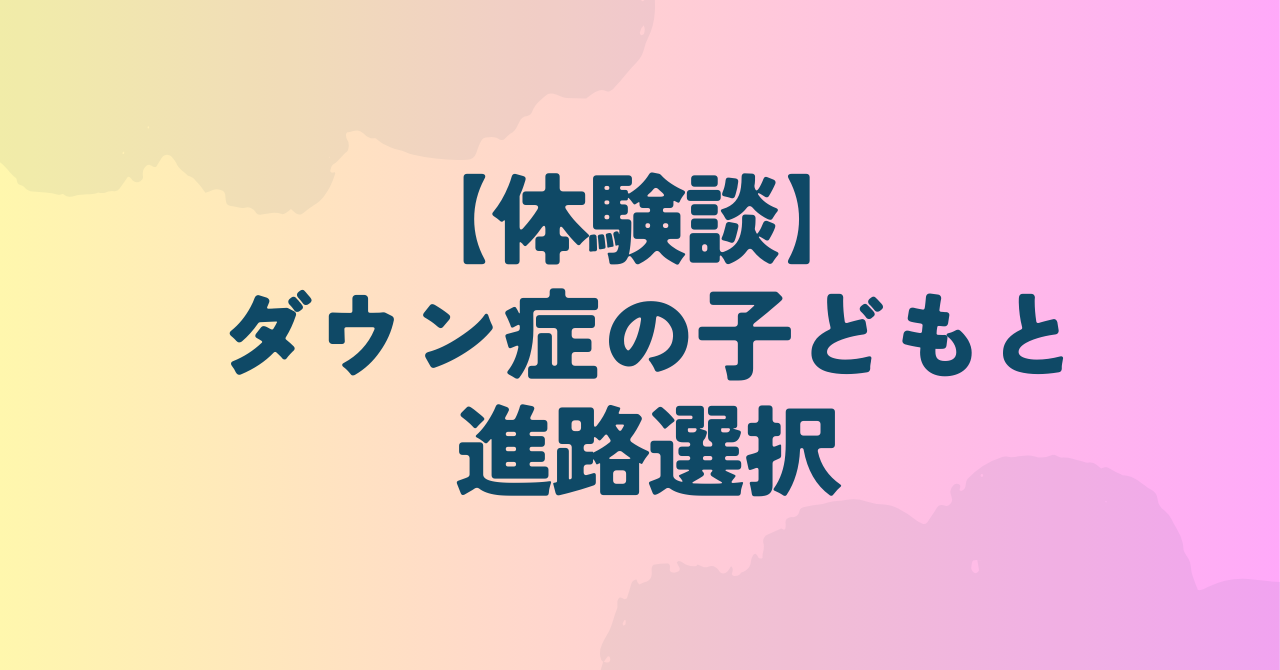
この記事は、ダウン症や発達障害のお子さんを育てた親の実体験に基づいた内容です。障害を持つ子どもの教育選択や不登校から社会参加への道筋について、貴重な経験をお伝えします。特に通信制高校という選択肢がどのように子どもの可能性を広げるかについて詳しくご紹介します。不快に感じられる方もおられるかも知れませんが、同じ悩みを抱える方々の参考になれば幸いです。
目次
- 我が子のダウン症診断と初期の葛藤
- 教育選択の分岐点 – 地域の小学校か特別支援学校か
- 不登校リスクと将来を左右する選択
- 社会参加を実現した現在の生活
- 通信制高校という選択肢 – 障害のある子どもの新たな学びの場
- 通信制高校で実現する個別最適化された学習環境
- 不登校経験から学ぶ – 通信制高校がもたらす心理的安全性
- 卒業後の進路と社会参加 – 通信制高校卒業生の多様な選択肢
- 家族の役割と支援体制 – 子どもの可能性を広げるために
- 通信制高校で実現する個別に応じた学びと社会参加への道
- まとめ – 一人ひとりに合った教育環境の大切さ
1. 我が子のダウン症診断と初期の葛藤
私の子どもは生まれてすぐにダウン症と診断されました。出産後すぐに分娩室から連れていかれ、ずいぶん時間が経った後、主人だけが別室に呼ばれました。
「心臓に大きな病気をもっておられるようですので、すぐにNICUのある総合病院に転院します。また、心臓に大きな病気をもって生まれるお子さんは他の病気も考えられるため、遺伝子の検査をおすすめします。」
これが主治医からの第一声でした。総合病院に向かう救急車の中で、別の医師から「顔貌がダウン症なので、遺伝子検査をおすすめします」と言われたそうです。
遺伝子検査の結果、1度目は「異常なし」でしたが、2度目に「ダウン症転座型」と診断をされました。生まれて4か月で心臓の手術を受け、中学校に入学する前にも再度手術を受けました。
生まれた当時はダウン症児の平均寿命がとても短く、担当医からは「20歳まで生きられないと考えておいてください」と言われるほど、まだまだ医学が発展しておらず絶望的な状況でした。
診断を受けた日の晩、私たち夫婦は朝まで泣き明かしました。「一体この先どのような人生が待っているのか」「自分の人生、子どもの人生、自分の親のこと、親戚のこと」。たくさんのことを考えると涙が止まりませんでした。
しかし、時代は移り変わり、医学が発展し、私の子どももついに成人を迎えることができました。現在は仕事にも行っており、社会との関わりもできております。子どもの障害により体験してきたことも今では思い出となり、家族で笑いあえるようになりましたが、絶望からどのように這い上がってきたのか、また数々の分岐点をどのように選択してきたのか、体験をつづりたいと思います。
2. 教育選択の分岐点 – 地域の小学校か特別支援学校か
私の住むまちでは、入学前に保護者の希望を聞いてくださる機会があり、総合支援学校か地域の学校のどちらに進学させたいかのヒアリングを受けます。小学校に入学する前に私たち夫婦と子どもの3人でヒアリングを受けることになりました。
私たち夫婦は、地域の小学校への入学ではなく総合支援学校への入学を希望しました。その理由は、地域の小学校へ入学し6年間を過ごすことになっても子ども自身に無理をさせるのではないか、同じ教育を受けるのなら子どものペースに合わせた内容で受けさせた方が良いのではないかといった気持ちがあったからです。
しかし、教育委員会から出された結論は、地域の小学校へ入学するという私たち夫婦の希望とは反対のものになりました。教育委員会に何度か理由を尋ねたものの曖昧な返答しかいただけず、入学後に風のうわさで耳に入ってきた内容は、この学年は他にも重度の障害者が多くいたため、その子どもたちを優先し総合支援学校に入学させたとのことでした。
頭では理解しているつもりでしたが、やはり自分の子どもが蔑ろにされたような気分でおり、子どもが小学生の間は学校の先生とも何度かもめたこともありました。今、考えると私たち夫婦の心のどこかに子どもがいじめられるのではないかといった心配があったことと、地域社会に溶け込ませることにより自分たちが恥ずかしい思いをするのではないかといった気持ちがあったのだと思います。
この時点で、多くの親御さんが直面する「インクルーシブ教育か特別支援教育か」という選択の難しさを私たちも経験していました。特に日本の教育制度では、この選択が子どもの将来に大きく影響することを後に実感することになります。
3. 不登校リスクと将来を左右する選択
6年間の小学生時代はなんとか過ごすことができ、中学校の入学前に小学校のときと同じように3人でヒアリングを受ける機会がありました。当然ですが、6年間我慢してきたという主張もし、手術の結果は成功ではあったものの今後も心臓の障害は残ることを説明した結果、無事に総合支援学校に入学することが決まりました。
小学校で私の子どもを含め同じように障害をもった同級生が3人おり、ほかの2人は発達障害児でした。2人とも地域の中学校への入学を希望され、そちらも希望通りになりました。しかし、私たち夫婦は少し違和感を覚えることになります。
実は地域の小学校へ入学を希望された2人のうち、1人(以下A君)は重度の発達障害児でした。小学校時代から先生の指示を聞くことができず、教室から逃走するなどクラスでもかなり問題を起こしておりました。問題行動といっても小学校の男子の範囲ですので、誰かに怪我をおわせたり、自分自身が自傷行為をするところまではいきませんでしたが、担任も常にバタバタされており、総合支援学校でA君にあった教育を受けられるものだと勝手に考えておりました。
A君に関しては、加配がつかないと中学校では難しいのではないかと心配もしておりましたが、結果的には育成クラスに属する形での入学になりました。ちなみにA君のお父さんは我が子の障害に対して受け入れられておらず、「この子なら大丈夫だ」と判断されていたそうです。
一方で、私の子どもは総合支援学校にうまく溶け込むことができ、技能習得や字を書く練習など子どもの成長度合いに合わせた学習時間を過ごすことができました。ダウン症といえども知能指数も子どもによって大幅に異なりますが、私の子どもは最重度の知的障害でしたので、字を書くことができるようになっただけでも大きな成長でした。
子どもが中学校3年生になるくらいのときに近所を歩いており、偶然A君のお母さんに出会いました。私の子どもの近況報告をすると同時にA君の最近の様子をそれとなく聞いてみると、なんと中学校に入学後すぐに不登校になったそうです。
理由は、小学校から同じように地域の中学校に入学した健常者の同級生からのいじめと、担任の手が回らずそれを防ぎきれなかったとのことでした。入学後1か月も経たない間に不登校となり、その後何度かチャレンジはしたもののA君のパニックがひどくなり、強い薬(脳を安定化させるもの)を服用していくたびにA君の動きも鈍くなっていったそうです。
学校が合わなかったのか、薬が合わなかったのかは私には分かりませんが、その時出会ったお母さんはとても辛そうなお顔でしたので、ご苦労をされたのだと察しました。また、A君は自宅に引きこもりゲームばかりしているとのことで、高校への入学も諦めていると伺いました。
私の子どもはダウン症で重度の知的障害でしたが、中学校から総合支援学校に通うようになり、そのまま高校へも進学が決まっておりましたので、A君の未来を考えると少し心配になりました。
私たち夫婦はその日の晩、A君の話をしました。結果として私たちの子どもは毎日楽しく学校に通えている一方で、地域の中学校を選択したA君は学校にも通えず、総合支援学校への転校も認められず、高校への進学もできない状況となりました。
決してA君のご両親を責めるつもりはありませんが、もしかしたら新しい環境に馴染むことができず不登校から引きこもりになったのかも知れません。いじめられたA君が悪いのではなく、当然いじめた側にも大きな課題はありますが、中学生の男の子同士のことですので、とても繊細な内容であったことは間違いありません。
この時点で私たちは、「適切な教育環境」の選択がいかに重要か、身をもって知ることになったのです。そして、この経験から後に通信制高校という選択肢の価値を深く考えるようになりました。
4. 社会参加を実現した現在の生活
私の子どもは無事に高校を卒業し、現在は私の助手として同じ会社に勤めております。助手としての扱いになりますので、正当な賃金はいただかず、あくまで私の業務のサポートをするという立場になります。上司もこの状況を認めてくださり、半分以上が社会貢献の気持ちのようです。
また、週に2日はデイサービスに通い、同じような障害を持った人たちとの交流の場もあり、本人はとても充実した毎日を送っております。手術をした心臓も術後のフォローは3か月に1回の通院だけになりました。経過も良く、今後手術をする必要はないと主治医からも言われております。
自分の子どもがダウン症だと聞かされた日の晩は夫婦で朝まで泣きました。一体この先どのような人生が待っているのか。自分の人生、子どもの人生、自分の親のこと、親戚のこと。たくさんのことを考えると涙が止まりませんでした。
しかし、今となってみれば、大したことではなく、子どもが元気に会社に通って私の仕事を手伝ってくれているだけで幸せな毎日を過ごしております。また、家事も積極的に手伝ってくれますので、今や私の片腕としては欠かせない存在になりました。
これから先もきっと結婚はしないでしょうし、一人暮らしや施設への入所も考えておりませんので、私たち夫婦の元から離れることはないでしょう。それでも家族の一員として、また社会の一員として生きていてくれるだけで幸せな日々を送ることができるのです。
知能指数は低くとも子どもの能力を生かす場面はたくさんありますし、それを見つけることが親としての使命であり、社会との断絶だけはさせまいと私自身も奮闘する毎日ですが、とても充実しております。
同じように小学校に入学し、同じように小学校を卒業したA君は中学校から学校に行けなくなり、今も引きこもりの状態が続いております。知能指数では圧倒的に低かった私の子どもは成人し、仕事にデイサービスにと忙しい毎日を過ごしております。この差が生まれた分岐点はどこにあったのか、今でもふと考えることがあります。
この経験から、私たちは「障害の程度」よりも「適切な環境選択」こそが子どもの将来を大きく左右すると確信するようになりました。そして、A君のようなケースでは通信制高校という選択肢が大きな可能性を持っていたのではないかと考えるようになったのです。
5. 通信制高校という選択肢 – 障害のある子どもの新たな学びの場
私たちが経験したA君のような不登校の状況は、残念ながら障害を持つ子どもたちの中で珍しいケースではありません。特に発達障害やその他の障害を持つ子どもたちは、一般的な学校環境での集団生活や学習に困難を感じることが多いのが現実です。
そのような子どもたちにとって、通信制高校は大きな可能性を秘めた選択肢となります。通信制高校の最大の特徴は、「個別のペースで学べる」という点にあります。一斉授業についていけないという不安や、集団生活でのストレスから解放され、自分のタイミングで学習を進めることができるのです。
また、通信制高校では「スクーリング」と呼ばれる登校日を設けていますが、その頻度は学校によって様々で、月に数日程度の学校も多くあります。体調や精神状態に配慮しながら、無理なく学校生活を送ることができるのです。
特に不登校を経験した子どもたちにとって、「学校に行かなければならない」というプレッシャーは非常に大きなものです。通信制高校ではそのプレッシャーを軽減しながらも、高校卒業資格という将来に向けた大切な一歩を踏み出すことができます。
私たちの経験から言えることは、A君のような状況に直面した場合、通信制高校という選択肢があれば、不登校から引きこもりという負のスパイラルを防ぐことができたかもしれないということです。中学校で不登校になった場合でも、次のステップとして通信制高校という選択肢があることで、子どもと親の希望を繋ぎ止めることができるのです。
6. 通信制高校で実現する個別最適化された学習環境
通信制高校の最大の魅力は、子どもの特性や状況に合わせた「個別最適化された学習環境」を提供できる点にあります。一般的な全日制高校では実現が難しい、一人ひとりに寄り添った教育が可能になるのです。
6-1. 個別学習計画の策定
通信制高校では、入学時に子どもの特性、得意・不得意、学習の進捗状況などを詳細に把握し、個別の学習計画を立てることができます。ダウン症や発達障害など、様々な特性を持つ子どもたちにとって、「自分に合ったペース」で学べることは非常に重要です。
例えば、数学が苦手な子どもには基礎からじっくり学ぶカリキュラムを、国語が得意な子どもにはより発展的な内容を提供するなど、柔軟な対応が可能です。私の子どものように知的障害がある場合でも、その子の理解度に合わせた教材や指導方法を選択できます。
6-2. ICTを活用した学習支援
近年の通信制高校では、タブレットやパソコンを活用したオンライン学習も充実しています。視覚情報を多用した教材は、特に言語理解に難しさを抱える子どもたちにとって効果的です。また、音声読み上げ機能や文字拡大機能など、障害特性に配慮したアクセシビリティ機能も充実しています。
私の子どもも、文字を読むことには苦労しましたが、イラストや写真を多用した教材では理解が進むことがありました。通信制高校では、こうした多様な学習ツールを活用することで、従来の教科書だけでは難しかった学びをサポートします。
6-3. 専門スタッフによるサポート体制
多くの通信制高校では、特別支援教育の知識を持つ教員や、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーなど専門スタッフが在籍しています。子どもの特性を理解したうえでのサポートが受けられるため、「理解されない」というストレスも軽減されます。
私たちが総合支援学校を選んだ理由の一つも、専門的な知識を持つ教員の存在でした。通信制高校でも同様に、障害特性を理解したスタッフのサポートを受けられることは大きな安心につながります。
7. 不登校経験から学ぶ – 通信制高校がもたらす心理的安全性
A君のように不登校を経験した子どもたちにとって、「学校」という場所自体が大きなプレッシャーとなることがあります。通信制高校では、そうした心理的負担を軽減しながら学びを継続することができます。
7-1. 「行かなければならない」というプレッシャーからの解放
通信制高校では、毎日通学する必要がなく、スクーリングと呼ばれる登校日も学校によって月に数日程度と少ないケースが多いです。「毎日学校に行かなければならない」というプレッシャーから解放されることで、子どもたちは精神的な余裕を持って学習に取り組むことができます。
A君の場合、中学校入学後すぐに不登校になったと聞きましたが、毎日の通学がもたらすストレスが大きな要因だったかもしれません。通信制高校であれば、そうしたストレスを大幅に軽減できたでしょう。
7-2. いじめや対人関係のストレスの軽減
A君が不登校になった直接の原因は同級生からのいじめだったとのことです。通信制高校では、対面での接触機会が限られるため、いじめのリスクも大幅に減少します。また、スクーリング時も少人数制のクラス編成が多く、教員の目が行き届きやすい環境が整っています。
障害のある子どもたちは、残念ながらいじめの標的になりやすい傾向があります。通信制高校という選択肢があれば、そうした不安から子どもを守りながら、学びを継続することができるのです。
7-3. 心理的安全性を確保した再スタート
不登校を経験した子どもたちにとって、「また学校が合わなかったらどうしよう」という不安は非常に大きなものです。通信制高校では、子どものペースに合わせた段階的な学校復帰が可能です。
例えば、最初は自宅学習のみから始め、徐々にスクーリングに参加する日数を増やしていくなど、子どもの状況に応じた柔軟な対応ができます。心理的安全性を確保しながら、少しずつ社会とのつながりを取り戻していくことが可能になるのです。
8. 卒業後の進路と社会参加 – 通信制高校卒業生の多様な選択肢
通信制高校を卒業することで、子どもたちの将来の選択肢は大きく広がります。高校卒業資格は、社会で生きていくための重要な足がかりとなるからです。
8-1. 進学の可能性
通信制高校でも全日制高校と同じ高校卒業資格が取得できるため、大学や専門学校などへの進学も可能です。特に障害特性に配慮した入試制度を設けている大学も増えており、子どもの特性や得意分野を活かした進学の道が広がっています。
知的障害がある場合でも、芸術や音楽、スポーツなど特定の分野で才能を発揮する子どもたちもいます。通信制高校でそうした才能を伸ばしながら、専門的な分野への進学を目指すことも可能です。
8-2. 就労支援と職業訓練
多くの通信制高校では、卒業後の就労を見据えたキャリア教育や職業訓練も行っています。障害特性に合った仕事選びや、就労支援機関との連携など、社会参加に向けたサポートが充実しています。
私の子どもは現在、私の助手として働いていますが、これも高校時代に身につけた基本的なスキルがあってこそ可能になったことです。通信制高校でも、子どもの特性に合わせた職業教育を受けることで、将来の就労に向けた準備ができます。
8-3. 社会参加の多様な形
卒業後の選択肢は進学や就労だけではありません。福祉的就労や地域活動への参加など、様々な形で社会とつながっていくことができます。
私の子どもは会社勤務の他に、週に2日デイサービスに通っていますが、これも社会参加の重要な形です。通信制高校では、こうした多様な社会参加の形について学び、子ども自身が自分の将来を考える機会を持つことができます。
9. 家族の役割と支援体制 – 子どもの可能性を広げるために
障害のある子どもの教育選択において、家族の役割は非常に重要です。私たちの経験からも、家族のサポートが子どもの成長に大きく影響することを実感しています。
9-1. 子どもの特性を正しく理解する
A君のケースでは、お父様が子どもの障害を受け入れられていなかったとのことでした。子どもの特性を正しく理解し、適切な環境選択をするためには、まず家族が子どもの障害と向き合うことが大切です。
私たちも最初は絶望し、朝まで泣いたこともありましたが、子どもの状態を冷静に見つめ、できることとできないことを見極めた上で、最適な選択をしようと努めてきました。
9-2. 情報収集と専門家との連携
障害のある子どもの教育選択には、多くの情報と専門的な知識が必要です。教育委員会や支援機関、医療機関など、様々な専門家と連携しながら情報収集することが重要です。
私たちも多くの専門家からアドバイスを受け、また同じような状況の家族との情報交換を通じて、子どもに最適な選択を模索してきました。通信制高校を検討する際も、実際に見学や相談を重ねることで、子どもに合った環境かどうかを見極めることができます。
9-3. 子どもの「働く」意欲を育む家庭環境
私の子どもが現在、仕事や家事を積極的に手伝ってくれているのは、家庭で「働く」ことの意義を伝えてきたからかもしれません。
有名人が言われていたように、「働く」という言葉は「はたを楽にする」という語源があり、「人べん」に「動く」となったそうです。自分のそばにいる人に楽をさせたい、自分のはたにいる人に楽になってもらいたい、といった気持ちで動くことが働くことになり、結果的には収入になるのです。
私の子どもも口にはしませんが、常に周囲を気にしており、誰かを楽にするために行動しております。小さなことで例を挙げると、お父さんの翌日の仕事の準備は子どもの日課です。ハンカチやマスクを用意し、お父さんが気持ちよく仕事に行けるよう毎日準備をしております。
また、私と一緒に仕事に行く朝は、必ず私の制服を2階から持ってきてくれます。私がバタバタと2階にあがることがないよう、子どもは私の制服の手配をすると同時に自分の仕事の準備をしております。
「働く」ということは簡単なことではありませんが、このような気持ちや行動が周囲にとっても子ども自身にとってもより良い環境を形成していることは間違いありません。だからこそ、子どもが将来困らないよう会社を設立し、社会とつながりを持てるようにしました。
10. 通信制高校で実現する個別に応じた学びと社会参加への道
これまでの私たちの経験から、障害のある子どもたちにとって「適切な教育環境」がいかに重要かを実感してきました。特に不登校を経験した子どもたちにとって、通信制高校は新たな可能性を開く選択肢となり得ます。
10-1. 通信制高校のメリット – 障害のある子どもの視点から
通信制高校には、障害のある子どもたちにとって多くのメリットがあります:
- 自分のペースで学習できる: 障害特性や理解度に合わせたカリキュラムで無理なく学べます。一斉授業についていけないというプレッシャーから解放され、自信を持って学習に取り組めます。
- 不登校経験からの再出発: A君のように中学校で不登校になった場合でも、通信制高校なら少ないスクーリング日数から始め、徐々に学校生活に慣れていくことができます。
- 柔軟な通学スタイル: 体調や精神状態に合わせた通学が可能です。通学が難しい日はオンライン学習で対応するなど、子どもの状況に合わせた柔軟な対応ができます。
- 多様な学習スタイル: 視覚教材、聴覚教材、体験型学習など、様々な学習スタイルが用意されており、子どもの特性に合った方法で学ぶことができます。
- 個別のサポート体制: 少人数制のため、教員や支援スタッフからきめ細かいサポートを受けることができます。障害特性を理解したスタッフによる個別指導も充実しています。
11. まとめ – 一人ひとりに合った教育環境の大切さ
私たちの実体験から学んだことは、障害のある子どもの教育において最も重要なのは、その子に合った環境を選ぶことだということです。
私の子どもとA君の進路の違いが示すように、知的障害の程度よりも「適切な教育環境」の選択が子どもの将来を大きく左右します。総合支援学校を選んだ私の子どもは社会参加を実現し、地域の中学校を選んだA君は不登校から引きこもりという難しい状況に陥ってしまいました。
これは決して、インクルーシブ教育が悪いということではありません。大切なのは、子ども一人ひとりの特性や状況に合わせた選択をすることです。そして、もしそれでも難しい状況に直面した場合、通信制高校という選択肢があることを知っておくことは非常に重要です。
通信制高校は、従来の教育システムでは対応しきれなかった子どもたちに、新たな可能性を提供します。個別最適化された学習環境、心理的安全性、そして卒業後の多様な選択肢。これらは全て、障害のある子どもたちの未来を広げるために欠かせない要素です。
私たち新開高等学院は、これまでの経験を活かし、障害のある子どもたちや不登校を経験した子どもたちに、一人ひとりに合った学びの場を提供したいと考えています。子どもたちの可能性を信じ、その子らしく輝ける未来のために、私たちはこれからも支援を続けていきます。
障害のある子どもの親として日々感じることは、子どもの成長は決して直線的ではないということ。時に立ち止まり、時に回り道をしながらも、子どもたちは確実に前に進んでいます。その歩みを温かく見守り、適切なサポートを提供することが、私たち大人の役割なのではないでしょうか。
「一人ひとりに合った教育」という言葉は簡単ですが、実現するためには様々な選択肢と柔軟な対応が必要です。通信制高校という選択肢が、多くの子どもたちとその家族にとって、希望の光となることを願っています。