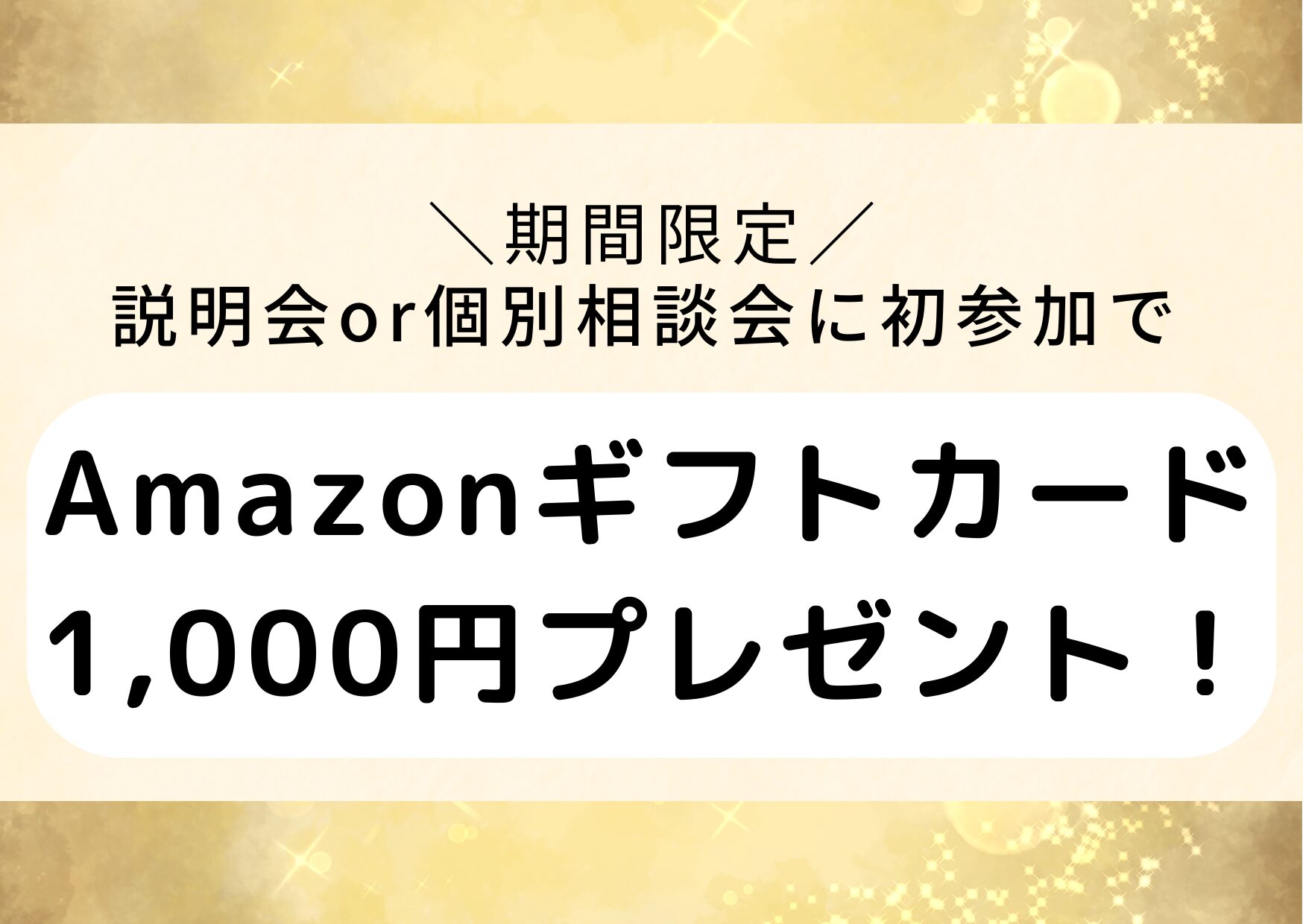【学校対応に失望して】不登校から通信制高校へ。私たち家族が選んだ未来
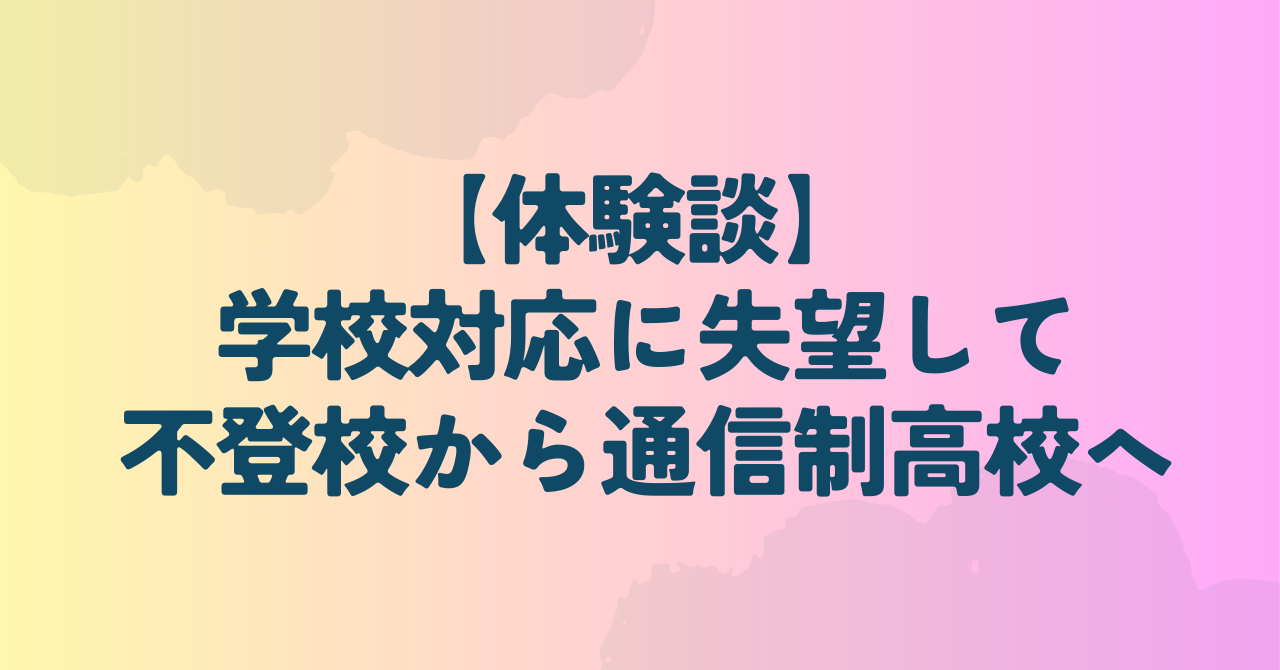
はじめに|学校の対応に悩み、不登校へ
「学校に行けなくなった」。それは、突然訪れた現実でした。
私には現在、高校3年生になる息子がおります。元気に高校へ通う今を迎えていますが、実は小学2年生の頃、学校対応の問題から大きな転機を迎えることになりました。本記事では、怪我をきっかけに学校との関係に悩み、不登校を経験し、最終的に通信制高校という新たな学びの道を選んだ私たち家族の実体験をお伝えします。
不登校の原因は様々です。いじめや学校での人間関係、家庭環境の変化など、一人ひとり異なる事情があります。しかし、どのケースにおいても共通するのは、子どもの心と体のSOSを見逃さないことの大切さではないでしょうか。
1. 登校中の事故と学校の初動対応
当時、息子は徒歩5分の距離にある小学校へ毎日1人で通っていました。地域には見守りボランティアもおり、安心できる環境だと思っていました。
幸い、私たちの自宅から小学校までは徒歩で5分ほどでしたので、保護者が付き添う必要もありませんでした。登校途中に一度だけ大きな道を渡らなければいけませんでしたが、その交差点には定年退職をしたおじさんが毎朝犬の散歩ついでに立ってくださる見守りの方もおられ、交通事故の心配はほとんどありませんでした。
しかし、ある日突然、通学途中でトラブルが起きました。精神的な課題を抱える同級生に後ろから引っ張られた拍子に、息子は前のめりに転倒。顔面を強打し、せっかく生え揃ったばかりの永久歯を1本失う大怪我を負ったのです。
救急車がようやく動き出し、時間外で口腔外科の診療科がある病院に運ばれましたが、私の咄嗟の行動も功を奏し、牛乳に浸かった歯を再建する緊急手術を受けることになりました。
学校に連絡し、救急搬送と同時に担任も現場へ駆けつけてくれました。しかしこの時点では、学校側からの説明や謝罪は十分とは言えないものでした。むしろ、事態の深刻さを理解していない様子が見受けられました。
2. 学校と教育委員会の対応に感じた違和感
事故後、学校側と加害児童の保護者を交えて話し合いが持たれましたが、そこで私たちはさらなる壁にぶつかりました。
小学校からは校長、教頭、担任の3人、加害者の子どもの母親、見守りをしてくださっていた方、主人の計6人で話し合いの場が持たれました。学校側としては通学途中の事故なので、安全義務を怠ったという一定の過失は認められておりました。
加害児童の母親は、「自分の子どもが犯人に仕立て上げられた」「本当は勝手に1人で転んで怪我をしただけなのに警察まで呼ばれて傷付いたのは自分の子どもだ」「私がひとり親だからといって全員でこのように囲んで、舐めているのか?」など、一切の謝罪もなく、学校を訴えるとまで言い出しました。
学校側は「通学中の出来事であり、安全配慮義務を怠った」と一定の責任を認めつつも、強く加害者親子に対応を求める姿勢は見せられず、教育委員会も手をこまねくばかり。
教育委員会と学校の対応は至ってまともで信頼できるものでしたが、加害者の子どもの母親の対応だけは問題が山積しておりました。結局、私の子どもはただ歯が抜けただけにも関わらず、何度か再建手術を受ける必要があり、約1か月の間ほとんど小学校に通うことができませんでした。
この一連の流れを通じて、私たちは「学校は生徒を本当に守ってくれる場所なのか」「問題が起きた時に頼れる存在なのか」と、深く疑問を抱くようになっていきました。
3. 息子に訪れた心の変化|学校への不信感
怪我の治療に加え、学校対応に不信感を抱いた息子は、学校に行くこと自体が苦痛になっていきました。
「自分が悪くないのに、なぜこんな目に?」「先生たちは本当に味方なのだろうか?」
通学に対する恐怖心、人との信頼関係への揺らぎ。これは単なる怪我の問題ではなく、子どもの心の奥深くに影響を与える出来事となりました。
しかも最後の手術が終わってから1年間は体育の授業で体を動かすことに制約が設けられ、私の子どもは長期間に渡ってストレスの溜まる日々を過ごすことになりました。主治医からは万一体育の授業で何かが起こって神経が回復していない歯が再度抜けるようなことがあれば2度と再建できないので我慢してください、と言われておりました。
身体的な制約だけでなく、精神的な疲労も重なり、少しずつ少しずつ、学校生活から心が離れていき、最終的に、息子は不登校となったのです。
4. 不登校を受け入れるまでの葛藤
最初は、「なんとか学校に戻さなければ」と必死でした。世間体や将来への不安から、学校に通うことが最善だと思い込んでいたのです。しかし、心も身体も限界を迎えた息子を見て、私たち両親も考えを改めました。
「無理に学校に戻すことが、本当にこの子のためなのか?」
学校に行くことだけが「正解」なのではない。その気づきは、私たち親にとっても大きな転換点となりました。
不登校を「失敗」と捉えるのではなく、「必要な休息」「次のステップの準備期間」として受け止めることにしました。この考え方の転換が、息子の心の回復に大きく寄与したと感じています。
5. 新たな選択肢との出会い|通信制高校を知る
そんな中、私たちが出会ったのが通信制高校という選択肢でした。
通信制高校の存在自体は知っていましたが、具体的にどのようなシステムで、どんな生徒が通っているのか、詳しいことは分かっていませんでした。不登校の子どもを持つ親の集まりや、教育相談センターでの情報収集を通じて、通信制高校について理解を深めていきました。
通信制高校は、
- 自宅中心の学習で心身の負担が少ない
- 自分のペースで学びを進められる
- サポート校を併用すれば、学習支援や進路指導も充実
という特徴がありました。また、一般的な全日制高校では対応が難しい「個別最適化された学び」が実現できる点も魅力的でした。
不登校で心身ともに疲弊していた息子にとって、通信制高校の自由度の高さ、柔軟なサポート体制はまさに「救い」だったのです。
6. 通信制高校での新たな出会いと成長
通信制高校を選ぶ際、私たちが重視したのは「子どもが安心して通える環境」と「将来の可能性を広げられるカリキュラム」でした。いくつかの学校を見学し、説明会に参加する中で、息子自身が「ここなら通えそう」と感じる学校と出会うことができました。
現在、息子は通信制高校の提携サポート校に在籍し、自分の興味がある分野に集中しながら、無理のないペースで高校生活を送っています。
以前のようにクラスに縛られることもなく、必要な時だけ先生と相談したり、仲間とプロジェクトに取り組んだり。「自分らしく学ぶ」という感覚を、ようやく取り戻すことができました。
通信制高校では、同じように不登校を経験した生徒や、様々な理由で全日制を選ばなかった生徒たちと出会いました。多様な背景を持つ仲間との交流は、息子の視野を広げることにもつながっています。
通信制高校では、年齢も住んでいる場所も様々な生徒が集まっていましたが、みんな何らかの理由でこの学校を選んだ経験を持っていたため、優しい雰囲気がありました。
これは、通信制高校を経験した方の言葉ですが、まさに息子も同じような環境の中で、自分の居場所を見つけることができたのではないかと思います。
7. 通信制高校を選んで感じたメリット
通信制高校に通うようになって、私たち家族が実感したメリットをいくつか紹介します。
7-1. 学習面での柔軟性
通信制高校の最大の特徴は、学習のペースや方法を自分で決められることです。レポート提出やスクーリング(対面授業)の日程も比較的自由に選べるため、体調や精神状態に合わせた学習が可能です。
日々の学習はオンライン授業で進め、課題も難しくなく、自分のペースで学べる環境が私に合っていました。試験も合宿中に行われ、事前に復習の機会もあったため、不合格になる生徒は少なかったです。
これは通信制高校経験者の声ですが、このような柔軟性が、不登校から学びの世界に戻るための大きな助けとなります。
7-2. 心理的な安全性
通信制高校では、生徒一人ひとりの事情や特性を理解したうえでのサポートが充実しています。息子の場合も、不登校の経験を踏まえた対応をしてもらえることで、安心して学校に通うことができるようになりました。
最初のスクーリングで泣いてしまった時、先生が『ここの学校の子達はみんな傷ついてきてる子たちだから、先生は大好きだよ』と背中をさすってくれたことは、今でも心に残っています。勉強を教える先生だけでなく、生徒を支援する専門の先生もいて、生徒の心のケアに力を入れていた環境でした。
この言葉からも分かるように、通信制高校には生徒の心のケアを重視する文化があります。これは、傷ついた心を持つ子どもたちにとって、非常に大きな意味を持ちます。
7-3. 多様な出会いと視野の広がり
通信制高校には様々な背景を持つ生徒が集まります。年齢も住んでいる場所も異なる仲間との出会いは、新たな価値観や考え方に触れる機会となりました。
通信制高校では、いじめで転校してきた生徒、妊娠で中退した後に復学した生徒、派手な外見の生徒など、多様な背景を持つ仲間と出会いました。彼らと話す中で、『自分の悩みってそんなに大したことじゃないのかな』と考えるようになりました。学校と家という限られた世界では大きく見えた悩みも、社会の広い視点から見るとそれほど重大ではないことに気づき、世界が明るく見えるようになりました。
この経験者の言葉にあるように、多様な背景を持つ人々との出会いは、自分自身の悩みを相対化し、より広い視野で世界を見ることにつながります。息子も同様に、様々な人生経験を持つ仲間との交流を通じて、自分の世界を広げています。
8. 通信制高校での学びが育んだ自立心
通信制高校での学びは、単に高校卒業資格を得るだけのものではありません。自分で計画を立て、実行する力、困ったときに自ら助けを求める力など、将来社会で生きていくために必要な力を育む機会にもなっています。
息子の場合、レポート提出の計画を自分で立てたり、分からないことがあれば先生に質問したりする習慣が身につきました。最初は親がサポートしていましたが、次第に自分で管理できるようになり、大きな成長を感じています。
通信制高校に通っていた頃、『このまま家にいてはだめだ』という思いから、地元のスーパーでレジ打ちのアルバイトを始めました。最初は声も小さく大人しかったため、注意されたりお客様からクレームを受けたりすることもありましたが、先輩方のフォローのおかげで高校3年間続けることができました。
このように、学校以外の場で社会経験を積む機会も増えることで、コミュニケーション能力や責任感が育まれます。息子も在学中にアルバイトを始め、学校だけでは得られない経験を積んでいます。
9. 通信制高校から広がる進路選択
通信制高校を卒業した後の進路も、全日制高校と変わらず多様な選択肢があります。大学進学、専門学校、就職など、生徒の希望に応じた進路指導が行われています。
息子の場合、通信制高校で自分のペースながらも着実に学びを進めることで、将来への希望を持つことができるようになりました。現在は大学進学を視野に入れ、自分の興味ある分野の勉強に取り組んでいます。
高校卒業後は地元の洋品店に就職しました。お客様として利用していた店だったこともあり、勇気を出して応募しました。先輩や店長に恵まれ、仕事も楽しくでき、性格も明るくなっていきました。同僚とは休日も遊ぶほど親しくなり、久しぶりにリアルな友人関係を築くことができました。
この例のように、通信制高校での経験が自信につながり、社会へと羽ばたくきっかけになるケースも多くあります。通信制高校は「普通の高校に行けなかった人のための場所」ではなく、「自分らしい学び方を選んだ人のための場所」なのです。
10. 不登校を経験した子どもたちへのメッセージ
現在、息子は自分のペースで学び、将来への希望を持って過ごしています。小学2年生の時の怪我から始まった困難な道のりでしたが、通信制高校という選択肢に出会えたことで、新たな可能性が開けたと感じています。
今、学校に行けずに悩んでいる子どもたちへ。学校と家という小さな世界に閉じこもっていると、悩みがとても大きく感じられると思います。でも、外の世界に出て社会を知ることで、視野が広がります。世の中にはさまざまな人がいて、多様な考え方があることに気づくでしょう。人生100年として考えると、学校に通う時間はたった12年です。今の辛い時期を乗り越えれば、新しい出会いや経験が待っています。無理に頑張る必要はなく、自分のペースで歩んでいってください。
これは通信制高校を経験した方からのメッセージですが、まさに私たち家族も同じことを息子に伝えてきました。学校に行けないことは「失敗」ではなく、新たな道を見つけるための過程なのです。
11. 保護者の方々へ|子どもの可能性を信じること
不登校の子どもを持つ親として、最も大切だと感じたのは「子どもの気持ちに寄り添うこと」と「多様な選択肢を模索すること」です。
お子さんのことを考えると不安だと思いますが、私自身が最も救われたのは、家族に理解され、普通に接してもらえたことでした。学校に行けないことは『負け』でも『逃げ』でもありません。頑張りすぎて疲れているだけなので、少し休息を与えてあげてください。特別扱いではなく、普通に接することが大切です。学校だけが全てではなく、勉強はどこでもできますし、友達も社会人になれば新たにできます。この時期を親子で乗り越え、いつか『あんなこともあったね』と笑って話せる日が来ることを願っています。
この言葉のように、不登校は「終わり」ではなく「新たな始まり」と捉えることで、子どもの可能性を広げることができます。通信制高校という選択肢は、その一つの道であり、私たち家族にとっては最善の選択となりました。
まとめ|「学校対応に悩んだら、通信制高校という選択肢を」
今回の経験を通じて私たちは痛感しました。
- 学校の対応が必ずしも子どもの味方になるとは限らない
- 不登校は「逃げ」ではなく「次への準備」である
- 通信制高校という柔軟な学びの場がある
学校の対応に悩み、どうしていいか分からないとき。無理に現状を変えようとせず、新しい環境に踏み出す勇気を持つことも大切です。
不登校という辛い経験は、当時は世界が終わったかのように感じられましたが、振り返ると人生の大切な転機となりました。通信制高校での多様な出会い、アルバイト経験を通じた社会性の獲得、全ての経験が私を形作っています。辛い時期があったからこそ、小さな困難を乗り越える力や他者への共感力が育まれました。不登校は終わりではなく、新たな可能性の始まりなのかもしれません。あなたの人生も、今の困難を乗り越えた先に、きっと素晴らしい未来が待っています。
もし、今同じような悩みを抱えている方がいれば、通信制高校・サポート校という選択肢もぜひ視野に入れてください。お子さんが本来の輝きを取り戻す場所は、必ずどこかにあります。
私たち家族の経験が、同じような状況にある方々の一助となれば幸いです。